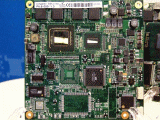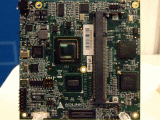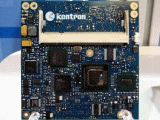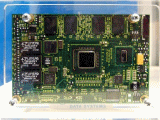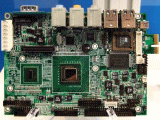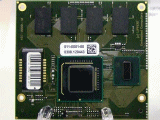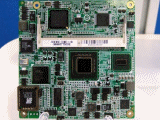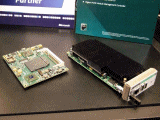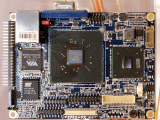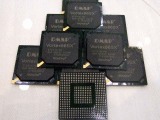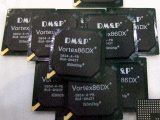組込システム会議「ESC SV 2008」レポート【x86プロセッサ関連展示編】
どっこい生きてたmP6
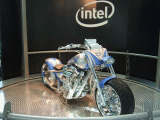 |
| 【写真01】あまりに入り口の脇過ぎて、むしろ目にとまってないのではないかという立地。あまり見る人も居ないまま、ぐるぐると回り続けるのを、警備員が仕方なさそうに監視しているのは、むしろ哀愁を誘うものがあった |
会期:4月14日~18日(米国時間)
会場:米国サンノゼ McEnery Convention Center
さて、やっとESC SVの展示物の話をすることができる。まずは比較的興味あるであろう、x86系プロセッサの話をしてみたい。会場には「4つ」のx86プロセッサベンダーがすべてブースを設けると共に、これらのCPUを使ったボードを出展しているベンダーも多いため、至る所にx86プロセッサが溢れているという構図は変わらない。ただ、PC向けではなくEmbedded向けだから、多少展示される内容は通常と異なることになる。それらの動向をベンダー別にご紹介したい。
●Intel ~広告の割にやる気なし。ただし興味ある展示も~
会場入り口すぐのところに巨大なブースを設けた割りに閑散としていたのがIntel。こちらで触れたバイクは、McEnery Convention Centerの入り口のすぐ脇に展示されていた(写真01)が、単に展示されているだけという風情。肝心のブースは、Core 2プロセッサやAtomプロセッサを使ったいくつかのカード(写真02~08)が展示されているほかは、あまり目立ったものはないという有様。「Diamondvilleは?」と聞いても「そんなものは知らない」とまで言われてしまう状況で、あとはTolapaiの実演デモが行なわれていたのが目立つ程度だった。
ただし、よく見るとちゃんと変なものが置いてあってちょっと安心(?)した(写真09、10)。10Gbit Ethernet(10GbE)そのものはIEEE 802.3aeとして2002年に標準化されているが、これは光ケーブルを使ったもののみ。銅配線では同軸ケーブル4本を使ったもの(10GBASE-CX4)がIEEE 802.3akとして2004年に標準化された。UTPケーブルを使い、通常のRJ-45に接続できるいわゆる10GBASE-Tが標準化されたのは2007年に入ってから。こちらはUTPで無理やり10Gbpsを通すために、かなりPHYの構造が複雑になっている。
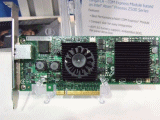 |
 |
| 【写真09】Intelは未発表の10GBASE-Tのアダプタを参考展示。おそらく完成したらIntel PRO/10GbEのシリーズとして販売されるのであろう | 【写真10】ACT/Linkの下に1Gig/10GigのLEDが並んでおり、コネクタもどう見てもRJ-45で、10GBASE-Tと思われる |
このマーケットで最初に製品アナウンスを行なったのがTeraneticsで、ほかにSolarflare/Plato/Neterionが製品出荷のアナウンスをし、Aquantiaが2008年中旬の出荷を目指しているとしている。
Intelはこれに関してアナウンスは一切行なってないが、2007年秋のIDF(今年のIDFは行って無いので未確認)では試作品を展示しており、何らかの作業を行なっていることは確認できていた。今回展示の製品はそれよりずっと進化しており、だいぶ完成に近いことを伺わせる。ポイントは2点ある。
1) インターフェイスがPCI Express x8になった
従来、Intelは82859EXという10GbEのMACを開発し、既にこれを搭載した10GBASE-SR/LR/CX4のカードを発売している。ただしこのコントローラのインターフェイスは133MHz/64bitのPCI-Xである。今回登場した製品はPCI Express x8になっており、またブリッジなどの存在も確認できないことから、これは新しいMACを開発したと想像される(写真09の右側)
2) PHYの消費電力は凄そう
10GBASE-SR/LR/CX4の場合、PHYにヒートシンクこそついていても、Active Fanが搭載されているものは無かった。が、こちらはPHYにそれなりのActive Fanが搭載されており、かなり発熱が多そうだ。
一時期ICH10には10GBASE-Tが入るという噂があった(結果から言えば、ICH9のリビジョンアップ品になった)が、帯域的にもDMIでは到底追いつかないし、MACを内蔵し、PHYを外付けという形にするにしても、発熱の具合から見て当分デスクトップに入りそうには見えない。暫くはサーバー向けの拡張カードに留まると考えるのが妥当だろう。
●AMD ~まるでやる気なし。Embeddedの方針を変えたことが明確~
次はAMDである。今回はっきり分かったことは、AMDはEmbedded Marketに対する取り組みを明確に変えたことだ。従来はGeode GX/LX/NXの製品ラインで小規模なEmbedded Deviceへのアプローチを図っていた同社だが、今回の展示からはそうした事に対する取り組みはほとんど見られない。
Geode LXについては摂氏-40度~+85度という広い動作温度をアピールしており、サードパーティ各社もこれをウリにGeode LX搭載モジュールを展示していたが、これは別に新しい話ではない。会場には一応50x15 Initiativeに沿ったサンプルなども並んでいたが、まるでやる気はなし。何より、ここで触れたSPARK Your Imaginationのハードウェアに今のところAMDの製品が入る予定が無い(Keith&Koep GmbHはPXA270CE、iCOPはVortex86SX、VIA Technologiesは当然VIA C7。AdvantechとSpecial Computingは現時点で未公表)あたりに、これ以上積極的にGeodeの製品ラインを販売して行こうという意思が感じられない。
その代わりにAMDが現状で積極的に展示を行なっていたのは、通信やストレージ向け製品。Advanced MCモジュールのサンプル(写真11)や、Bridge Bay RDK(写真12)、DTI ATCA Reference Design(写真13)、ATCA Server Blade(写真14)、ATCA Module(写真15)、Huawei社のATCA Server Blade(写真16)などが展示されており、明らかにEmbeddedといっても方向性が従来と大きく変わってきている事が見て取れる。実演されていたデモも、NIのPXIe-8130でデータ転送レートを示すといった類だった(写真17)。
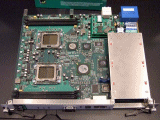 |
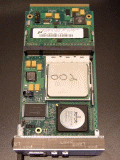 |
| 【写真14】同じくATCA向けのサーバーブレード。Opteron 2000 HEシリーズ(Dual or Quad)を搭載、8GBのメモリを利用できる。オプションで4GB Flashとか30GBの1.8インチHDDなども搭載可能 | 【写真15】おそらく写真11の右側と同じもので、ヒートシンクを取り去った姿ではないかと思う。これはATCAのブレードに装着する形で実装される事を想定していると思われる |
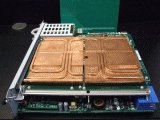 |
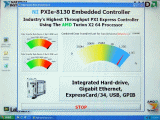 |
| 【写真16】1.8GHzの55W Opteronを4P搭載できるが、8P構成も可能とか書いてあるのが恐ろしい。ヒートシンクが凄まじいことに | 【写真17】NI PXIe-8130はNATIONAL INSTRUMENTSが提供する計測用モジュール。同社はLabViewという開発/計測ソフトウェアをコアに持っており、このLabViewがデータを取り込んだり、分析するためのハードウェアとして、こうしたモジュールを提供している。Turion X2ベースのモジュールで、1GB/secを超えるデータのサンプリングが可能というのがこのデモの示すところ |
いわゆるコンサバティブなEmbeddedの場合、「細く長く」といった商売の仕方になることが多い。つまり設計開始から商品発売までの時間も長いし、いきなり商品がバカ売れすることもそう多くない。なので、ある程度商売が軌道にのるまでは、なかなか売り上げが伸びない。その代わりといっては何だが、一度売れ始めると、それは長期(10年を超えることも珍しくない)に渡って売れる。したがって長期的に見れば、売れ線の商品をいくつか持っていると、それだけで黙っていても毎月売り上げが立つという世界である。
こうしたビジネスは、IntelやAMDが主戦場とするPC向けのCPUとは全く異なる世界である。したがってPC的な視点でEmbeddedに乗り込むと、さっぱり売り上げが伸びずに経費だけ掛かる→撤退といったことになる。AMDはかつてAM29000とかAMD Elanで失敗し、Alchemyでも痛い目にあっていた筈だが、またもや同じ事をGeodeに対して行ないそうな雰囲気がありありと感じられる。このままだと、Bobcatも本当に出てくるのか怪しいと強く感じた展示であった。
●VIA Technologies ~ポロっと漏らした「C8」~
次は、案外元気なVIA Technologies。同社は今回大きく分けて2つの展示を行なっていた。1つはC7を搭載したEden系プラットフォーム、もう1つはS3の4300E Embedded Multimedia Graphics Processorである。これを順に紹介しよう。
まずC7。CPUそのものは既に公開済みで珍しいものもないし、C7を搭載したEden製品も順次出荷されているから、これもそれほど珍しいわけではない。が、やはり目玉はSPARK Hardware Providersの1つに選ばれたこと(写真18)。結果として「ARTiGOってなんだ?」(写真19)ということで、注目を集めたものと思われる。ほかにも会場にはEPIA P700(写真21)やEPIA P710(写真22)などの新製品が展示され、歴代EPIAシリーズが並んでいるのはなかなか壮観であった。
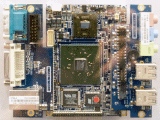 |
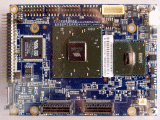 |
| 【写真21】Pico-ITXの新製品。C7/1GHzにVX700という組合せはEPIA PXと同じ(500MHzのULV C3搭載版もある)だが、LVDSインターフェースやGbE(EPIA PXは10/100BASE-T)を搭載しているあたりがちょっと異なる | 【写真22】こちらで触れたSUMITコネクタを搭載したEPIA P710。SUMIT-AにはPCI Express x1が4本とUSB、I2C、SPI、LPCの各インターフェイスが、SUMIT-Bには追加のPCI Expressレーンが出ている |
もう1つの目玉がS3 4300E。会場にはこれを搭載したMMC 7000(写真23)も展示されていたが、それよりも目玉だったのは4300Eと同じChrome 430 GTを使ったリアルなドライブシミュレータだ(写真24)。誰でも運転できるとあり、常に長蛇の列を成していた。
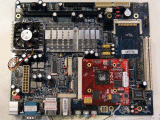 |
 |
| 【写真23】FlexATXボードにC7/1.5GHzとCN800チップセットを組み合わせ、PCI Express x16のMXM-IIスロットに4300E(赤いカード)を装着している | 【写真24】動画を見ていただくと分かるが、黄色いシャーシの後端にはアクチュエータがついており、車の動きに合わせてシャーシが前後左右に移動するという仕組み。このあたりも全部PCで制御してるとか |
このシミュレータ、動画をご覧頂くと分かるが、かなりスムーズに動く。そこでS3のジャケットを着込んだスタッフに「これのグラフィックは?」と聞くと、Chrome 430 GTを2枚装着して、AFR(Alternate Frame Rendering)で動作させているとの事。ついでに「ではCPUは?」と聞くと、「(ものすごく悔しそうに)今はIntelのCore2を使ってる。でももうちょっとしてC8が出てきたら、同じだから」との答えが返ってきた。「C8?」と聞くと、C7のDual Coreとの事だった。ただ教えてくれたのはここまで。ネイティブ(Core 2 DuoとかAthlon 64 X2の様に1ダイで2コア)なのか、MCM(Pentium Dの様に2つのダイを1つのパッケージに載せたもの)なのかは教えてくれなかった。
すっかりPC向けから撤退したと思ったVIAであるが、水面下ではいろいろやっているようで、ちょっと嬉しい。気になるのは、その場合デュアルビデオカードが使えるマザーボードはどうなるのかということ。今年のCOMPUTEXではVTF(VIA Technology Forum)が中止になったり、そもそもVIAがブースを出さないといった話があるだけに、なかなか確認の術が無いのが残念ではある。
●DM&P Vortex86 ~10年生き延びたm6P~
最後はこの話である。SPARK Hardware ProvidersにICOP Technologyが入っているという話はこれまでもしてきた。実際には同社のeBOX-2300SXという製品がこれに相当する(写真25、26)。これに使われているVertex86SXは何かという話だが、これを製造しているのはDMP Electronicsである。両者の関係を知るにはこのあたりを見ていただくのが早いだろうが、複数の企業から成るDM&Pグループがあり、DMP Electronicsは開発と製造、ICOP Technologyは販売をそれぞれ担っている。
そのDMP Electronicsが開発するVertex86SXとは、結論から言えばRiSE mP6をベースとしたSoCである。このあたりは、DMP Electronicsのページを見ると察しやすい。
同社の最初の製品であるM1667Dは、型番からお分かりの通り、かつて(ULiにPC関連部門が分社化される前に)ALiが製造していた、i386SX互換CPUコアを搭載したSoCである。これに引き続き登場したのがVortex86であるが、これはVortex86のデータシートを見ればお分かりの通り、SiSがかつて販売していたSiS550シリーズのSoCである。このSiS550は、独立系CPUメーカーとして'98年にRiSE Technologyが開発したiDragon mP6というCPUコアに、同社が持っていた周辺回路を統合したSoCであり、2007年位までは辛うじて製品ラインナップに残っていたのだが、遂に今年に入ってラインナップから消えてしまった。
もともとRiSE Technologyは'98年にmP6を発表、ついで'99年にはTigerというコード名のノート向けCPUをMicroProcessor Forum 1999で発表予定だった。ところがその発表は直前でキャンセル。Tigerのほか、mP6にキャッシュを搭載したmP6-IIというプロセッサも予定されていたが、どちらも消滅してしまった。その後RiSE TechnologyはSTMicroelectonics及びSiSと提携。両社にmP6コアを提供し、STMicroelectronicsからは逆にSTPC ConsumerIIという386SX互換コアの提供を受けて、Embedded向けに製品をシフトして生き延びる道を選んだが、最終的には'99年にSiSに買収されてしまった。
さて話を戻そう。Vertex86は、このSiS550シリーズをそのまま販売していた形になるが、ここにDMP Electronicsが手を入れたのがVortex86SXである。具体的には、
・動作周波数を300MHzに引き上げ
・FPUと、恐らくMMXユニットも削減
・DDR2のメモリコントローラを搭載
・USB 2.0のコントローラを追加
を始めとして、さまざまな手が入ったものになっている。特に周辺回路に関しては、SiS550シリーズに比べて随分強化されているようだ。面白いのは、元々のRiSE mP6が8段のパイプラインなのに、Vortex86SXでは6段に減っていることだ。これに関してDMP Electronicsのブース(写真27)で「これ(Vortex86SX)って、元はSiS550だよね?」と確認したら素直に「そう」と返事が返ってきたので、間違いはないと思う。プロセスの違いを考えれば、新機能を追加したり動作周波数をうんと引き上げるので無い限り、パイプラインの段数を減らすのはそれほど難しくなかっただろうから、そう不思議ではない(写真28)。
このVortex86SXの新型が、Vortex86DX(写真29)である。違いは、まずプロセスを微細化(130nm→90nm)したことで、消費電力を増やさずに動作周波数を600MHzまで引き上げたこと、FPUを搭載した(ということは、またMMXユニットも復活している可能性が高い)ことがメインだそうだ。
それにしても、もっと高い性能を目指したTransmetaとかCyrixはこの10年の間に消えてしまい、Embeddedに特化した筈のNSのGeode GXも風前の灯なのに、事もあろうに(というのも失礼だが)RiSEのmP6が未だに生き残っているあたりが、Embeddedという業界の特殊性(なのか、PC業界がむしろ特殊なのかは判断つかないが)を感じさせてくれる。
なおICOPに「なぜVortex86DXでキットを作らなかったの?」と聞いたら、「Vortex86SXで十分だと顧客に言われている」との事。MIDなどへの提供も今後は考えられるが、今のところ明確なプランは無いという話だった。
□ESC SV 2008のホームページ(英文)
http://www.cmp-egevents.com/web/esv/home
□関連記事
【4月18日】【ESC】Windows Embeddedの製品ラインを再編
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0418/esc03.htm
【4月17日】【ESC】PC/104 Embedded Consortium、「PCI/104-Express」らを承認
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0417/esc02.htm
【4月15日】【ESC】組込システム会議「ESC SV 2008」開幕レポート
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0415/esc01.htm
(2008年4月21日)
[Reported by 大原雄介]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp お問い合わせに対して、個別にご回答はいたしません。
Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.