 |


■笠原一輝のユビキタス情報局■Intelは、Nehalem世代で5つのCPUコアを投入 |
Nehalem世代のIntelのCPUコア計画が徐々に判明してきた。
情報筋によれば、IntelはNehalem世代のクライアントPC向けに5つのCPUコアを投入することを計画しているという。すでに判明しているハイエンドPC向けのBloomfieldのほか、デスクトップPC向けにLynnfield(リンフィールド)とHavendale(ヘイブンデール)、ノートPC向けにはClarksfield(クラークスフィールド)とAuburndale(アーバンデール)を2009年に投入する計画であるという。
中でも、メインストリーム向けとなるHavendale、Auburndaleの2製品は、CPUの内部にGPUを内蔵したノースブリッジがMCMの形で実装されており、従来のチップセットで言えばサウスブリッジに相当するPCH(Platform Controller Hub)と呼ばれるIbexpeak(アイベックピーク)と組み合わせて2チップ構成でPCを実現できるようになる。
●Nehalem世代の最初の製品となるBloomfield
最初に登場するのが、2008年の第4四半期に投入が計画されているデスクトップPC向けのBloomfieldだ。Bloomfieldは4コア構成で、トリプルチャネルのDDR3メモリコントローラがCPUダイに統合される。以前はCSIと呼ばれていたQPI(Quick Path Interconnect)をシステムバスとして利用し、PCI ExpressバスとサウスブリッジのブリッジとなるIOH(I/O Hub)のTylersburg(タイラスバーグ)に接続され、さらにその先にはICH10がサウスブリッジと接続される構成になっている。
もともとこのBloomfieldは、どちらかと言えばUP(UniProcessor)のワークステーション向けに開発された製品で、クライアント用途だけでなくXeon向けにも投入される製品となる。このため、マザーボードの設計などもおそらく6層基板などが前提となるため、製品のコストも決して安価ではない可能性が高い。
●超ハイエンドに留まるBloomfield、メインストリームには別コアを投入
このため、このBloomfieldは今で言えばCore 2 Extreme向けなどの超ハイエンドのみに留まり、メインストリームには別のコアが投入される。その役割を担うのが2009年前半に投入が計画されているデスクトップPC向けのLynnfield(4コア)/Havendale(2コア)、ノートPC向けのClarksfield(4コア)、Auburndale(2コア)となる。なお、ノートPC向けのClarksfield/Auburndaleは、2008年の第2四半期に投入されるMontevinaプラットフォームの後継製品となるCalpella(カルペラ)向けプロセッサとなる。
 |
| 【図1】IntelのCPUコアロードマップ(筆者予想) |
基本的にはLynnfieldのノートPC版がClarksfield、HavendaleのノートPC版がAuburndaleとなるが、実際には逆でClarksfieldのデスクトップPC版がLynnfield、AuburndaleのデスクトップPC版がHavendaleということになる。というのも、Intelは65nmの世代からモバイル向けのコアをデスクトップPCに拡張するという手法をとっているからだ。ノートPC向けのMeromをデスクトップ版に拡張したものがConroeであり、45nm世代でもまずはノートPC向けのPenrynを開発し、それを元にデスクトップ版としてYorkfield/Wolfdaleを作り出している。それはこのNehalem世代でも同様で、まずノートPC向けの製品が開発され、その派生品としてデスクトップ製品が作られているのだ。
ただし、実のところIntelは別の手法も検討していた。具体的にはBloomfieldのローエンド版を作るという手法だ。Intelの社内では、Tylersburgの廉価版として統合型GPUとメモリコントローラを内蔵した「Summitlake」というコードネームで呼ばれていたIOHの計画も以前は存在していた。これにBloomfieldのデュアルコア版を接続し、メインストリーム向けとするというプランだ。
しかし、この計画はその後キャンセルされてしまったようで、ノートPC向けのコアをデスクトップPC向けにリファインして利用する現在のプランに落ち着いたようだ。この手法のメリットは、同じダイとして製造することができるので、製造効率が優れておりトータルで見れば低コストで製造できることだ。言うまでもなく低コストで製造できることは半導体製造メーカーにとっては死活問題ともいえ、こちらの手法に落ち着くというのはロジカルな選択だったといえるだろう。
このことにより、BloomfieldのデスクトップPCにおける位置付けは、超ハイエンドに留まり、いずれLynnfieldに置き換えられるということを意味する。ちなみに、CPUソケットもBloomfieldはLGA1366というソケットであるのに対して、Lynnfield/HavendaleはLGA1160という互換性を持たないものになるという。となれば、NetBurst世代の序盤にSocket 423のWillametteが登場したことや、P6世代の最初のPentium Proと同じようなポジショニングになると考えればわかりやすいだろうか。もっとも、デスクトップPC向けで、トリプルチャネルのDDR3とQPIが使えるのはBloomfieldだけということになるので、パフォーマンス重視のユーザーには引き続き選択肢となりうる可能性は高い。
●QPIはサポートしないメインストリーム向けクアッドコアのLynnfield/Clarksfield
メインストリーム向けのクアッドコア製品となるのがLynnfieldとClarksfieldだ。いずれも、HTテクノロジにより仮想マルチスレッディング(SMT)をサポートする。Bloomfieldと同じように8MBのL2キャッシュを内蔵しており、Bloomfieldで追加されるSSE4の追加命令をサポートする。
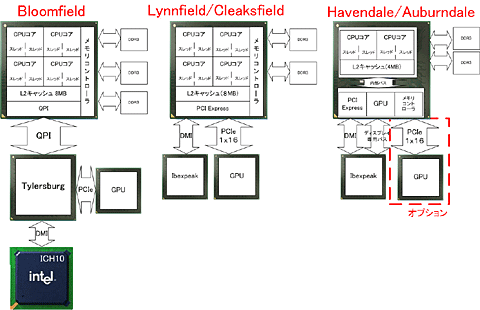 |
| 【図2】Bloomfield、Lynnfield/Clarksfield、Havendale/Auburndaleの違い |
Bloomfieldとの大きな違いは、QPIをサポートしないこと、統合されているメモリコントローラがデュアルチャネルのDDR3であること(Bloomfieldはトリプルチャネル)、さらにはCPUから直接PCI Express x16が出ていることだ。結局のところQPIのメリットは、AMDのHyper Transportと同じように、複数のプロセッサを接続する時に制限が少ないことと、開発コードネーム“Geneseo”と呼ばれる各種アクセラレータを接続することができることにあると言ってよい。しかし、クライアントPCの場合はどちらも必要度は高くないので、QPIのサポート機能を落とし、PCI Expressの機能を実装し、ノースブリッジを不要というアプローチが採られたのだと考えることができる。QPIとPCI Expressの物理層はほぼ同じものだと考えることができるので、QPIをPCI Expressに置き換えるのはそう難しいことではないだろう。
また、ノースブリッジ相当の機能はみなCPU側に実装されてしまったので、従来のサウスブリッジはCPUに直接接続されることになる。Ibexpeakと呼ばれるPCH(Platform Controller Hub)がそれで、従来のICHに置き換えて利用されることになる。
●MCMでGPUをCPUに統合するデュアルコアのHavendale/Auburndale
Nehalem世代でメインストリーム向けのデュアルコア製品となるのがHavendale(デスクトップ版)、Auburndale(ノートPC版)だ。
クアッドコアのLynnfield/ClarksfieldとHavendale/Auburndaleの最大の違いは、ノースブリッジ機能の実装方法だ。Lynnfield/Clarksfieldがメモリコントローラ/PCI Expressブリッジという以前のノースブリッジ相当の機能をCPUダイに統合しているのに対して、Havendale/Auburndaleはそれらのノースブリッジ相当の機能は別チップとしてCPUプレート上にMCM(Multi Chip Module)として実装される。
Intelがこうしたアプローチを採った背景には、2つの理由が考えられる。1つは開発時の理由、もう1つが製造時の理由だ。こうした設計にしておけば、開発フェーズが異なるCPUとGPUをそれぞれ別々に開発し、バリデーション(動作検証)の段階で1つにまとめてテストを行なうことができる。GPUをCPUに統合した場合、例えばGPU側に何らかの不具合があって修正するという場合、関係のないCPU部分も含めてやり直しということになるので効率がよくない。
製造面でも、それぞれ別々に製造した方が歩留まりの点で有利だ。具体的には、両方が1つのダイとして製造された場合、GPUだけがだめでもCPUの方も使えなくなるが、それぞれが別々に製造されれば、GPUがだめでもCPUの方は使うことができる。
ただし、それぞれのチップがCPUプレート上で外部バスで接続されることになるので、ダイ上で統合されている場合に比べればメモリレイテンシなどの点で不利になる。それでも、ソケットを介して接続されている場合に比べれば圧倒的に高速に設定できるので、FSBを介して接続する従来の形に比べればメモリレイテンシなどが削減できるはずだ。
Havendale/Auburndaleの仕様は、SMTに対応した2つのCPUコアと4MBのL2キャッシュ、デュアルチャネルのDDR3メモリコントローラ、1x16のPCI Expressとなっており、やはりDMIを介してPCHとなるIbexpeakと接続される。
なお、HavendaleのCPUソケットはLynnfieldと同じLGA1160になり、ピン互換で同じマザーボードを利用することができる可能性が高い。なお、Havendaleにも1x16のPCI Expressをサポートしており、外部GPUを接続して利用することができる。
●ディスプレイの出力はPCH側から出される
すでに触れたように、Lynnfield/Clarksfield/Havendale/Auburndaleと組み合わせて利用されるPCHは、Ibexpeakと呼ばれる最初の世代のPCHとなる。
Ibexpeakは、従来のICHでも利用されていたDMI(Direct Media Interface)を利用してCPUと接続されるが、それ以外にもDisplay Connectと呼ばれるディスプレイ出力の専用バスも用意される。このDisplay Connectが用意される理由は2つある。1つはアナログ信号をソケットを介して出力したくないからで、もう1つはHDMIポートのためだ。
仮にCPU側からディスプレイ出力をした場合、GPU内部のDACで変換されたアナログ信号を、CPUソケットを介して出力することになる。ある程度コントロールの効くデジタル信号とは異なり、アナログ信号の場合コントロールが難しく、不確実さが増えて信頼性の低下を招く可能性がある。ボード上に完全に実装された状態ならともかく、ソケットを介すとなると、ある個体ではきちんと動いても、別の個体では動作しないという可能性が出てくる。
また、HDMIポートを実装する場合、必ずオーディオ信号をマージして出力する必要がある。このため、オーディオ信号をノースブリッジ、すなわちCPU内部に持ってくるか、ビデオ信号の方をPCHの方に持ってくる必要がある。上で述べたように、オーディオ信号、すなわちアナログ信号をソケットを介してCPU内部に持ってくるのはリスクが非常に高い。このため、ビデオ信号の方をデジタルのままPCHに持ってきて、PCH側のDACを利用してDVIやHDMI、アナログRGBなどの出力を行なうのだ。
なお、情報筋によれば、このほかにもIbexpeakでは14ポートのUSB(2つのEHCIコントローラ)、6ポートのシリアルATA、統合されたTPM、8x1のPCI Express、PCIスロット、LPCなどをサポートするという。
Havendale/Auburndaleに内蔵されているGPUを利用すると、PCHとわずか2チップでPCを作れるようになる。マザーボード上に搭載されるチップセットもPCH1チップですむので、マザーボードの製造コストは削減することが可能になるだろう。
ただし、Intel以外のサードパーティのチップセットベンダに関しては、ビジネスチャンスを喪失することになるということは言えるのではないだろうか。今のところIntelはDMIのライセンスをサードパーティには与えておらず、おそらくこのNehalem世代でもその方針に変更はないと考えることができる。
外付けGPUを持つベンダはともかく、現在ノースブリッジ/サウスブリッジを提供するようなサードパーティのチップセットはIntel向けの市場からの退場を迫られることになる可能性が高いのではないだろうか。もっとも、この傾向はIntelだけでなく、AMDにも言えることで、AMDもFusionのCPUをリリースした時には、やはり同じ問題をサードパーティのチップセットベンダに突きつけることになる。
□関連記事
【11月9日】【海外】2008年中に95%をデュアルコアにするIntel CPUロードマップの秘密
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1109/kaigai399.htm
【10月26日】【海外】Intel版「8x4」で広がる2008年のCPUロードマップ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1026/kaigai397.htm
【10月22日】【海外】8コア×8ソケットで64コア128スレッドの「Beckton」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1022/kaigai395.htm
(2007年11月26日)
[Reported by 笠原一輝]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.