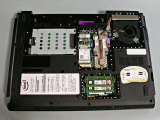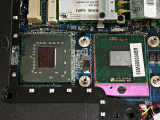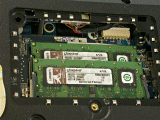|


■多和田新也のニューアイテム診断室■Intelの新Centrino Duoプラットフォーム
|
Intelは5月9日、新しいモバイル向けチップセット「Mobile Intel 965 Express」シリーズを発表。これまで「Santa Rosa」(サンタローザ)のコードネームで伝えられた、新しいCentrino Duoプラットフォームを形成するチップセットとなる。この評価機を利用する機会を得たので、実機を利用してSanta Rosaプラットフォームが持つ新機能の動作を見ていきたい。
●800MHz FSBのCore 2 Duo Tシリーズを利用する新プラットフォーム
すでに、Santa Rosaプラットフォームの詳細については、Intel Developer Forum(IDF)や同社のイベントなどで多くの情報が伝えられているが、本稿では実機を利用した機能紹介を行ないつつ、改めて概要を紹介していきたい(図1)。
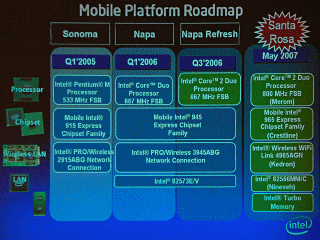 |
| 【図1】Centrinoプラットフォームの変遷とSanta Rosaを構成するパーツ |
まずはCPUについて。Santa Rosaの前世代であるNapaプラットフォームは、当初、YonahコアのCore Duoを利用し、その後、MeromコアのCore 2 Duoが利用された。Santa Rosaプラットフォームでも、引き続きMeromコアのCore 2 Duoが利用されることになるが、FSBが800MHzへ引き上げられた。
新たにラインナップされる800MHz FSBの製品は、表1の通りである。表中の動作クロック欄に(最大)と表記した理由は後述するが、注意したいのはT5000番台のプロセッサ・ナンバがなくなった。これまで、L2キャッシュが2MBのモデルは、Core 2 Duo T5000シリーズとして明確に分けられていたが、今回のラインナップでは4MBモデルと同じ、T7000番台のプロセッサ・ナンバが割り振られるようになっている。
| ブランド | プロセッサ・ナンバ | 動作周波数(定格/最大) | L2キャッシュ | 価格(1,000個ロット時) |
|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo | T7700 | 2.40GHz/2.60GHz | 4MB | 530ドル |
| T7500 | 2.20GHz/2.40GHz | 316ドル | ||
| T7300 | 2GHz/2.20GHz | 241ドル | ||
| T7100 | 1.80GHz/2GHz | 2MB | 209ドル | |
| Core 2 Duo低電圧版 | L7500 | 1.60GHz/1.80GHz | 4MB | 316ドル |
| L7300 | 1.40GHz/1.60GHz | 284ドル |
続いて、Santa Rosaプラットフォームの核となるMobile Intel 965チップセットであるが、グラフィック非統合型の「Intel PM965」、グラフィック統合型の「Intel GM965」がラインナップされる。後者のグラフィックコアは「Intel GMA X3100」と呼ばれる。ハードウェア自体はデスクトップ向けのIntel GMA X3000と同じもので、ドライバレベルで機能差が設けられているという。
これらに組み合わせられるICHは、ICH8-MおよびICH8-M Enhancedの2種類。後者は4月に発表されたビジネス向けの「Centrino Pro」プラットフォームに対応するバージョンで、Intel AMTサポートなどのビジネス向けの機能が組み込まれている。
今回テストするのは、Intelから借用したSanta Rosaプラットフォームの評価機である(写真1)。この評価機は、CPUにCore 2 Duo T7700、チップセットにIntel GM965+ICH8-Mを搭載したものだ。COMPAL製のベアボーンをベースとしたもので、背面から各種パーツを確認することができる(写真2~4)。
ちなみに、IntelではSanta Rosa発表を機に、IntelはCentrino Duoプラットフォームのロゴを変更した。今回の評価機でも早速、その新しいロゴのシールが貼られていた(写真5)。
この評価機におけるベンチマーク結果は表2の通り。今回は適切な比較対象PCを用意できなかったので、単体のスコアになっている。
CPU関連のテストは全般に良好な結果。グラフィックは、ゲームを快適にプレイできるレベルにあるとは言い難いものの、従来のIntel 945GMでは1,000を超えるかどうかであったPCMark05のGraphics Scoreが1,700超と、良い結果を見せている。メモリパフォーマンスは、意外に伸びなかった印象だが、DDR2-667を利用している点を考えれば仕方ない。
注目はHDDである。ノートPC用の2.5インチHDDを利用している場合、PCMark05のHDD Scoreは2,000台、Windows Vistaのエクスペリエンスインデックスでは3~4といったところが妥当なのだが、今回の評価機はかなり良いスコアとなっている。これは、Santa Rosaで採用されたTurbo Memoryの効果と思われる結果だが、詳細は後述したい。
| PCMark05 Build 1.2.0 | PCMarks | 4,264 |
|---|---|---|
| CPU Score | 5,743 | |
| Memory Score | 4,751 | |
| Graphics Score | 1,794 | |
| HDD Score | 3,313 | |
| 3DMark06 Build 1.1.0 (1024×768ドット/32ビットカラー) |
3DMarks Score | 561 |
| SM2.0 | 168 | |
| HDR/SM3.0 | 220 | |
| CPU Score | 1725 | |
| 3DMark05 Build 1.3.0 (1024×768ドット/32ビットカラー) |
3DMarks Score | 873 |
| CPU Score | 7,371 | |
| Windows Vista エクスペリエンスインデックス |
プロセッサ | 5.3 |
| メモリ(RAM) | 4.5 | |
| グラフィックス | 3.4 | |
| ゲーム用グラフィックス | 3.5 | |
| プライマリHDD | 4.9 |
●シングルタスク時にクロックアップを行なう「Intel Dynamic Acceleration」
では、順にSanta Rosaで実装されたユニークな機能のチェックを行なっていきたい。まずは、「Intel Dynamic Acceleration」(IDA)と呼ばれるものだ(図2)。この機能は、一言でいえばオーバークロック機能と言い換えても差し支えないものであるが、単純なオーバークロックを行なうものではない。
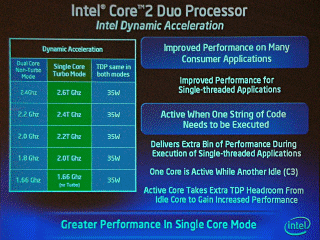 |
| 【図2】Intel Dynamic Accelerationの説明スライド。FSB 800MHzのMeromでのみサポートされる |
IDAはシングルタスク/シングルスレッドのアプリケーションを動作させている時に、そのコアのみをクロックアップするもの。IDAが機能している時、もう片方のコアはC3ステート(アイドル)まで落ちており、クロックが上げられた状態でもTDPは上昇しない仕組みになっている。
クロックアップされる量は、CPUの倍率を1つ上げた分。例えば、Core 2 Duo T7700は通常、最大2.4GHzで駆動するが、IDA有効時には片方が2.6GHzまで引き上げられることになる。
このIDAの動作を評価機で試してみようと思ったわけだが、結論からいうと、動作していることを確認できなかった。実際には動作クロックの上がっていて、クロックの監視に利用したCPU-Zに反映されていないだけという可能性もある。しかし、シングルタスクのベンチマークをいくつか実施してみてもスコアに変化はなく、実際にクロックは上がっていない可能性のほうが高いと考えている。この理由は2つある。
1つは動いているアプリケーションは1個だけでも、実際には複数のスレッドに分けられて処理されることで、複数の論理CPUが動いてしまう点である。画面1はCineBench9.5のシングルCPUレンダリングを実行している状態だが、CPUの使用率は50%でCPUのリソースは1つ分しか利用していないことになるものの、2つのコアを利用してしまっていることが分かる。
もう1つは、とくにWindows Vistaで顕著であるが、1つのコアがフルに動いている状態で、もう1つのコアがアイドルになる時間が短いという点だ。画面2はStress Prime 2004を利用して、片方のコアだけに負荷が集中するケースを作ったケースであるが、この状態でもIDAが動作していない。もう片方のコアの負荷はゼロに近いものの、わずかにグラフが浮き沈みしており、アイドル状態にはなっていないことが分かる。
この状態はTurbo Memoryを無効化するなどしてStress Prime 2004以外のプロセスが走ることを極力抑えた結果ではあるのだが、それでもバックグラウンドで動作するタスクが存在することで、2つのコアを利用する羽目に陥ってしまい、結局のところIDAが機能しない結果になっていると想像できる。さらに、このことは、Santa Rosaでサポートされた、省電力機能にも影響を及ぼしていると考えているが、続いては、この点について触れていきたい。
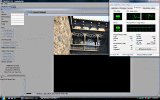 |
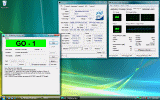 |
| 【画面1】CineBench9.5のシングルCPUレンダリングは1つのCPUコアを使うように見えるが、実際には複数のスレッドに分けられて動作しており、2つのコアが動作している | 【画面2】動作させるコアを選択できるStress Prime 2004を利用して片方のコアに集中して負荷をかけてみたが、もう片方のコアがアイドル状態になっていない。これでは、IDAは動作しないはずだ |
●Santa Rosaが持つ、2つの新しい省電力機能
Santa Rosaプラットフォームは、FSBが上げられてはいるものの、MeromコアのCPUを利用する点では同じである。MeromコアのCore 2 Duoでは最低倍率が6倍となっているが、FSBが上げられているということは、Enhanced Speed Stepを利用した場合の最低動作クロックが上がってしまうことになる。667MHz FSBでは1GHzが最低クロックとなるが、800MHz FSBでは1.2GHzになってしまうのである。このことは、消費電力とバッテリ駆動時間にに影響を及ぼす。
そこで、Santa Rosaでは、バスクロックを下げる機能が追加されている(図3)。従来のLow Frequencyモードに加え、Super Low Frequencyモードと呼ばれるモードを追加。この状態では、バスクロックが200MHzから100MHzへ落ちるため、CPU最低動作クロックは600MHzにまで落とすことができる。
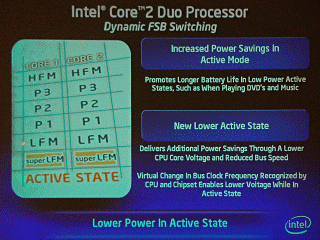 |
| 【図3】Dynamic FSB Switchingの説明スライド。バスクロックを半分の速度に落として、CPUにより低い動作クロックのモードを設けるもの |
さらに、Santa Rosaではアイドル時のステートも追加。従来のDeeper Sleep(C4)よりもさらに低い電力となるステートで、Enhanced Deeper Sleep(DC4)と名付けられている(図4)。従来のC4ステートではキャッシュの内容を保持し続けるが、C4ステートが長時間続く場合は、徐々にキャッシュの内容を消していくことで、DC4ステートでは完全にキャッシュ内容がクリアされる。これにより消費電力を抑制することができるというものだ。
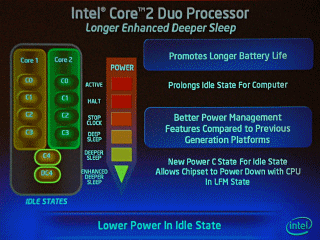 |
| 【図4】Enhanced Deeper Sleepの説明スライド。キャッシュ内容を徐々にフラッシュしていくことで、アイドル時の消費電力をさらに落とすステートとなる |
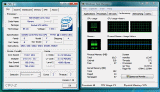 |
| 【画面3】アプリケーションが何も動いていなくても、Windows VistaでCPU使用率が0%を維持する時間は短い。消費電力を見てもEnhanced Deeper Sleepに入ったと思われる状況は発生しなかった |
ただ、試してみると、やはり、どちらも動作していると考えられる状況は生まれなかった。例えば、Super Low Frequencyモードの動作を確かめようと、ほとんどのアプリケーションを終了して放っておいたものが画面3になるが、これもCPU負荷は0~1%で、やはりバックグラウンドで動作するアプリケーションの影響がある。
画面3ではCPU-Zが動いてしまっており、完全にアイドルとはいえないわけだが、バッテリを取り外した状態でワットチェッカーを利用してPCの消費電力をチェックしてみたところ。アプリケーション終了直後に18Wまで落ち、以降1時間放置してみたが、一時的に上がることはあっても下がることはなかった(ちなみに、CPU-Zを起動している画面3の状態でも18Wまで落ちる)。
見えないところで動作している可能性は否定できないものの、これらの仕組みから考えて、すべて実際に動作していないと筆者は考えている。
特にWindows Vistaはバックグラウンドで動作するプロセスが目立つし、ユーザーによる意図的なプロセスが存在しないことを見計らって動作するシステム関連のプロセスも多い。このような仕組みのOSで使う以上、プロセッサドライバなどを用いてうまくコントロールできるようにならないと、こうした機能は絵に描いた餅になりかねない状況なのだ。
●ReadyBoostとReadyDriveを1モジュールで実現するTurbo Memory
続いては、Robson Technologyの開発コードネームで知られた機能について触れていきたい。この機能は、Santa Rosaの製品化にあたり「Turbo Memory」という名称がつけられた。Windows Vistaに実装されているReadyBoostとReadyDriveを利用したキャッシュ領域として利用されるものである。つまり、Windows Vistaでのみ利用可能な機能になる。
Turbo Memoryのハードウェアは、NAND型フラッシュとコントローラチップで構成され、モジュール形式もしくは直付けでマザーボード上に実装が可能。メモリ容量は512MBと1GBのものが用意される。モジュールはPCI Express Mini Cardの形態で提供されることになるが、オンボード実装した場合もコントローラは同一なのでPCI Express接続となる点に変わりはない。そのため、USBメモリのように気軽にホットリムーブするようなスタイルでは利用されないが、その一方でReadyBoostだけでなくReadyDriveとしても使えるわけだ。
評価機では、そうした利用スタイルを見越してか、キーボード上部という手が届きにくい場所に、PCI Express Mini Cardのモジュールで搭載されている(写真6~8)。なお、このモジュールはディスクドライブとしては認識されないため、ReadyBoost/ReadyDriveとして利用しない場合でもストレージとして利用することはできない。
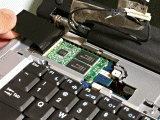 |
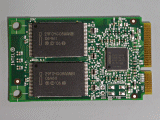 |
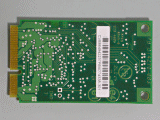 |
| 【写真6】キーボード上部に搭載されているTurbo Memoryのモジュール。脱着しづらい場所にあるのは、一度取り付けたら触ることが少ないデバイスだからだろう | 【写真7】Turbo Memoryの1GBモジュール。写真左側にあるチップがコントローラで、2枚のNANDフラッシュによって構成されている | 【写真8】Turbo Memoryモジュールの裏面には何も実装されていない |
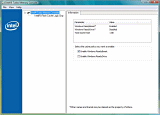 |
| 【画面4】Turbo Memoryの設定を行なう、Intel Turbo Memory Console。ReadyBoostとReadyDriveの動作を個別に切り替えることができる |
設定はWindows上で動作する専用ツール「Turbo Memory Console」から行なう(画面4)。ここから、ReadyBoostとReadyDriveのどちらかを有効、または両方を有効にできる。ただし、両方を有効にした場合、その容量の配分を決めることはできず、実際にどの程度割り当てられているかを確認する手段もない。
また、このTurbo Memory Consoleの使い勝手も、まだ作りこみが甘いように思われる。例えば、ReadyBoostのチェックボックスを外しているにも関わらずUSBメモリによるReadyBoostが有効にできなくなってしまうことや、両方とも無効化している状態からReadyBoostだけにチェックして再起動してもなぜかチェックが外れてしまっているなど、設定が正しく反映されないケースが散見された。
そもそも、Intelでは、Turbo Memoryの設定はHDDなどの設定を行なうIntel Matrix Storage Managerで行なうと説明していたので、このツール自体がサンプルアプリケーションである可能性もある。いずれにしても、もう少し安定した動作が望まれる。
さて、このTurbo Memoryを利用した際のパフォーマンスであるが、ここでは、hiyohiyo氏による「CrystalDiskMark 1.0.2」を利用してテストしてみたい。テストにあたっては下記のテストパターンを設定。CrystalDiskMark 1.0.2上では5回測定を行なう仕組みになっているが、それをさらに3回実行した平均値を出している。
・すべての機能を無効
・Turbo MemoryによるReadyBoostとReadyDriveを有効
・Turbo MemoryによるReadyBoostのみ有効
・Turbo MemoryによるReadyDriveのみ有効
・USBメモリによるReadyBoostのみ有効
・Turbo MemoryによるReadyDriveと、USBメモリによるReadyBoostを有効
なお、テストに使用したUSBメモリは、あるイベントでSamsungがプレスキットを入れて配布したもの(同社のWebサイトでは製品を確認できない)。頂いた物ながら、これが筆者宅にあるもっとも高速なUSBメモリであり、パフォーマンスは表3の通り。書き込みが若干遅い傾向にはあるが、読み込みは高速な部類に入るだろう。容量は1GBで、全領域をReadyBoostに割り当ててテストしている。
| Sequential Read | 29.4 MB/sec |
|---|---|
| Sequential Write | 14.5 MB/sec |
| Ramdom Read 512K | 29.3 MB/sec |
| Ramdom Write 512K | 4.9 MB/sec |
| Ramdom Read 4K | 6.6 MB/sec |
| Ramdom Write 4K | 0.2 MB/sec |
これらのパターンで、HDDのパフォーマンス測定を行なった結果はグラフに示した通りで、いくつかの傾向を見て取ることができる。
1つは、4KBのランダムアクセスにおいてReadyBoostの効果が大きいという点である。こうした細かいデータでのランダムアクセスに非常に有効であることが分かる。
ただし、ReadyDriveはこのテストのアクセスには、あまり効果が出ていない。おそらくキャッシュの使われ方に違いがあり、ReadyDriveは主に起動時やハイバネーションに利用され、通常アプリケーションでは積極的に活用されない可能性が高そうである。
また、Turbo Memoryの利用方法をReadyBoostに限定した場合でも、明確なパフォーマンス差は得られていない。Turbo MemoryでReadyBoostのみを有効にした場合は、両方を有効にした場合に比べて多くの容量がReadyBoostに割り当てられることになるが、そのことが明確なメリットとしては発揮されていない。
Turbo MemoryとUSBメモリを比較してみると、Random Read 4KBの結果を見る限りでは、前者の方がReadyBoostを利用した際にパフォーマンスが高いように見られる。ただ、同じRandom Readでも512KBではUSBメモリを利用した方がパフォーマンスが良いなど、やはり明確な結論は見出せない状況である。
逆にTurbo Memoryを利用した場合は、Sequential Readが遅い傾向にあるのも気になる点だ。シーケンシャル処理であれば、フラッシュメモリよりもHDDのほうが高速に読み出しできることは知られている。USBメモリのReadyBoostでは、こうした傾向が見て取れないことから、Turbo MemoryのドライバがHDDアクセスに何らかの遅延を生じさせている可能性もある。
ReadyBoost/ReadyDriveはキャッシュメモリという性格上、安定した結果が出にくいため、今回のテストだけではTurbo Memoryのパフォーマンスについては明確な答えが出せないのだが、いくつかの傾向は見ることができただろう。
なお、Turbo Memoryにはパフォーマンスだけでなく、HDDのメカ駆動を減らすことで消費電力を下げ、バッテリ駆動時間を伸ばすメリットもある。現状では、MobileMarkのように決められた複雑な動作をループし続けるWindows Vista対応ツールが存在しないため、同一条件下でもバッテリ駆動時間を測定するのが非常に困難である。そのため、今回はバッテリ駆動時間の違いは計測できていないのだが、この点もTurbo Memoryの効果として期待できることを付け加えておく。
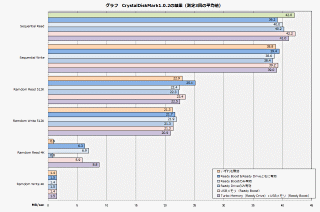 |
| 【グラフ】CrystalDiskMark1.0.2の結果(測定3回の平均値) |
●802.11nドラフト対応の新無線LANモジュール
最後に見ておきたいのは、ネットワーク機能である。Santa Rosaプラットフォームでは、Centrino ProでサポートされるIntel AMTへ対応させるために、LAN関連のモジュールが一新されている。有線LANはIntel 82556シリーズ、無線LANはIntel Wireless WiFi Link 4965シリーズとなる。
特に注目したいのが後者の無線LANモジュールである。Intel Wireless WiFi Link 4965には、従来通りIEEE 802.11a/b/gをサポートするIntel Wireless WiFi Link 4965AGのほか、IEEE 802.11nのドラフト2.0に対応するIntel Wireless WiFi Link 4965AGNがラインナップされている。
従来通りIntel PRO/Wireless 3945ABGを利用することもできるが、こちらを利用した場合はIntel AMTに対応できない。つまり、Centrino Proを名乗る場合は4965シリーズのいずれかが必須となる。また、Centrino Proを名乗る場合には、コンシューマ向けのCentrinoとは異なり、有線LANのIntel 82556MMが必須となっており、従来のモバイル向けプラットフォームにはなかった条件が追加されていることになる。
今回の評価機には、Intel Wireless WiFi Link 4965AGNのPCI Express Mini Cardモジュールが、CPUやチップセットの脇に搭載されていた(写真9)。Windows上のドライバでは、802.11nに関する設定項目がいくつかあり、802.11nのチャネルを20MHzに制限する項目や、802.11nのみを無効にすることなども行なえるようになっている(画面5)。
ちなみに、前述の通り、現時点では802.11nはドラフト仕様であり、ユーザー側としても接続性に不安を覚える向きがあると思う。そうした状況に対処するため、Intelでは「Connect with Centrino」というプログラムを始める(図5)。これは、アクセスポイントを提供するハードウェアベンダーと協力したもので、Intel Wireless WiFi Link 4965AGNとの接続が確認できたアクセスポイントにロゴシールを貼付するというものになっている。
●変更を積み重ねて一新されたCentrino Duoプラットフォーム
Santa Rosaでは前世代と同じコアのCPUを利用しているが、新しい動作ステートが用意されたほか、チップセットや周辺デバイスも多くの改善や機能追加がなされている。少なくとも、Penrynコアのモバイル向けCPUが登場するまでは、このSanta RosaプラットフォームがノートPCで多く採用され、メインストリームの存在になることは間違いないだろう。800MHz FSBのCPUはデュアルコアを活かしたパフォーマンス路線の製品で特に採用が進むと思われ、パフォーマンス面でNapaを上回る要素が多いのは魅力的な存在といえる。
だが、現時点では、正しく動作していることを確認できない機能が多かったり、802.11nにしても40MHzモードでの動作が国内で認められていないなどの問題もあり、持てるポテンシャルを発揮しきれていない印象は残る。802.11nの問題はIntelだけではどうすることもできないわけだが、同社だけで可能な点、例えばTurbo Memory設定ツールの安定性向上などは早急に取り組んで欲しい。
□関連記事
【4月5日】インテル、「Centrino Pro」ブランドを発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0405/intel.htm
【4月23日】【元麻布】法改正が待たれる802.11nの国内利用
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0423/hot480.htm
【1月24日】Intel、ノートPC内蔵用IEEE 802.11nモジュール
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0124/intel.htm
【2006年1月10日】インテル、Centrino Duo/Viivの国内セレモニーを開催
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0110/intel.htm
(2007年5月9日)
[Text by 多和田新也]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2007 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.