 |


■笠原一輝のユビキタス情報局■Santa Rosaの発展版となる
|
Intelが開発者向けに開催しているIntel Developer Forumは、本日より中華人民共和国 北京市にあるBeijing International Convention Center(BICC)において開催されている。その前日となる16日には、報道関係者を集めた記者説明会が開催され、Intelが開発中のさまざまな技術などに関しての説明が行なわれた。
本レポートでは、その中でも、Intel 上級副社長兼モバイルプラットフォーム事業本部 本部長のムーリー・イーデン氏が公式に明らかにした次世代モバイルプラットフォームとなる“Montevina”(モンテビーナ、開発コードネーム)の概要と、OEMメーカー筋などから寄せられたMontevinaの詳細な情報などについてお伝えしていきたい。
●45nmプロセスのPenryn、Cantiga、EchoPeakから構成されるMontevina
 |
| Intel 上級副社長兼モバイルプラットフォーム事業本部 本部長のムーリー・イーデン氏。手に持つのは45nmプロセスルールで製造されたPenrynの300mmウェハ |
イーデン氏はIntelが今四半期(第2四半期)中に製品出荷を目指して開発を続けている、次世代モバイルプラットフォームの“Santa Rosa”(サンタロサ、開発コードネーム)に関する説明を行なった。Santa Rosaの詳細に関しては、すでに以前の記事で触れたとおりなので、ここでは繰り返さないが、MeromコアのCore 2 Duo Tシリーズ、チップセットの“Crestline”ことIntel 965シリーズ、11nドラフトに対応した無線LANのIntel Pro/Wireless 4965AGNなどから構成されており、OEMベンダはオプションとして“Robson”の開発コードネームで知られるIntel Turbo Memoryなどを採用することができる。
「今回我々がリリースするSanta Rosaプラットフォームは非常にパワフルなプラットフォームだ。すでに多くのOEMに評価をいただいており、リリース時には世界中で200を超える製品が登場することになるだろう。その立ち上がりは非常に順調であり、今年(2007年)の末までにはIntelのモバイルプラットフォームの80%はSanta Rosaベースになるだろう」(イーデン氏)と述べ、IntelとしてはSanta Rosaの立ち上がりが順調であることを強調した。
そして、そのSanta Rosaの後継としてリリースされるのが“Montevina”の開発コードネームで知られる次々世代プラットフォームだ。イーデン氏は「Montevinaプラットフォームは45nmプロセスのPenryn(ペンリン、開発コードネーム)、チップセットのCantiga(キャンティーガ、開発コードネーム)、WiMAXと無線LANのコンボ機能を実現するEcho Peak(エコーピーク、開発コードネーム)から構成されている。より詳しい詳細は次回のIDFで明らかになるだろう」と述べ、文字通りMontevinaの詳細をわずかながら明らかにした。
 |
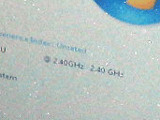 |
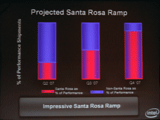 |
| Penrynが動作するSanta RosaプラットフォームのノートPC。クロックは2.4GHzだった | Santa Rosaの立ち上がりは非常に速いと、イーデン氏 | |
●Meromのマイクロアーキテクチャを元に若干の改良を施したPenryn
イーデン氏が明らかにしたMontevinaの詳細は、基本的には関連記事や後藤氏の記事で触れたとおりなのだが、その後いくつかのアップデートがされているので、ここでお伝えしていきたい。
CPUは45nmプロセスルールで製造されるPenrynとなる。Penrynは現在Core 2 Duo Tシリーズに利用されているMeromコアの後継で、Meromのマイクロアーキテクチャ(プロセッサのハードウェアの仕様のこと)をベースに「細かな改良」(イーデン氏)が行なわれている製品となっている。
イーデン氏が説明したPenrynの改良点は、大きく言うと次のようなポイントが挙げられる。
・実行エンジン効率の改良
・L2キャッシュの増量(4MBから6MB)
・新命令セットSSE4に対応
・新しいパワーステートの追加
このほか、OEMメーカー筋の情報によればMeromでは対応していなかったIntel TXT(Trusted eXecution Technology)に対応していること、システムバスは1,066MHzに引き上げられること、さらには“Enhanced Dynamic Acceleration Technology”と呼ばれる、以前の記事でIDAとして紹介したシングルスレッド動作時にクロックを1グレード引き上げる機能などの拡張が行なわれる。また、Meromでもハーフサイズキャッシュ版、つまり2MBキャッシュのSKUが用意されていたが、Penrynでも同じように3MBキャッシュ版も用意される。
また、新しいCPUのパワーステートとしてC6モードが追加される。イーデン氏によれば、C6ステートでは、従来のMeromで用意されていたEnhanced Deeper Sleep(C4e)をさらに進め、L1キャッシュへの電源供給も落とすことでより低い電圧でのアイドル状態を可能にするという。
なお、イーデン氏によればSanta Rosaへの移行の前に、現行のNapaプラットフォームに対して新しいプロセッサのMeromを追加してリフレッシュを行なったように、Santa Rosaプラットフォーム向けのPenrynが、Montevinaのリリースに先立って投入されるという。
 |
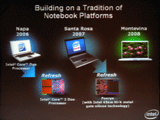 |
| 2008年のプラットフォームになるMontevinaを説明するスライド | Santa Rosa用のPenrynも用意される |
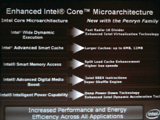 |
 |
| Penrynの機能を説明するスライド | 新しいC6というパワーステートが追加され、アイドル時の消費電力の低下を実現 |
●同じデータレートのDDR2に比べて35%も消費電力が低いDDR3をサポート
チップセットのCantigaも、Santa Rosaに採用されるCrestline(Intel 965シリーズ)に比べていくつかの機能向上が図られる。ただし、イーデン氏はCantigaのコードネームこそ明らかにしたが、そのほかの細かな機能などは明らかにしなかった。そこで、OEMベンダ筋の情報から、Cantigaの姿を解き明かしてみよう。
情報筋によれば、Cantigaの強化点は大きくいうと、以下の点になる。
・新メモリのDDR3 SDRAMに対応
・Gen5と呼ばれる新世代GPUコアを内蔵
・DirectX 10/シェーダモデル4.0に対応
・10個のシェーダユニットを内蔵
・VC-1/MPEG-4 AVCのハードウェアデコードに対応
・Intel Clear Video Technologyの拡張
・新しい省電力機能の搭載
Cantigaでは、デスクトップPCではコードネーム“Bearlake”ことIntel 3シリーズチップセットでDDR3 SDRAM(以下DDR3)に対応する。DDR3は、現在PCでメインストリームのメモリデバイスとして利用されているDDR2 SDRAM(以下DDR2)の後継となる高速メモリで、すでにメモリデバイスメーカーはサンプル出荷を開始している。
DDR3の最大の特徴は、同じデータレートであればDDR2よりも消費電力が低下することだ。
| DDR2 | DDR3 | |
|---|---|---|
| データレート | 800/667/533/400MT/sec | (1,666)/1,333/1,066/800MT/sec |
| プリフェッチ | 4bit | 8bit |
| 供給電圧(VDD) | 1.8V | 1.5V |
| ターミネータ | マザーボード上 | モジュール上 |
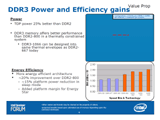 |
| DDR3の消費電力を説明するIDFのスライド。同クロックのDDR2に比べて25%の消費電力削減が期待できるという |
もっとも重要なことは、供給電圧の違いだ。DDR2では1.8Vの電圧がかけられていたのに対して、DDR3では1.5Vに下げられている。このため、電圧の二乗に比例して下がることになる消費電力は同クロック(厳密に言うと同じデータレート)で比較した場合、DDR3はDDR2に比べて圧倒的に低い。すでに公開されているIDFの資料の中で、IntelはDDR3の消費電力はDDR2に比べて25%も低いと明らかにしているほか、DDR3-1066はDDR2-667と同じ消費電力で利用できるという。シングルチャネルでの帯域がDDR2-667が5.2GB/secであるのに対して、DDR3-1066は8.5GB/secにも達するので、消費電力はあがらずに性能を向上させることが可能になるため、特にモバイルではそのメリットは非常に大きいと言える。
CantigaではDDR3で用意される3つのスピードグレード(1,333/1,066/800MHz)のうち、1,066MHzと800MHzの2つがサポートされる。すでにJEDECにおけるDDR3 SO-DIMM仕様も最終化されており、5月頃にはメモリデバイスベンダなどからOEMベンダに対してサンプル出荷が開始される見通しであるとIDFで明らかにされている。
ただし、イーデン氏はDDR3のモバイルプラットフォームでのサポートに関しては「モバイルにもDDR3がくることは疑いがない。しかし、1つ指摘しておきたいことは、DDR2とDDR3は同じマザーボードを利用できないため、別の設計が必要になる。このため、まずはプレミアムがつけられるハイエンドから入ってきて、その後DDR3がメインストリームになってからすべてのセグメントに来るだろう」と述べるなど、リリース当初はDDR2とは別のマザーボードを用意するためのコストやDDR3モジュール自体の価格プレミアムなどにより、まずはハイエンドから入っていき、ローエンドはDDR2にとどまるだろうという見通しを明らかにした。
●DirectX 10を本格的にサポートするCantigaの内蔵GPU
Cantigaのもう1つの特徴は、DirectX 10に対応したGPUを内蔵していることだ。おそらく、CantigaはDirectX 10をサポートする初めてのIntelのモバイル向けGPUになる。そう書くと、“あれ、じゃあSanta RosaのIntel GM965は?”という声が聞こえてきそうだが、「GM965の内蔵GPUはDirectX 10をサポートしていない。ハードウェアとしては確かにDirectX 10に対応可能な構造になっているのは事実だ。しかし、ソフトウェア側の準備はまだ整っていない。今後、ソフトウェアのアップグレードなどにより対応できる可能性はある」(イーデン氏)とのことで、GM965の内蔵GPUであるGMA X3100はスタート時にはDirectX 10には対応していないことが明らかにされた。
GM965は、その製品名からもわかるようにIntel G965のモバイル版とも言えるチップセットで、内蔵GPUの構造はG965のGMA X3000とほぼ同じ構造になっている。8つのプログラマブルな演算ユニットを備え、これを利用してドライバレベルでさまざまな実装が行なえるようになっている。GM965の内蔵GPUであるGMA X3100もほぼ同じ構造であると推測できるため、ドライバの開発が間に合っていないなどの理由でDirectX 10への対応が先送りになっていると考えるのが正しいだろう。
これに対して、Cantigaでは最初からDirectX 10をサポートする。Cantigaの内蔵GPUは、演算ユニットが8から10に増やされるなど強化されており、ドライバソフトウェアレベルでDirectX 10 APIやシェーダモデル 4.0などへの対応を実現するという。もっともこれは、この時点では必ずDirectX 10に対応していないといけないという背景もある。Microsoftは、同社がOEMベンダのPCにロゴシールを貼り付けるWindows Logo Programというマーケティングプログラムのうち、上位の「Premiumロゴ」と呼ばれるロゴシールを貼るための要件に、“2008年の6月1日以降はDirectX 10に対応していなければならない”という事項があるのだ。
●CPU負荷率を下げるVC-1/MPEG4 AVCのハードウェアデコーダを内蔵
動画再生周りでも機能の拡張が行なわれる。日本のPCベンダにとって大きいのは、次世代DVD(HD DVD/BD)のCODECとして採用されているVC-1/MPEG-4 AVCのハードウェアデコーダ機能の実装だろう。これも、ソフトウェアドライバにより実装される機能で、実際には内蔵されている演算器を利用して行なわれる。
現行世代のGPUでは、VC-1/MPEG-4 AVCのアクセラレーション機能として、動き補正(Motion Compensation)とILD(In Loop Deblocking)という2つの処理をハードウェアで行なっているのだが、Inverse Transform(逆変換)、VLD(Variable Length Decode)といった処理はCPUで行なっている。この2つがCPUに高い負荷をかけることになり、結果的にコマ落ちが発生する(PCでHD DVDのベンチマークとして有名なタイトルである“夜桜”を再生するとややコマ落ちして見える場合があるのはこのためだ)。
Cantigaではこの2つ(Inverse TransformとVLD)に関しても、内蔵GPU側で処理可能になるので、HD DVD/BD再生時のCPU負荷が圧倒的に下がることになる。これにより、CPUがデスクトップPCに比べて非力なノートPCでも、安定してHD DVDやBDの再生が可能になる。
また、CantigaではHDCPの暗号化鍵がチップの中に封入される。このため、SiliconImageなどが提供する暗号化鍵を封じ込めた外部トランスミッタチップを利用しなくてもHDCPやHDMIが低コストで実装可能になる。なお、Cantigaではオーディオコントローラは、依然としてサウスブリッジとなるICH9側にあるが、ノースブリッジにはHDオーディオの出力を入力する口が用意されており、ノースブリッジの内部でHDMIのビデオ+オーディオにマージして出力することが可能になっている。
●TPMチップがノースブリッジに内蔵されるCantiga
Cantigaでは、もう1つの注目点としてセキュリティ周りの強化が挙げられる。CPUのPenrynもそうだが、Cantigaも“LaGrande”の開発コードネームで知られたIntel TXT(Trusted Execution Technology)に対応している。また、TPM 1.2に対応したセキュリティチップがノースブリッジに統合されている。TPM 1.2はWindows Vista UltimateやEnterpriseに搭載されているファイル暗号化機能“BitLocker”で必要となるセキュリティチップで、最近の企業向けノートPCでは標準搭載となりつつある。これらを、ノースブリッジに統合することで、ノートPCをよりセキュアにすることが可能になる。
CantigaのサウスブリッジはICH9Mとなる。ICH9Mは、デスクトップPC向けのIntel 3シリーズに採用されているICH9のモバイル版で、USB 2.0が12ポートに増やされるほか、Serial ATA-300のポート数がICH8Mの3ポートから4ポートに増加する。ただし、その代わりパラレルATAのポートは完全に外されるので、OEMベンダは光学ドライブをシリアルATAのものに変更する必要がある。
| Santa Rosa | Montevina | ||
|---|---|---|---|
| CPU | プロセッサコア | Merom | Penryn |
| 製造プロセスルール | 65nm | 45nm | |
| コア数 | 2 | 2 | |
| L2キャッシュ | 4MB | 6MB | |
| FSB | 800MHz | 1,066/800MHz | |
| 省電力機能 | EIST | EIST、C6拡張 | |
| Enhanced Dynamic Acceleration Technology | ○ | ○(拡張版) | |
| 熱設計消費電力 | 35W | 35W | |
| アベレージパワー | 1W以下 | 1W以下 | |
| ノースブリッジ | 開発コード名 | Crestline | Cantiga |
| SKU | GM/PM/GL | GM/PM/GS | |
| メモリ | DDR2 | DDR2/DDR3 | |
| メモリクロック | 667/533MHz | 1,066/800/667/533MHz | |
| 内蔵コア | Intel GMA X3100 | Gen5 | |
| 対応API | DX9 | DX10 | |
| 内蔵コア数 | 8? | 10 | |
| PCIe | x16 | x16(Gen2) | |
| Intel Clear Video Technology | ○ | ○(拡張版) | |
| HD DVD/Blu-rayサポート | - | ○ | |
| HDCPキー | - | ○ | |
| HDMIオーディオマージ機能 | - | ○ | |
| PVP-OPM | - | ○ | |
| HDMI | オプション | ○ | |
| DisplayPort | - | ○ | |
| DVI/RGB | ○ | ○ | |
| VT-d | - | ○ | |
| Intel TXT | - | ○ | |
| TPM統合 | - | ○ | |
| 省電力機能 | 電圧 | 電圧/周波数 | |
| クロック周波数 | ? | 475MHz(1.05V) | |
| サウスブリッジ | 世代 | ICH8M | ICH9M |
| PCIe | 6ポート | 6ポート | |
| GbE MAC | ○ | ○ | |
| AMT | 2.5 | 4 | |
| SATA | 3ポート(SATA-300) | 4ポート(SATA-300) | |
| PATA | 1 | - | |
| USB 2.0 | 10 | 12 | |
| 追加コンポーネント | Wi-Fi | Intel Pro/Wireless 4965AGN | Shirley Peak |
| Wi-Fi/WiMAX | - | Echo Peak | |
| ギガビットイーサネット | Nineveh | Boazman | |
| NANDフラッシュ | Intel Turbo Memory | Robson 2.0 |
●Montevinaプラットフォームは2008年Q2に登場、LV/ULVはやや遅れてQ3に
以上のように、Montevinaプラットフォームのうち、CPUとチップセットを中心に紹介してきたが、基本的にはCPUもチップセットも前世代の改良版という色合いが強いプラットフォームであると言える。従って、Santa Rosaの正常進化版がMontevinaであると考えることができるだろう。
ノートPCにとって次の大きな変革となる可能性があるのは、開発コードネーム“Nehalem”(ネハレム)で知られる、メモリコントローラをCPU側に統合したプロセッサのモバイル版が投入されたときになるのではないだろうか。情報筋によれば、IntelはMontevinaの後継プラットフォームを2009年に予定しているという。現時点ではその後継プラットフォームがどんなものになるかはわからないが、Intelに近い関係者によればNehalemのモバイル版は存在しており、おそらくそのMontevinaの後継プラットフォームで導入される可能性が高いという。
Nehalemでは、プロセッサバスが現行のGTLをベースにしたパラレルバスから、CSIと呼ばれるシリアルバスに移行するという。CSI自体は、物理的にはPCI Express Gen2を応用したものになると言われているが、高いと言われるPCI Express Gen2の消費電力がどうなるのか、これが1つのチャレンジになるだろう。
ただ、1つ言えることは、現在のパラレルバスのFSBもクロックを引き上げてきたことで、かなり消費電力を食う存在になっているという事実だ。実際、前述の関係者はまずシリコンを作り込み、CSIに移行することで消費電力を下げることは可能だと指摘している。
なお、OEMメーカー筋の情報によれば、当初2008年第1四半期に予定されていたMontevinaプラットフォームのリリースは、2008年の第2四半期に変更されているという。それに先立つ第1四半期には、Santa Rosaプラットフォーム用のPenrynがリリースされ、Santa Rosaのリフレッシュが行なわれることになる。なお、低電圧版、超低電圧版はやや遅れ、2008年第3四半期のリリースが予定されているという。これらに関しては別レポートでお伝えしていきたい。
□関連記事
【1月31日】【笠原】WiMAXはノートPCの標準機能になるか
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0131/ubiq170.htm
【2006年11月30日】【笠原】見えてきたSanta Rosaの全貌
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1130/ubiq169.htm
【2006年10月11日】【海外】2008年のモバイルプラットフォーム「Montevina」への道
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1011/kaigai310.htm
(2007年4月17日)
[Reported by 笠原一輝]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.