 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■マイクロアーキテクチャの変化を反映する“Core”ブランディング |
●12年間続いたPentiumブランドは終焉へ
「Intel Core」Processorへのブランドチェンジによって、Intelは、いよいよ「Pentium」ブランドに終止符を打つと見られる。12年間に渡って使い続けられてきたPentiumブランドは、2006~7年には終焉に向かう。
もともと、Intelは、「Intel 486」プロセッサまでは、CPUのブランディングをそれほど重視していなかった。だが、同じ3並びの数字を持つAMDやCyrixの互換CPUの攻勢を受けた結果、互換CPUと差別化するためのブランドの重要性を意識し始めた。そこで、5世代目であるコードネーム「P5」だったCPUには、「586」ではなく、“5”を意味する「Pent-(ペンタ)」を冠したPentiumブランドを与えた。
こうした経緯から、6世代目に当たる「P6」には、「Hexa-(ヘクサ)」(6の意味)をプリフィックスに持つ新ブランド名がつくとウワサされた。しかし、Intelは、P6に「Pentium Pro」を冠し、Pentiumブランドを継続。その後、「Pentium II(Klamath:クラマス)」、「Pentium III(Katmai:カトマイ)」、「Pentium 4(Willamette:ウイラメット)」、「Pentium M(Banias:バニアス)」、「Pentium D(Smithfield:スミスフィールド)」と、Pentiumブランドを継承してきた。つまり、マイクロアーキテクチャが拡張されたり革新されても、Pentiumブランドを維持されており、Pentiumの本来の“5世代目”という意味づけは、すでに消えている。
では、ここへ来てのCPUブランドの変更は、何を意味するのだろうか。
Intelの今回のCPUブランド変更が非常に面白いのは、これがマーケティングと製品戦略の変化だけでなく、CPUアーキテクチャの3つの変革を反映していることだ。
(1)CPUのマルチコア化
(2)CPUのユニファイドアーキテクチャ化
(3)CPUマイクロアーキテクチャの方向性の変化
逆を言えば、こうしたIntelの内部的技術的な変化を反映したのが、今回のブランド刷新と言える。ブランドも変更することで、Intelは、ある意味“腹をくくった”と言っていいかもしれない。
●CPUのマルチコア化
Intelがマルチコア(Multi-core)CPU化を強調するために、わざわざCoreというブランド名を選んだことはすでにレポートした通り。Coreブランドからは、Intel CPUはマルチコアへ向けて突き進む。
マルチコア化は、イコール、「命令レベルの並列性(Instruction-Level Parallelism:ILP)」重視から「スレッドレベル並列性(TLP:Thread-Level Parallelism)」フォーカスへの大転換で、その意味ではCPUアーキテクチャのパラダイムシフトと言える。Intelは、もともとこの流れに、乗り遅れかかっていた(1年半前はシングルコアのTejasをリリースしようとしていた)。Coreとブランドすることで、今のIntelはその時流に乗っていることを強調しようとしている。
●CPUのユニファイドアーキテクチャ化
新ブランド「Intel Core Processor」には、“M(Mobile)”や“D(Desktop)”といったフォームファクタを規定するイニシャルはつかないと言われている。
つまり、これまでのように、モバイルとデスクトップという区分けは、Coreブランドでは強調されない。唯一の区別はProcessor Numberにつけるパワークラス(電力階層)のプリフィックスで、TDP(Thermal Design Power:熱設計消費電力)帯ごとに区分される。
| ? | 100Wクラス |
| E | 50W以上 |
| T | 24~49W |
| L | 15~24W |
| U | 14W以下 |
このブランディングのメッセージは明瞭で、IntelはもうCPUブランド名でフォームファクタは規定しないということだ。モバイルとデスクトップはシームレスにつなげる。そのため、IntelはMerom/Conroe系を「ユニファイドアーキテクチャ(Unified Architecture)」と呼んでいる。
実際、Intelの事業部でも、従来のデスクトップとモバイルの垣根を越える「Digital Home Group」が設立されている。Yonah世代以降は、Intelが“公式”に、モバイル系CPUベースのデスクトップも推進する。
また、今後は、Merom/Conroeだけでなく、PC向けCPUアーキテクチャは今後も一本化すると見られる。Intelといえども、2系列のCPUを並列に開発するのは負担が大き過ぎるからだ。昨年秋のインタビューで、Intelの研究部門を統括するJustin R. Rattner(ジャスティン・R・ラトナー)氏(Intel Senior Fellow, Director, Corporate Technology Group)は、次のように語っていた。
「今後は、コアによる差別化は減って、“アンコア(uncore)”による差別化が増えていくだろう。アンコアと我々が呼んでいるのは、キャッシュ、バスインターフェイスなどCPUコア以外の部分で、TLBのライン数なども含まれる。
我々は、できるだけコアの種類を減らし、同じコアをベースに、各市場の電力とパフォーマンスの要求に最適化した製品を設計していくつもりだ。差別化のフォーカスは、コアではなく、アンコアの部分になる。
例えば、ノートPCなら、最適な量のキャッシュとメモリ帯域をプロセッサに実装する。メモリコントローラの統合も求められるかもしれない。
また、各市場に向けてコアの数も変えるだろう。例えば、デスクトップは2コアで、プレミアデスクトップとサーバーは4コアといった差別化へと向かいつつある。いずれにせよ、モバイルとデスクトップとサーバーそれぞれに異なるマイクロアーキテクチャを開発するのは、時間も人もかかりすぎる。基本的には、1種類か2種類のコア設計を核に、異なる市場に最適化したアンコアの組み合わせと、最適化したコア数を取ることで、差別化することになるだろう」
おそらく、Core以降は、CPUコア自体は、デスクトップとモバイルで共通となり、他のアンコア部分で差別化がなされていくと推測される。実際、IntelはMP(Multi-Processor)サーバー向けのWhitefieldでは、FSBを変更しようとしていた。例えば、近い将来、デスクトップCPUとモバイルCPUで、FSBアーキテクチャが異なる製品が登場しても不思議ではない。
これまでは、デスクトップCPUはNetBurst、モバイルCPUはBaniasと、CPUアーキテクチャが二分されていた。これは、NetBurst系が予想以上に消費電力が上がってしまったための苦肉の策だった。だが、結果としてBanias系が存在したことが、Intelを救った。Banias系を発展させたMerom系を、NetBurstの後継のユニファイドアーキテクチャとして投入できるからだ。Banias/Yonah/Merom系は、Intelイスラエルが開発を担当しており、Pentium III以降のIntel IA-32 CPUの開発を担当してきたIntelオレゴンの製品ではない。
もっとも、Merom/Conroeの次の世代は、再びオレゴン開発の「Nehalem(ネハーレン)」になると言われている。Nehalemの次は再びイスラエルとなる。現在のIntelの態勢では、オレゴンとイスラエルが交互にCPUを開発するようになっているらしい。
●CPUマイクロアーキテクチャの方向性の変化
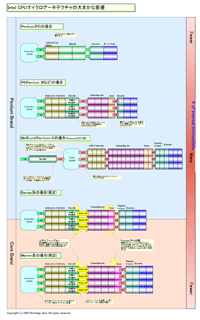 |
| Intel CPUマイクロアーキテクチャの大まかな変遷(別ウィンドウで開きます) PDF版はこちら |
Pentiumブランドは4つのCPUマイクロアーキテクチャ(P5/P6/NetBurst/Banias)にまたがって使われており、特定のマイクロアーキテクチャとの連携性はない。しかし、歴史的に見るとPentiumブランドは、ひとつの時代、ひとつのCPUアーキテクチャのトレンドを確実に示している。
Intel CPUは、386までは「CISC(Complex Instruction Set Computer)」型CPUの世界での競争を戦い、486で本格的な「RISC(Reduced Instruction Set Computer)」型プロセッサの挑戦にさらされた。そのため、Intelは、CISCであるx86命令セットを維持しながら、RISCプロセッサに対抗するためにPentiumを開発した(その一方でRISCのIntel 860も開発したが)。
さらに、Pentiumと平行して開発していたP6(Pentium Pro)では、x86命令をRISC風(固定フォーマット&ロードストア型)の内部命令「uOPs(Micro-Operations)」に変換して実行するアプローチを採用。アウトオブオーダ/スーパーパイプライン/スーパースカラと、RISCプロセッサ風のテクニックを網羅した。Pentium 4は、その流れをさらに発展させ、より深いパイプライン、より複雑なスケジューリングのアーキテクチャを採った。こうしたアーキテクチャ上の発展の結果、PentiumブランドCPUは、CISCの性能限界説を跳ね返し、パフォーマンスを伸ばし続けた。振り返ると、PentiumブランドCPUの歴史は、RISCに対抗して産まれ発展したことになる。
P5では、5ステージのパイプラインで、最大2命令を並列実行していた。次のP6では、最大3個のx86命令をuOPsに変換し、アウトオブオーダ(out-of-order)実行。パイプラインは12ステージへと伸びた。さらに次のNetBurst(Pentium 4)になると、x86命令デコードをパイプラインの前に出し、uOPsをよりアグレッシブにスケジューリングし、パイプラインも20~31ステージへとさらに細分化した。加えて、SMT(Simultaneous Multithreading)技術のHyper-Threadingも実装した。つまり、Pentiumの歴史を通じて、パイプラインはより広く長くなることで、性能を増し続けてきた。
トレードオフはCPUの非効率化で。オンザフライで制御しなければならない内部数が増大、スケジューリングに膨大なリソースが占められ、性能向上以上に消費電力が増大した。ムダは多いが、シングルスレッドの絶対性能が高いCPUを目指したのがPentium世代だが、TDPが100Wをヒットして、Intelは方向転換の必要に迫られた。そして、Intelの転換のスタートとなったのが、Pentium 4で手薄になった低消費電力ライン向けに開発されたBaniasアーキテクチャだった。
●uOPsフュージョンの進化
興味深いのは、IntelはNetBurst系CPUにはCoreブランドをつけないが、Banias系アーキテクチャを発展させたYonahにはCoreブランドを冠する点だ。新ブランドCPU群の、2世代目となる「Merom(メロン)」系アーキテクチャは、Banias/Yonahをさらに革新したものと推測される。そう考えると、Banias/Yonah系アーキテクチャは、ちょうどPentiumからCoreへの橋渡しとなる。
Banias系のアイデアの基本にあるのは、それまでのPentiumブランドCPUの流れに逆行すること。すなわち、内部命令数を減らし、パイプラインを短くし、ムダを省いた高効率化が、Baniasのコンセプトだ。鍵となる技術のひとつが、「uOPsフュージョン」だった。x86命令を複数のuOPsに分解する代わりに、複数のuOPsを縫合する「Fused uOPs」にほぼ1対1変換する。パイプライン中ではFused uOPsとして扱い、(おそらく)命令発行の前にuOPsに分解する。実行される時には、uOPsベースとなるが、それまでの間制御する命令数は大幅に減ることになる。今までは、デコーダで実行ユニットを隠蔽していたのが、uOPsフュージョンになるとuOPs分解のステージで隠蔽することになる。
uOPs数に注目すると、Pentiumブランド=uOPsの増大、Coreブランド=uOPsの削減という転換になる(演算系命令の場合。制御系のuOPsは、*Tの導入で増加する)。Meromの後に位置すると見られるNehalemやその次の「Gilo(ギロ:このコードネームのままかどうかは不明)」がどういうアーキテクチャになるかわからないが、おそらく基本ラインは変わらないだろう。「我々が電力効率を向上させるために、BaniasからMeromとそれ以降(のCPU)まで継続して行なっているのは、よりuOPsフュージョンを適用することだ」とIntelのRattner氏も語っている。
もともと、CISCはRISCに比べると、コード密度(Cord Density:プログラムサイズ当たりの命令数)が高く命令フェッチ効率がいいという利点がある。uOPsフュージョンは、こうしたCISCの特性を、CPUコア内部にも及ぼしたと考えることもできる。乱暴な言い方をすれば、CISCの利点をより活かす形へと振り子を揺り戻したのがBanias以降とも言える。
Intelが意図しているかどうかはともかく、今回のCPUブランド変更は、こうしたアーキテクチャの大きな流れの変化も反映しているところがポイントだ。
□関連記事
【11月28日】【海外】「Cell」に対抗すべく名付けられた「Core」ブランド
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1128/kaigai227.htm
【11月25日】【海外】Coreブランド化とクアッドコア投入が見えるIntelデスクトップCPU
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1125/kaigai226.htm
(2005年11月30日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.