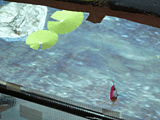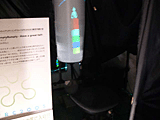|


■森山和道の「ヒトと機械の境界面」■IVRC+インタラクティブ東京2005開催
|
「第13回国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト(IVRC2005)東京予選大会」と「インタラクティブ東京」という2つのイベントが、日本科学未来館にて同時開催された。
●IVRC2005東京予選大会
IVRCは学生対抗で実施されるバーチャルリアリティ・コンテスト。今回で13回目。企画立案、製作、展示、解説まですべてを学生で構成されたチームが行なう。実行委員長は館すすむ東京大学教授。昨年、第12回の模様は本連載でレポートした。
IVRCでは書類審査を含めて合計4回の審査が実施されるが、今回は予選作品がデモ展示された。デモといってもただのデモではなく、来場者による投票が行なわれる審査過程の1つだ。最終審査は岐阜で行なわれる。
テーマは「未来にさわれる夏休み!」。以下の10作品が展示された。
・「INVISIBLE 影を追う者」Team Shadow 奈良先端科学技術大
・「bubble cosomos」scope+中村正宏 筑波大学大学院
・「球魂」いよだま 北陸先端科学技術大学院大学
・「超人ヌーク」ヒッキーズ 北陸先端科学技術大学院大学
・「遊ぶ声」素人vs玄人 富山大学
・「splash Fishing」攻盾 東京工業大学
・「Brain Touch -脳コン-」地下職人 京都大学大学院
・「お座敷ベースボール」FRT 岐阜大学など
・「DumptyRumpty -Have a great fall !-」ダルマニア 東京大学など
・「聴心器」草もち 電気通信大学
それぞれ簡単に当日の様子を写真で紹介する。詳細に興味がある人はIVRC2005のウェブサイトに作品概要PDFがアップロードされているので、そちらをご覧頂きたい。
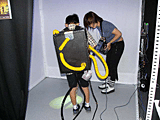 |
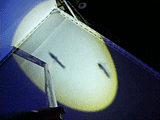 |
 |
| 「INVISIBLE 影を追う者」、Team Shadow 奈良先端科学技術大。ライトを使ってゴブリンの影を探し、それを背中に背負った掃除機のような機械で吸い込む。吸い込むと、流体が送り込まれて実際に重たくなる。実際の像ではなく、影を呈示することで存在を感じさせるという狙いの作品。この作品が1位で予選を通過した | 【動画】ゴブリンを吸い込む様子 | 「bubble cosmos」、scope+中村正宏 筑波大学大学院。暗室に入ると、煙入りのシャボン玉が浮かび、それにプロジェクタから映像が投影される。写真はシャボン玉発生器 |
 |
 |
| 「球魂」、いよだま 北陸先端科学技術大学院大学。加速度センサーなどの入ったボールを、指示どおりに投げて、バッターを三振させるゲームスタイルの作品。子供達には大人気だった | 「超人ヌーク」、ヒッキーズ 北陸先端科学技術大学院大学。東京タワーやカブトムシなど、なんでも「抜く」ことで遊んでみようという作品 |
 |
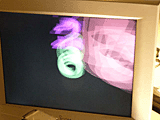 |
| 「遊ぶ声」、素人vs玄人 富山大学。シースルーHMDをかぶり、数字を叫ぶと、その数字が目の前に現れて飛び回るという作品 | |
残念ながらコンセプトに負けている作品も少なくないのだが、それぞれ学生たちによる作品なので、今後のブラッシュアップに期待したい。取材に伺ったのは平日、しかも台風の日であったにも関わらず未来館には親子連れも意外と多く、子供たちもゲーム感覚でインタラクティブ作品を遊んでいた。
●インタラクティブ東京
「インタラクティブ東京」、「IVRC」も同じ会場で行なわれたため、一般来場者たちは特に区別することなく両展に展示されたインタラクティブ作品を楽しんでいた。
「インタラクティブ東京」は、世界で活躍するインタラクティブ作品制作者が国内に多いのにも関わらず、インタラクティブ作品を実際に手に取って体験できる形で発表できる機会が少ないことから新たに企画されたイベントだ。
併せて開催された講演、パネルディスカッションセッションでの基調講演で、筑波大学の岩田洋夫教授は「インタラクティブ技術は万人が体験可能」と、実演発表へのこだわりを語った。
また、テクノロジーを見える形で呈示し、ツールとコンテンツが一体化したインタラクション作品やインターフェイス・アートなど、技術の面白さを真っ向から出すものを「デバイスアート」と呼ぶことを提唱。「デバイスアートはハードウェア要素が大きく、芸術性も高い。洗練された道具への美意識は古典的な日本文化に通じるところがある。新市場も創出するだろう」と語った。
「デバイスアート」は平成17年度から独立行政法人 科学技術振興機構(JST)の「戦略的基礎研究推進事業(CREST)」にも選ばれており、デバイスアートにおける技術体系を明らかにし、製作・評価の方法論を構築していくことを今後5年の間に目指すという。
 |
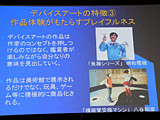 |
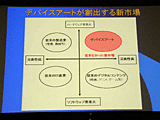 |
| 岩田洋夫 筑波大学機能工学系教授 | 「デバイスアート」の特徴。ユーザーが体験を通じて、自分なりの楽しみを発見する | 「デバイスアート」の占める市場位置。いわゆる「次世代ロボット」と同様の位置づけ。ただし岩田教授自身は、いわゆるロボットはデバイスアートとは別物だと考えているそうだ |
さて、「インタラクティブ東京」では、20の作品が展示されたが、ここではいくつか目立ったものを紹介する。
「Augmented Coliseum」は、小型ロボットとCGを組み合わせたAugmented Reality的ゲームだ。小型ロボットの位置を認識させることで、操作に合わせたCG(銃弾や爆発などのエフェクト)を上からプロジェクタで投影する。アイデアは単純なのだが、非常に面白い。ROBO-ONEなど二足歩行ロボット競技も盛んな昨今、いろいろな可能性が感じられるアプリケーションだ。なお計測にもプロジェクタを用いている。
 |
 |
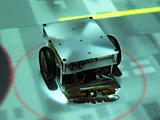 |
| 「Augmented Coliseum」 | システム全景 | 使われていた小型ロボット |
特定の方向からの音源のボリュームだけをアップしたい。そう思ったとき、通常ならばミキサーを操作することになるのだが「Sound Scope Headphone」は、それを単にクビを振るだけで調節するデバイス。電子コンパスと加速度センサーをつけたヘッドフォンだ。また耳の横に「フォーカスフラップ」なるものがつけられており、それを押すと聴きたい音をさらにアップさせることができる。
「水鈴」は、浮き球を用いたインタラクティブファニチャー。中には水が入れられていて、浮き球が浮いている。そこに手を突っ込んでまわりの試験管などにあてると、そこで奏でられた音をサンプリングして実空間で再提示する。同時に光と霧で癒し効果を狙う。もともと日本は水の浮き玉を入れて涼を味わう文化がある。もう1つ、風鈴も同様のファニチャーだ。それにインスパイアされてデジタルで拡張したものが水鈴である。ここには時間と空間、主体と客体を喪失させることを狙いがあったのだという。
 |
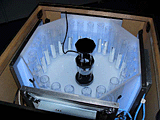 |
| 「Sound Scope Headphone」 | 「水鈴」 |
「Thermo Painter」は、サーモグラフィを使った作品。熱を感知して、手や指でさわることで落書きができる。熱を使っているので、息を吹きかけたり、お湯を筆で塗ったりすることでも絵が描けるところが面白い。
「バーチャルカヌー」は波面のリアルタイムシミュレーションによって、リアルな波の映像と水の抵抗力を実感できるという作品。個人的にはそれほどリアルには感じられなかったのだが……。
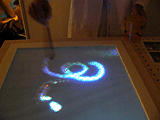 |
 |
| 「Thermo Painter」 | 「バーチャルカヌー」 |
「Kobito -Virtual Brownies-」は、昨年のIVRCに出展されていた作品のグレードアップバージョン。一見、箱が動いているだけなのだが、ディスプレイ越しに見ると、こびとが動かしている様子が見える。昨年見たものよりも、こびとたちの動きがずいぶん良くなっていた。
「Straw-like User Interface」も、昨年のIVRCに出展されていた作品。RFIDを使ったタグを、タグリーダーつきの皿の上に置いて、吸う。すると吸ったときの感覚が呈示される。思わず咳き込んでしまうくらい、エフェクトがきつかった。
 |
 |
 |
| 「Kobito -Virtual Brownies-」 | 【動画】こびとが箱を動かす様子 | 「Straw-like User Interface」 |
「TWISTER」。以前も本連載で紹介したことがある東大 舘研の全周囲立体映像ディスプレイ。直径約2mの回転体の中で、LEDアレイとパララクスバリア(遮光板)が回転しており、その残像によって立体映像が見える仕組み。今回展示された5号機では、画像が遙かに高精細になっていた。
 |
 |
| 「TWISTER V」。解像度は3,168×600ピクセル | 【動画】中で見られる映像コンテンツの一部 |
「Shaking The World」は、NTTコミュニケーション科学研究所による展示。「前庭感覚電気刺激」という手法を使い、耳の後ろに電気刺激を加えることで、加速度感覚を与える。被験者はまるで船の上に乗ったときのような体が傾く感覚を味わう。それによって、人間が歩く向きを多少操作したり、ゲーム画面に応じて加速度感覚を強制的に味合わせることができる。電気刺激の強度は、被験者自身がダイヤルで調整できる。
「KHRONOS PROJECTOR」は、ディスプレイの表面にタッチすることで、画面の時間軸を操作する。タッチディスプレイなどではなく、ビジョンチップで画面そのものの変位を捉えることで画面を変化させている。積層された時間を、画面そのものを押し込み、触覚で操作する感覚はかなり面白い。医学用途や、GISなど、さまざまな用途がありそうだ。
 |
 |
| 【動画】「Shaking The World」。ゲーム画面に応じて加速度感覚を被験者に加える。それによって体が実際に加速度を感じるので被験者は思わず体を動かしてしまう | 【動画】「KHRONOS PROJECTOR」。昼間の画面が映し出されているが、画面を押し込むと夜の画像が現れる |
●うけるインタラクティブ作品の作り方
パネルディスカッションの最後には、「うけるインタラクティブ作品はこう作る」と題した特別パネルも行なわれた。司会は岩田洋夫 筑波大学教授。パネリストは明和電機の土佐信道社長(吉本興業)、神戸大学の塚本昌彦教授、NTTドコモの福本雅朗氏。
まず、岩田教授は、最初に「おや」と思わせて意外性があって笑いを取ることが大切であり、もちろん確かな技術と、深淵な哲学が背後に必要である、と述べた。
ところが塚本教授は最初に「それは違う!」というスライドからプレゼンを開始。深淵な哲学といってもそんなに簡単ではないし、意外性やひねりも下手にやると審査員の反感を買うだけだ、と語った。ではどうすればいいのか。とにかく何かしら最先端技術を持ってくる、それをナンセンスな使い方で使う。そしてとにかく頑張る。そういう方法が良いのではないかと語った。
 |
 |
| 塚本昌彦 神戸大学教授。ウェアラブルの伝道師として著名 | NTTドコモ 福本雅朗氏 |
続けてNTTドコモの福本氏は、「Keep It Simple and Stupid」、本来は「Keep It Simle, Stupid!(もっと簡単に、この愚か者)」という言葉を紹介し、とにかくシンプルであることが重要であり「プレゼンは笑ってもらってナンボ、海外では特に、パッと見てわかるベタなギャグのほうが良い」と述べた。
 |
 |
 |
 |
| 福本氏がこれまで作ったもの。指輪型キーボードや骨伝導を使って指を突っ込むだけの電話、指パチするだけで機器をコントロールするリモコンなど、独創的なモノの開発者として広く知られている | |
続けて、明和電機の土佐信道社長が、これまで作ってきた「パチモク」や「魚コード」、「ジホッチ」、「ガチャコン」などを見せ、時折「(ダイヤルで操作する「ジホッチ」や「ガチャコン」について)今の機械からは計器類が消えてしまったので景気回復」といったダジャレを交えながら「うけなきゃ食い扶持がなくなる。そこで稼ぐのが明和電気の生き様」と語った。
 |
 |
 |
| 明和電機 土佐信道社長。「ツクバ系」のアートパフォーマンスで知られる | 「魚コード」は5万本売れた、と聞いて、塚本教授が「5万本ですか……」と答える | ジホッチ。ダイヤルを回すと、時報の音声で現在時刻を教えてくれる腕時計 |
 |
| 坂根厳夫 IAMAS 名誉学長 |
会場には坂根厳夫 IAMAS (情報科学芸術大学院大学、国際情報科学芸術アカデミー)名誉学長も顔を見せ、「テクノ漫談はこれからのお茶の間番組のネタになり得る」とコメントを述べた。いっぽう、「アートとテクノロジーをどのように繋いでいくかが課題。それがなんであるかは一緒に考えていきたい。アートの評論家も招いて激しい議論をやると良いと思う」と現状の問題点を指摘。そして「技術的な学会のなかでこんな楽しい話が聞けることが良い。アートとテクノロジカルアート、サイエンス、それらの間にある壁を破ってください」と語った。
それに答えて土佐信道氏は「現代アートがいつ頃からか、わくわくしなくなり、若い人たちも自分たちの時代のことしか語らなくなってきた。イマジネーションが減ってきている。でも逆にデザインの世界は非常に活気がある。なぜかというと経済と結びついているからだと思う。作品を買う買わないということで目利きがちゃんとついている。テクノロジカルアートが残るためには、買ってもらえるような良いものを作って頂かなければならない」と語った。
 |
| アーティスト 八谷和彦氏 |
続けて、「視聴覚交換マシン」等の作品、最近は「風の谷のナウシカ」に登場する、主人公ナウシカが乗るグライダー・メーヴェの実機を製作している(詳細は「OPENSKY ─the Project to make personal jet glider─」参照。)ことで知られるアーティスト 八谷和彦氏が発言した。
現在八谷氏は、NTTコミュニケーション研究所 NTTコミュニケーション科学基礎研究所 感覚運動研究グループの前田太郎氏、安藤英由樹氏らと、大阪・天保山で開催されている「ガンダム展」にて、フラナガン機関でのニュータイプ適性検査をイメージした作品を実演展示している。
「フラナガン機関」とは、「機動戦士ガンダム」の作中で、ニュータイプの研究をしていたとされる研究所の名前。展示は2人1組で体験する形式で、「インタラクティブ東京」でも出展されていた前田氏らの前庭感覚電気刺激を使い、目をふさいだ状態で立って歩き、もう1人のコントロールによって右左の操作指示の感覚を受けながら、障害物の風船を避けるというもの。「コンテンポラリーアートとしてのニュータイプテスト」だ。「ガンダム」最終回での、カツ、レツ、キッカの子供三人組による主人公アムロの誘導をイメージしたものだという。
八谷氏は「フラナガン機関のテストならば、みんな受けてみたいだろうと考えて制作したもの」と語り、すなわち「演出は大事」と強調した。また「劣化してしまうものは美術として残っていかない」ので、技術だけに頼るものは駄目だと述べた。
ソニーCSLの暦本氏も会場からコメントした。作品を見て「すごい」と思うことがあるが、一方で「すごいけど欲しくないもの」もある。もっとも高い評価は「あ、これ欲しい」と思うモノ、「すごくて欲しいもの」なのではないか、それは持続性のある「ウケ」なのではないか、と語った。「これをずーっと使っていたいと思うモノ、家にこれがあると幸せになるモノ、インタラクティブ・アートも、そこにいけば産業になる」と述べた。
●インタラクティブ・アートは定着するか
インタラクティブ・アート、メディア・アートの類が抱えている問題は、その他のデジタル・ガジェットや次世代ロボットなどが直面している問題と同根に思える。インターフェイスやインタラクションをはじめ情報処理一般、ロボティクス一般、アーティストなどがお互いの中に持つ壁を取り払い、広く議論することで面白い解が出てくるかもしれない。
□関連記事
【2004年9月3日】第12回学生対抗バーチャルリアリティコンテスト開催
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0903/kyokai28.htm
(2005年8月31日)
[Reported by 森山和道]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.