 |
 |
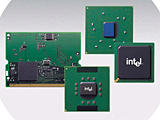 |
| Centrino製品群 |
Intelは、Centrinoモバイルテクノロジをついに正式発表した。
発表された具体的な内容やPCベンダの搭載ノートPCなどは別記事をチェックして頂くとして、本レポートではPentium Mの性能が、果たして期待通りのものであるのかを、実際にベンチマークプログラムを利用してチェックしていきたい。
●64KBのL1キャッシュと1MBのL2キャッシュを搭載
Pentium Mでもっとも性能に関わってきそうな部分といえば、キャッシュ容量だろう。L1キャッシュは、データ32KB+命令32KBの64KBを搭載しており、L2キャッシュはPC用のCPUとしては最大級となる1MBを搭載している。特に大容量のL2キャッシュは、メモリレイテンシの隠匿につながり、性能向上につながりそうだ。
拡張命令セットに関しては、MMX、ストリーミングSIMD拡張命令(SSE)に加え、ストリーミングSIMD拡張命令2(SSE2)にも対応している。
なお、クロックグレードに関しては、一昨日の記事で説明したとおりで、通常版が1.60GHz、1.50GHz、1.40GHz、1.30GHzとなっており、低電圧版が1.10GHz、超低電圧版が900MHzという構成になっている。
●ベンチマークにはMobileMark2002を利用
それでは、ベンチマークプログラムを利用して、Pentium Mの性能を計測していこう。今回はベンチマークとして、BAPCoのMobileMark2002、SYSmark2002、スクェアのFinalFantasy XI Official Benchmarkの3つの利用した。
ユーザーがノートPCを、特にモバイルとして利用する場合には、ACアダプタに接続して机の上などで利用する場合と、喫茶店や新幹線、飛行機の中などバッテリで利用する場合の2つの使い方が考えられる。
SpeedStepやLongRunのような、クロックや電圧を多段階で変動させながら利用する技術がCPUに採用される以前は、ACアダプタで利用しても、バッテリで利用しても同じ性能だったが、最近ではバッテリ駆動時とそうでない場合では、その性能が異なる。
また、バッテリ駆動時には性能もさることながら、バッテリ駆動時間も重要になってくる。いくらパフォーマンスが高くても、バッテリで長時間使えなければあまり意味がない。そこで、バッテリ駆動時の性能とバッテリ駆動時間を同時に計測しようというのがMobileMark2002だ。
MobileMark2002ではSYSmark2002でも利用されている、以下のアプリケーションを利用してパフォーマンスを計測する。
◆MobileMark2002のアプリケーション
・Microsoft Word 2002
・Microsoft Excel 2002
・Microsoft PowerPoint 2002
・Microsoft Outlook 2002
・Netscape Communicator 6.0
・McAfee VirusScan 5.13
・Adobe Photoshop 6.0.1
・Macromedia Flash 5
・WinZip 8.0
これらのアプリケーションを90分1クールで実行しパフォーマンスを計測する。高速なCPUでは90分より前に終了してしまうので、その間はポーズモードに入り、90分たつと再びアプリケーション実行プロセスをバッテリが無くなるまで繰り返し実行することで、バッテリ駆動時間を計測する。
スコアとしては性能を示すPerformance Ratingとバッテリ駆動時間を示すBatteryMarkの2つを導き出す。なお、Performance Ratingは相対値で、モバイルPentium III 1GHzを100として基準としている。
ACアダプタ駆動時の性能を測るのには、PCの性能を示す標準的なベンチマークであるSYSmark2002を利用し、同じように3Dを計測するのに、人気の3DゲームであるFinal FantasyのベンチマークであるFinalFantasy XI Official Benchmarkを利用した。
●モバイルPentium 4-Mを上回る性能を発揮する通常版Pentium Mプロセッサ
それでは、Pentium Mのパフォーマンスをチェックしていこう。今回は、通常版のPentium M 1.60GHzを搭載したマシンと、同じく通常版Pentium M 1.30GHzを搭載したマシンを入手した。Pentium M 1.60GHzのマシンは、開発途上のODM用ノートPCであり、チップセットにはIntel 855PM、グラフィックスにはATI MOBILITY RADEON 9000(32MB)、メモリ256MB(PC2100)、HDDに5,400rpmの東芝MK4019GAX(40GB)を採用し、DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ内蔵、バッテリは6セルで48W/hのハイエンドスペックのマシンとなっている。
なお、本製品は実際に販売される製品そのものの評価ではなく、あくまでPentium M 1.60GHzの性能をチェックするための参考の結果であることをお断りしておく。
Pentium M 1.30GHzを搭載したマシンはNECのLaVie Mで、同じくグラフィックスにはMOBILITY RADEON 9000(32MB)、メモリ256MB(PC2100)、HDDには日立のDK23EA-60/4,200rpm、6セルバッテリ(48W/h)を採用と、こちらも十分ハイエンド仕様の2スピンドルシン&ライトノートPCだ。
比較に用意したのは、日本アイ・ビー・エムのThinkPad A31p(モバイルPentium 4 2.0GHz-M搭載、Intel 845MP、FIRE GL7800/32MB、メモリ256MB(PC2100)、HDDは日立 IC25T060ATCS05/5,400rpm、DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ内蔵、6セル-48W/h、ThinkPad T30(モバイルPentium 4 1.80GHz-M、Intel 845MP、MOBILITY RADEON 7500/16MB、256MB PC2100、東芝MK4019GAX/5,400rpm、DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ内蔵、6セル-48W/h)、ThinkPad X30(モバイルPentium III 1.20GHz-M、Intel830M、ビデオ機能はチップセット内蔵、HDDはIC25N040ATCS04/4,200rpm、6セル-48W/hの3製品だ。
環境、結果は、表1とグラフ1~3の通りで、マシン名でなく搭載しているCPUの名前で表記している。
【テスト環境】| Pentium M 1.60GHz | Pentium M 1.30GHz | モバイルPentium 4 2.0GHz-M | モバイルPentium 4 1.80GHz-M | モバイルPentium III 1.20GHz-M | 超低電圧版モバイルCeleron 600A MHz | TM5800 867MHz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー名/マシン | - | NEC/LaVie M | IBM/ThinkPad A31p | IBM/ThinkPad T30 | ThinkPad X30 | ソニー バイオU (PCG-U101) | ソニー バイオU (PCG-U1) |
| チップセット | Intel 855PM | Intel 845MP | Intel 830M | Intel 855PM | CPU内蔵 | ||
| メモリ | 256MB(DDR266) | 256MB(PC133) | 256MB(DDR266) | 256MB(PC133) | |||
| HDD | 東芝MK4019GAX 5400rpm | 日立 DK23EA-60 4,200rpm | 日立 IC25T060ATCS05 5,400rpm | 東芝 MK4019GAX 5400rpm | IBM IC25N040ATCS04 4,200rpm | 東芝 MK3004GAH 4,200rpm | 東芝 MK2003GAH 4,200rpm |
| ビデオチップ(ビデオメモリ) | MOBILITY RADEON 9000 (32MB) | MOBILITY FIRE GL7800 | MOBILITY RADEON 7500 (16MB) | Intel830M内蔵 | MOBILITY RADEON (16MB) | MOBILITY RADEON (8MB) | |
| バッテリ | 6セル/48Wh | 角形3セル/24Wh | 3セル/24Wh | ||||
■ベンチマーク結果
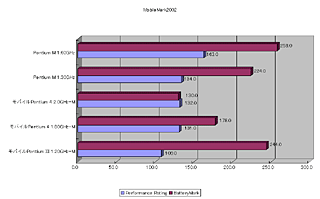 |
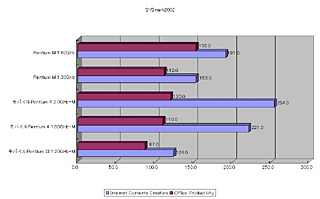 |
| 【グラフ1】MobileMark2002 | 【グラフ2】SYSmark2002 |
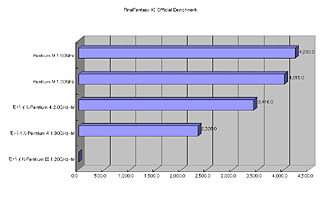 |
| 【グラフ3】FinalFantasy XI Official Benchmark |
MobileMark2002に関しては、すでにIntelから発表されている公式結果の通り、Pentium M 1.60GHzが、モバイルPentium 4 2GHz-MやモバイルPentium 4 1.80GHz-Mを大きく上回った。バッテリ駆動時間だが、いずれも6セル-48W/hとほぼ同じ容量のバッテリを採用しているのに、モバイルPentium 4-Mでもっとも優秀だった1.80GHzの178分を大幅に上回り、なんと258分を実現している。実に40%もバッテリ駆動時間が延びている。
もっとも、これらは同じプラットフォームで比較しているわけではないので、あくまで参考値といえるが、同じ容量のバッテリであることを考えると、Pentium M 1.60GHzシステムのバッテリ駆動時間がかなり期待できるものだと言っていいだろう。
Pentium M 1.30GHzを搭載したNECのLaVie Mも224分という、4時間弱の駆動時間を記録しており、モバイルPentium 4-M搭載2スピンドルノートPCの代表といえるThinkPad T30が3時間弱だったことを考えると、Pentium Mを搭載することで、バッテリ駆動時間を延長することが可能になっているということができるだろう。
ただし、SYSmark2002のInternet Contents Creationに関しては、モバイルPentium 4-Mの圧勝と言ってよい。これは、Internet Contents Creationに含まれるテストが、クロック周波数の影響が大きいSSE/SSE2命令を多数含んでいるためだと考えられる。
SSE命令やSSE2命令を実行する場合には、複数の処理をまとめて行なうことになるので、CPU内部の実行効率よりは、クロック周波数が性能に大きな影響を与える。このため、モバイルPentium 4-Mが優秀なスコアをたたき出していると考えることが可能だろう。従って、SSE/SSE2命令が有効に活用できるビデオエンコードやMP3のエンコードなどに関しては、モバイルPentium 4-Mの方がやや有利といえる。
しかし、同じSYSmark2002でもOffice Productivityに関しては、Pentium Mの圧勝だ。モバイルPentium 4 2.0GHz-Mが120であったのに対して、Pentium M 1.60GHzは153と大幅に上回っている。また、Pentium M 1.30GHzも112とモバイルPentium 4 1.80GHz-Mの110を上回っており、こちらも500MHz上のモバイルPentium Mを上回っている。
Office Productivityに採用されているようなオフィスアプリケーションでは、メモリレイテンシが性能に大きな影響を与える。Pentium Mでは1MBという大容量L2キャッシュを搭載しており、メモリレイテンシの隠匿という意味では、L2キャッシュが512KBのモバイルPentium 4-Mに比べて有利であり、それが大きな理由だと考えられるだろう。
なお、グラフ3のFinalFantasy XI Official Benchmarkは、CPUのみならずグラフィックスチップが及ぼす影響が大きく、今回はPentium M搭載ノートはいずれもATIのMOBILITY RADEON 9000を搭載しており、MOBILITY RADEON 7500を搭載しているモバイルPentium 4-M搭載ノートPCに比べて有利だ。このため、あくまで参考値だが、数値を見てわかるようにいずれのノートPCでもFinal Fantasy XIを遊ぶのに十分な性能を備えているということができるだろう。
●消費電力が気になる超低電圧版モバイルCeleron 600A MHz
本日ソニーから発表された新しいバイオUであるPCG-U101(以下U101)は、Baniasコアの超低電圧版モバイルCeleron 600A MHzを採用している。このCPUはPentium Mをベースに、L2キャッシュを半分(512KB)にしてエンハンストSpeedStepテクノロジを無効にしたバージョンで、Intelの正式発表には入っていないが、間違いなくBaniasコアを採用している。
この超低電圧版Celeron 600A MHzだが、仕様はいまいちはっきりしていない。というのも、このCeleron 600A MHzはIntelのロードマップなどにも乗っていない特別版であり、ソニー以外のOEMメーカーが採用していないため、どのような電圧で動作しているのかが伝わってこないためだ。超低電圧版を名乗ることを考えると、その熱設計の仕様である7Wを切っていることが1つの条件になる。
ちなみに、Pentium Mには、600MHz時の電圧設定は通常版Pentium Mおよび低電圧版Pentium Mの0.95Vと、超低電圧版Pentium Mの0.85Vの2つの設定がある。
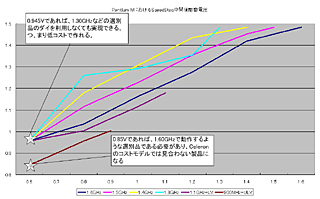 |
| 【図1】Pentium Mの電圧変動グラフ |
図1は一昨日掲載した記事のうち、Pentium Mの電圧変動を示すグラフだが、前者であれば(1)になり熱設計消費電力は6Wで平均消費電力が1W以下、後者であれば(2)で熱設計消費電力は4Wで、平均消費電力は0.5W以下になる。
筆者は前者である可能性が高いと思う。というのも、仮に後者だとすれば、一昨日説明したとおり、選別された、本来ならPentium M 1.60GHzという600ドルを超える価格に設定できるダイを、100ドル台半ばにしかならないCeleronとして販売しなければならないことになるからだ。
バイオU101の実売16万円前後という価格を見る限り、IntelがこのCPUに対して超低電圧版Pentium Mなみの価格(200ドル台半ば。それでもPentium M 1.60GHzに比べればずっとお得だが)にしたとは到底思えないので、おそらくモバイルCeleron並の価格で販売されたと考えるのが妥当だろう。であれば、さほど選別されたコアでなくても7Wが実現できる0.95Vである可能性が高いと思うのだ。
だが、もし0.85Vに設定されているのであれば、Intelは損を覚悟でそれをやっているということを意味する。もしそうならば、それはなぜだろうか? そこまでしてでも、ソニーに(あるいは日本メーカーに)BaniasコアのCPUを使ってもらいかったのだろう。
では、どうしてIntelはソニーを取り込みたかったのだろうか? それは、ソニーがTransmetaにとって、重要な顧客だからだ。ソニーは、前モデルのバイオUの他、C1、バイオGTなど幅広くTransmetaを使ってきた、Transmetaの大手の顧客なのだ。
“パラノイア”Intelにとっては、ノートPCの小さな市場とはいえ、Transmetaに市場を持って行かれることは、将来への禍根を残すことになる。実際、Intelは、バリュー市場に侵食するのにやや対応が遅れ、その結果AMDのその後の躍進を招く結果になっている。
今はノートPC全体で数%にしかならないサブノート、ミニノート市場だが、近い将来には大化けする可能性もないとは言えない。そうしたことを見据えているからこそ、IntelはTransmetaをつぶすための低電圧版、超低電圧版に引き続き、限定モデルながら超低電圧BaniasコアCeleronという隠し球を投げてきたと考えるのが妥当だと思う。
消費者にとっては、歓迎すべきことと言えるこの競争だが、その競争もTransmetaあればこそだ。一昨日の記事の繰り返しになるが、詳細が明らかにされたTM8000をぜひとも成功させて、Intelにプレッシャーをかけ続けて欲しいものだ。
●超低電圧版モバイルCeleron 600A MHzはTM5800 867MHzの倍近い性能を発揮
さて、U101の性能を系するために、今回は初代バイオUであるPCG-U1(以下U1)と比較することにした。U1は、CPUにTransmetaのCrusoe TM5800 867MHzが採用されている。HDDは同じ東芝の1.8インチドライブが採用されており、ほぼCPUに関する比較となる。結果はグラフ4~6の通りだ。
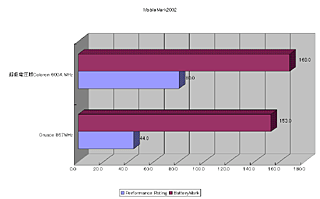 |
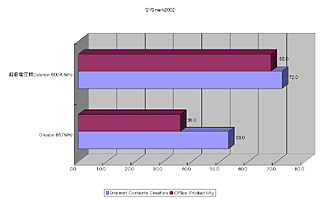 |
| 【グラフ4】MobileMark2002 | 【グラフ5】SYSmark2002 |
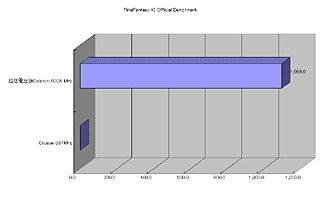 |
| 【グラフ6】FinalFantasy XI Official Benchmark |
処理能力(Performance Rating)では明らかに超低電圧版モバイルCeleron 600A MHzを搭載したU101が上回っている。U101のスコアは80と、U1のスコアである44の倍近いものとなっている。しかも、バッテリ駆動時間は若干延びているという結果になっており、バッテリ駆動時間を犠牲にせずに処理能力を伸ばすことに成功しているということが見て取れる。
SYSmark2002に関しても、いずれも超低電圧版モバイルCeleron 600A MHzを搭載したU101がTM5800 867MHzを搭載したU1を大きく上回っている。
なお、注目したいのは、Final Fantasy XIの結果だ。ソニーの発表によると、U101のグラフィックスチップはMOBILITY RADEONとなっており、U1のそれと変わっていない。ところが、U101ではFinalFantasy XI Official Benchmarkが動作するのに、U1では動作しないという結果となった。
この差は、U101に採用されているMOBILITY RADEONが、MOBILITY RADEONといいつつも、ハードウェアT&Lエンジンに対応している新コアであることが影響している。FinalFantasy XI Official BenchmarkはハードウェアT&Lエンジンを持っているグラフィックスチップではないと動作しないのだ。3DMark2001 Second Editionでチェックすると、確かにU101のMOBILITY RADEONはハードウェアT&Lエンジンを持っていることがわかった。
ATI TechnologiesのWebサイトを見る限り、MOBILITY RADEONはハードウェアT&Lエンジンを持っていないことになっているのだが、実際には持っている。RADEONのレンダリングエンジンを持ち、ハードウェアT&Lエンジンを持っているということになれば、事実上MOBILITY RADEON 7500と同じということになってしまう。ATIが詳細を明らかにしていないためわからないが、おそらくMOBILITY RADEONはかなり古いコアをベースにしているので、すでに生産は停止しており、その代わり、より上位のコアをMOBILITY RADEON相当の価格にして販売している、そのあたりが真相ではないだろうか。
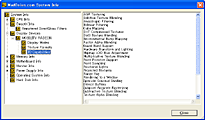 |
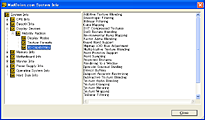 |
| 3DMark2001 SEでU101のMOBILITY RADEONの3D機能を表示したところ。ハードウェアT&Lエンジンがあるのがわかる | 3DMark2001 SEでU1のMOBILITY RADEONの3D機能を表示したところ。ハードウェアT&Lエンジンはない |
さて、FinalFantasy XI Official Benchmarkの結果だが1,098と、なんとかゲームになるレベルとなっている。すごく快適というわけではないだろうが、とりあえずそれなりに遊べるレベルということができるだろう。
なお、U101に関する詳細なレポートは、後日レビュー記事として掲載する予定だ。
●高い処理能力を実現しつつ、バッテリ駆動時間を伸ばすCentrinoモバイルテクノロジ
以上のように、Pentium Mは、SSE/SSE2命令を多用したような場合を除き、モバイルPentium 4-Mを上回る処理能力を発揮し、特にオフィスアプリケーションのようなユーザーがモバイル環境で利用する機会が多いアプリケーションで高い処理能力を発揮している。しかも、Pentium Mを搭載したノートPCでは、CPUやチップセットの平均消費電力が、従来製品に比べて低く抑えられているため、バッテリ駆動時間は明らかに延びている。
本日、多数のPentium M搭載ノートPCが発表されたが、いずれも魅力的な製品に仕上がっている。また、本日発表された製品ばかりでなく、今後多くのPCベンダからより魅力的な製品が登場してくる可能性が高く、今後も期待したいところだ。
□関連記事
【3月11日】【短期集中連載】 Centrinoの謎を解く
第2回:低消費電力チップセット「Intel 855PM」の秘密
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0311/cent02.htm
【3月10日】【短期集中連載】 Centrinoの謎を解く
第1回:BaniasことPentium Mの秘密に迫る
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0310/cent01.htm
(2003年3月12日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.