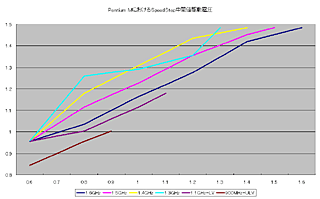|
 |
Intelがまもなく正式発表すると思われる「Centrinoモバイルテクノロジ」。本記事はCentrinoモバイルテクノロジが、どのような技術で、今後のノートPC製品にどのような影響を与えていくのかを数回に分けて紹介していきたい。
Centrinoモバイルテクノロジは、CPUの「Pentium M」プロセッサ、チップセットの「Intel 855」ファミリー、無線LANモジュールの「Intel PRO/Wireless 2100」ファミリーの3つの要素から構成されており、それぞれについて市場的な観点と、技術的な観点から説明していきたい。初回となる今回は、Centrinoモバイルテクノロジの最も重要なピースであるCPUの「Pentium M」についてだ。
●半分はずれで半分あたりの「Pentium Mプロセッサ低消費電力CPU説」
「Pentium Mは従来のCPU(例えばモバイルPentium III-M)に比べて低消費電力なCPUだ」というのは、おそらく多くのCentrinoに関する記事の中でふれられているキャッチフレーズだろう。Pentium Mプロセッサは、コードネーム「Banias」で呼ばれていた頃から、消費電力が低いCPUと報じられてきたため、読者の多くもそういう印象を持っていることだろう。
確かに、Intelもそういう説明をしている。実際、IntelがPentium Mのマイクロアーキテクチャを語る時には、
・マイクロOpsフュージョン
・アドバンスト分岐予測
・専用スタックマネージャ
・低消費電力な大容量L2キャッシュ
などの特徴をあげ、「これらにより効率よく命令を実行しているので、省電力なんですよ」というアピールに徹している(これらに関しての説明は、後藤弘茂氏の記事が詳しいので、こちらを参照していただきたい)。
そうしたIntelの非常にうまいアピールもあり、多くのユーザーの間では冒頭の「Pentium Mは従来のCPU(例えばモバイルPentium III-M)に比べて低消費電力なCPUだ」ということが半ば定説ということになりつつある。
だが、この定説、実は半分は当たっているが、半分ははずれている。
●通常版、低電圧版、超低電圧版の3つの製品が存在するPentium M
今回、Intelが発表するPentium Mプロセッサは、以下のような製品が存在する。
【表1:Pentium Mのクロックと電圧】| 動電圧/熱設計消費電力 | SST時のクロック/電圧/熱設計消費電力/平均 | |
|---|---|---|
| 通常版 | ||
| 1.60GHz | 1.48V/24.5W | 600MHz/0.96V/6W/1W以下 |
| 1.50GHz | 1.48V/24.5W | 600MHz/0.96V/6W/1W以下 |
| 1.40GHz | 1.48V/22W | 600MHz/0.96V/6W/1W以下 |
| 1.30GHz | 1.39V/22W | 600MHz/0.96V/6W/1W以下 |
| 低電圧版 | ||
| 1.10GHz | 1.18V/12W | 600MHz/0.96V/6W/1W以下 |
| 超低電圧版 | ||
| 900MHz | 1.00V/7W | 600MHz/0.85V/4W/1W以下 |
現時点では正式発表前のため、上記の駆動電圧や消費電力のデータなどは筆者が独自に取材して得たデータであり、Intelの公式な見解ではないことをお断りしておく。ただし、実際にはこれから大きくはずれることはまずないだろう。
Pentium Mには、通常版、低電圧版、超低電圧版の3種類が存在する。これらの違いは、熱設計消費電力(Thermal Design Power:TDP)の違いであり、通常版が25Wまで、低電圧版は12Wまで、超低電圧版は7WまでをそれぞれカバーするCPUになる。
現在のノートPCは、熱設計がベースになっており、CPUの熱設計消費電力はノートPCのフォームファクタに与える影響が大きい。Pentium M登場以前、ノートPCをフォームファクタで分類し、熱設計で分類し、セグメント分けするのであれば以下のようになっていた。
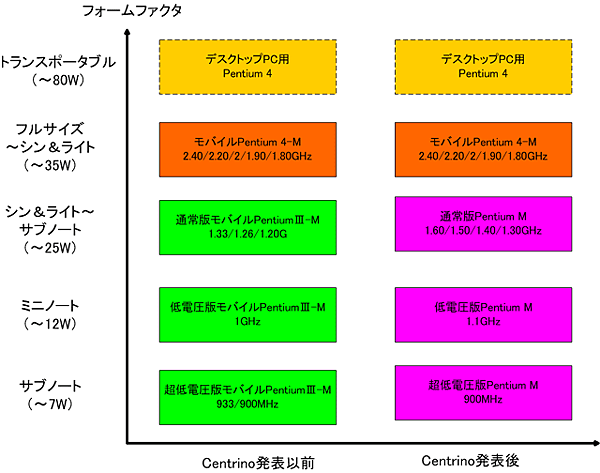 |
| 【図1:フォームファクタ別の分類】 |
左側が現在のIntelのモバイル向けCPUで、上からTDP 35W以上がデスクトップリプレースメントと呼ばれる市場で、大型の液晶パネルを採用し、デスクトップPC用のPentium 4が採用されている市場だ。TDP 25~35Wのセグメントは、フルサイズノートPCやシン&ライトと呼ばれる2スピンドル(HDDとCD-ROMドライブ内蔵)薄型ノートPCなどに利用され、モバイルPentium 4-Mが採用されてきた。
12~25Wのセグメントは、シン&ライトとサブノートなどに利用され、モバイルPentium III-Mの通常版が利用されてきた。7~12Wのセグメントはサブノートなどに利用され、モバイルPentium III-Mの低電圧版が利用されてきた。さらに、7W以下がミニノートのためのセグメントで、モバイルPentium III-Mの超低電圧版が利用されてきた。
Pentium Mの~25W、~12W、~7Wという熱設計省電力の傾向は、モバイルPentium III-Mの傾向と一致する。つまり、熱設計消費電力的観点から見れば、Pentium MはモバイルPentium III-Mを置き換える製品と言っていいことが判る。従って、Pentium M以降の各セグメント向けCPUは図1の右側のようになる。
なお、補足しておくと、デスクトップリプレースメントの市場には、「-M」がつかないモバイルPentium 4プロセッサが第3四半期に投入される。モバイルPentium 4は、基本的にはデスクトップPC向けCPUだが、SpeedStepテクノロジに対応していることが大きな違いとなる。
モバイルPentium 4-Mも、今年中はOEMメーカーに対して提供されるが、フルサイズのものはモバイルPentium 4へ移行し、シン&ライトはPentium Mへ移行していくことで、この25~35Wというセグメントは、デスクトップリプレースメントへ吸収されていくことになるだろう。
●Pentium Mプロセッサにすることで、むしろ増大する熱設計消費電力
以下の表は、Pentium M 1.60GHz+Intel 855GM、モバイルPentium III-M 1.20GHz+Intel 830M、モバイルPentium 4-M 2.40GHz+Intel 852GMという3つのプラットフォームにおける熱設計消費電力(TDP)の合計を表にしたものだ。いずれのチップセットとも、Portraコアを採用したIntelのグラフィックス統合型チップセットで、比較に適していると言える。
【表2:3つのプラットフォームの熱設計消費電力(TDP)】| Pentium 4-M+Intel 852GM | Pentium III-M+Intel 830M | Pentium M+Intel 855GM | |
|---|---|---|---|
| CPU | 35 | 22 | 24.5 |
| メモリ | 12 | 8 | 12 |
| ノースブリッジ(Int Gfx) | 3 | 3.8 | 3.2 |
| サウスブリッジ | 2.2 | 2 | 2.2 |
| 合計 | 52.2 | 35.8 | 41.9 |
見て判るように、モバイルPentium III-M 1.20GHz+Intel 830Mに比べて、Pentium M 1.60GHz+Intel 855GMのTDPは増大している。要因は3つある。1つはCPU自体のTDPが若干あがっていること、もう1つはメモリがDDR SDRAMになったことによる上昇、さらにICH3-MからUSB 2.0コントローラが有効になったICH4-Mに変更することで0.2W上昇していることの3つだ。
従って、OEMベンダの観点で言えば、Pentium III-MからPentium MにCPUを変更することは、熱設計の上では消費電力は増えていることになり、熱設計はより厳しくやる必要があると言える。つまり、少なくとも熱設計消費電力の観点から言えば、「Pentium Mプロセッサ低消費電力CPU説」は微妙になってくると言えるわけだ。
●イールドの関係で上のクロックになればなるほどSpeedStep有効時には低消費電力
Pentium Mでは、コードネーム“Geyserville III”と呼ばれてきた新しいエンハンストSpeedStepテクノロジ(以下、区別するためにGV3)がサポートされる。
従来のモバイルPentium 4-M、モバイルPentium III-MでサポートされてきたGeyserville IIのエンハンストSpeedStepテクノロジ(同GV2)ではクロック・電圧を動的に変動させる機能がサポートされていたが、多段階のスケーリング機能は用意されていない。これに対してGV3では、多段階におけるクロック・電圧の変動機能がサポートされる。具体的には、VID(Voltage ID)よばれる駆動電圧の信号を動的に変更することで、電圧も変動する。
Pentium Mでは、最高クロックから最低クロックとなる600MHzまで、200MHz刻みでクロックがスケーリングしていく(なお、ギガヘルツ表記で、小数点第一位が奇数になるクロックは飛ばされる。例えば、1.5GHz、1.3GHz、1.1GHz、0.9GHz、0.7GHzは利用されない)。Pentium MにおけるクロックとVIDの仕様は、表3およびグラフ1のようになっている。
【表3:Pentium MのクロックとVIDの仕様】| 1.6GHz | 1.5GHz | 1.4GHz | 1.3GHz | 1.2GHz | 1.1GHz | 1GHz | 900MHz | 800MHz | 700MHz | 600MHz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60GHz | 1.484 | 1.42 | 1.276 | 1.164 | 1.036 | 0.956 | |||||
| 1.50GHz | 1.484 | 1.452 | 1.356 | 1.228 | 1.116 | 0.956 | |||||
| 1.40GHz | 1.484 | 1.436 | 1.308 | 1.18 | 0.956 | ||||||
| 1.30GHz | 1.388 | 1.356 | 1.292 | 1.26 | 0.956 | ||||||
| 1.10GHz-LV | 1.164 | 1.036 | 1.004 | 0.956 | |||||||
| 900MHz-ULV | 1.004 | 0.956 | 0.844 |
なお、このデータは正式発表前であるということもあり、Intelが公開したデータではなく、筆者が独自に取材して判明した結果であることをお断りしておく。
見て判るように、クロックグレードが最も上の1.60GHzモデルは、中間のクロックにおける電圧は、下のクロックグレード(1.50GHz、1.40GHz、1.30GHz)に比べて低くなっていることがわかる。1.60GHzグレードは、中間の1.4GHz、1.3GHz、1.2GHz、1GHz、800MHzの各段階において、通常版の他のクロックグレードを下回っている。
なぜこうしたことが起こるかと言えば、それは歩留まり(イールド)の関係だ。基本的にどのクロックグレードも同じ製造過程で作られているが、最終的にパッケージに封入される段階で、テストされて、どのクロックグレードであるかが選別される。
この時に、同じ1.48Vをかけて1.6GHzまであげることができたダイは1.60GHzとして出荷され、1.3GHzでしか動かなかったダイは1.30GHzとして出荷されることになる。電圧をあげればクロックをあげやすくなることはよく知られているが、その逆も真なりでクロックを下げれば電圧も下げやすくなる。
ところが、1.6GHzを1.48Vでスタートする1.60GHzのダイと、1.3GHzを1.48Vでスタートする1.30GHzのダイでは、中間の電圧に差が出てしまうということなのだ。
つまり、SpeedStepが有効である場合の中間クロックの各段階において、通常版Pentium Mで最も低消費電力なCPU、それはなんと1.60GHzであるのだ。
●非常にお買い得価格となっている低電圧版と超低電圧版
ところで、Pentium Mには、通常版のほか、低電圧版と超低電圧版の2つが用意されている。
低電圧版Pentium M 1.10GHzは、1.1GHz時における駆動電圧が1.18VでTDPは12Wとなっており、200MHz単位でスケーリングして最終的には通常版と同じ600MHz/0.96Vに到達する。超低電圧版Pentium M 900MHzは900MHzにおける駆動電圧が1Vと非常に低く、最終的には600MHzで0.85Vに達する。
グラフ1には低電圧版、超低電圧版も掲載したが、見てわかるように、低電圧版、超低電圧版は、最も良品のダイである通常版1.60GHzよりも消費電力がさらに下回っていることがわかる。このことは、仮に、低電圧版、超低電圧版のクロックをあげて行けば、1.60GHzで回せる可能性が高いことを意味している。超低電圧版Pentium M 900MHzに至っては、おそらく1.60GHz以上で駆動させることが可能だろう。
ところが、それでは価格も1.60GHzと同じかと言えば、そうではない。まだ正式発表前であるので、正式な値段は不明だが、情報筋によればPentium M 1.60GHzが600ドル(日本円で7万円強)オーバーであるのに対して、低電圧版Pentium M 1.10GHzは200ドル台半ば(日本円で3万円強)、超低電圧版Pentium M 900MHzも同じクラスだが、ちょっと安いというレベルになるという。つまり、本来であれば600ドルの価格が1/2以下なのだ。
これは、非常に大胆な価格設定といえるだろう。この低電圧版、超低電圧版を除き、Intelの価格設定は選別した高クロックで動くものは高く、そうでないものは安くという価格設定になっている。従って、本来であれば高クロックで動くはずの低電圧版Pentium M、超低電圧版Pentium Mは値段がPentium M 1.60GHzと同じか、それより高くてもなんら不思議ではない。
なぜ、Intelがこうした価格設定をするのかと言えば、それはこのマーケットにいる競合相手をつぶしたいからだ。言うまでもなくTransmetaである。TransmetaのCrusoeは当初は200ドルを超えるような高い価格をつけていたが、現在では100ドル台という低価格路線を敷いているという。それはもちろんIntelの低電圧版、超低電圧版に対抗するためだ。
TransmetaもPentium M、特にこの低電圧版、超低電圧版がいかに脅威か判っているはずだ。だからこそ、彼らは10日、TM8000の詳細を明らかにしたのだろう。少しでもユーザーやメーカーの興味を自分たちに向けたいからだ。果たしてそうした努力が報われ、ミニノートにCrusoeを採用している彼らのOEMメーカーを守ることができたのか、その審判はまもなく下される。
ただ、1つだけいっておきたいのは、Intelが低電圧版、超低電圧版を、200ドル台というバーゲン価格にしているのは、Transmetaがこの市場でがんばっているからこそだ。そうした意味では、今後もTransmetaがこの市場をもっとかき回してくれるということに期待したい。
●平均消費電力ではモバイルPentium III-Mを下回るPentium M
さて、以上のようにPentium Mについて長々と解説してきた。すでに「半分はずれ」については説明したので、半分あたりの部分について説明しておく必要があるだろう。
【表4:3つのプラットフォームの平均消費電力差】| Pentium 4-M+Intel 852GM | Pentium III-M+Intel 830M | Pentium M+Intel 855GM | |
|---|---|---|---|
| CPU | 2 | 1.5 | 1 |
| メモリ | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| ノース | 2 | 2 | 1.7 |
| サウスブリッジ | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 合計 | 4.9 | 4.3 | 3.6 |
表4は、先ほどのPentium M 1.60GHz+Intel 855GM、モバイルPentium III-M 1.20GHz+Intel 830M、モバイルPentium 4 2.40GHz-M+Intel 852GMという3つのプラットフォームにおける、平均消費電力の違いだ。
平均消費電力とは、ユーザーが通常利用するアプリケーションなどを実行している段階における消費電力のことだ。DVDプレーヤーなどの一部のアプリケーションを除き、ユーザーがPCを使っている時には、PCには比較的余裕がある、つまりCPUに限界まで負荷をかけている時間はほとんどない場合が多い。従って、実際には、ピーク時の消費電力であるTDPよりも、むしろこの平均消費電力が低い方がバッテリ駆動時間に大きな影響を与えるのだ。
この平均消費電力では、明らかにPentium Mが、モバイルPentium III-MやモバイルPentium 4-Mに比べて低くなっている。つまり、Pentium Mは低消費電力なCPUであるというのは半分当たっているのだ。
「熱設計消費電力ではP3よりちょっと高いけど、平均消費電力ではP3よりも有利で、バッテリ持続時間は明らかに延びる」、これこそがBaniasことPentium Mの正体なのだ。
(2003年3月10日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.