



 |
|
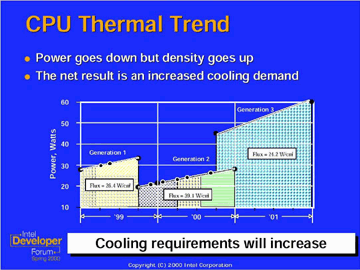 |
| IDFで公開された熱対策トレンド (c)2000 Intel Co. |
1.9~2GHzというクロックは、IDFの技術セッションでIntelが示した、Willametteのための放熱機構やPCの熱設計ソリューションから推測したものだ。このセッションのスライドによると、1.4GHzで登場すると見られるWillametteの消費電力は45W前後となっており、2001年を通じてWillametteの消費電力がリニアに上昇するという。グラフはそれほど詳細ではないので大まかな数字しか出せないが、Intelの示した2001年のWillametteの消費電力の予測は、およそ次のようになっている。
第1四半期の頭 約48W
第2四半期の頭 約52W
第3四半期の頭 約55W
第4四半期の頭 約59W
第4四半期末 約62W
CPUコアの物理設計とプロセス技術が変わらず、駆動電圧も同じなら、クロックは消費電力の上昇と比例して上がる。そのため、このグラフから、およそのWillametteの2001年のクロックは逆算できる。下が、消費電力から推定できるWillametteのクロックだ。
第1四半期の頭 約1.5GHz
第2四半期の頭 約1.6GHz
第3四半期の頭 約1.7GHz
第4四半期の頭 約1.8GHz
第4四半期末 約1.9GHz
つまり、順当にいけば、来年末にはWillametteは1.9GHzに達することになる。さらに、IntelがCPUの設計やプロセス技術の改良などで、さらに上乗せで高クロック化と低消費電力化を果たした場合には、2GHzに到達できるだろう。これまでと比べると、意外とのんびりしたクロック向上のペースだが、それはこのところの極端な高クロック化の方が異常だったのだ。Willametteには事実上ライバルがいないので、この程度のペースに落ち着くのではないだろうか。
●意外と“小さな”Willamette
また、このグラフからは、Willametteがそれほど巨大な(トランジスタ数の多い)チップではないことも推測できる。つまり、CPU自体の製造コストが、Intelの従来の新アーキテクチャCPUよりも低い可能性が高いということだ。それは、Willametteの普及のペースが従来より早いことも意味する。
Willametteが新人CPUとしては、比較的小さなチップだと推測できるのは、先ほど引用したグラフで0.18μm版Pentium III(Coppermine:カッパーマイン)の消費電力と比較した結果だ。Coppermineは1GHzで27W程度となっている。つまり、クロックあたりの消費電力をWillametteとCoppermineで比較してみると、非常に“熱い”と思えるWillametteも、クロックあたりの消費電力ではCoppermineの1.2倍程度に過ぎない。これは、もし同じクロック(同じ電圧)ならWillametteはPentium IIIの1.2倍程度しか消費電力が高くないということだ。
Coppermineのトランジスタ数は2,800万だから、これを単純に消費電力の比率で1.2倍にするならWillametteは3,400万ということになる。この計算は乱暴すぎるので、数字はまったく参考にならないが、Willametteのトランジスタ数が比較的少ない可能性があるのは確かだ。
Willametteが、意外と“小さい”CPUであることの示唆は、Intelのこれまでの技術説明の中にもある。Intelは、1年前のIDFの技術セッションの中で、新アーキテクチャのプロセッサでは性能が1.5倍になる代わりに消費電力は2倍になると説明していた。これはトランジスタ数が増え、クロックが上昇するためだ。このセオリー通りならWillametteのクロック当たりの消費電力は1.33倍にならないとおかしいはずだ。しかし、Intelの明かした数字では1.2倍に過ぎない。となると、Pentium III→Willametteのトランジスタ数の増加は、これまでのCPU世代交代よりも少ないということになる。
Willametteが比較的小さいという推測は、昨年10月のMicroprocessor Forumでセミナーを行なったアナリストKeith Diefendorff氏(Microprocessor Reportのシニアアナリスト)も述べていた。同氏の推測では、Willametteのダイサイズ(半導体本体の面積)は180平方mm(0.18μm時)と比較的小さいだろうという。
●Willametteは思ったより普及が速い?
もしWillametteが180平方mmかそれ以下なら、0.35μmで製造していた初代Pentium II(klamath:クラマス)の203平方mmより小さい。しかも256KBの2次キャッシュをオンダイ(On-Die)で統合しているわけで、原理的には製造コストはklamathより低くなる。つまり、Pentium II 233/266MHzより生産しやすく普及させやすいことになる。
Intelの新世代CPUは、これまでPentiumもPentium Proも、デビュー時は300平方mmの巨大なチップだった。そのため、最初の1~2年はハイエンドにへばりついていて、2回くらいシュリンクを繰り返してようやく普及レンジに入ってきた。だが、Willametteの場合は、ダイサイズが小さいと推測されるため、それよりずっと早いペースで普及してくる可能性がある。
実際、IDFのキーノートスピーチでIntelのアルバート・ユー上級副社長は「Willametteは、今年の末までに、おそらく数万~数10万個の単位で出荷できるだろう。そして、来年には数100万個の単位で出荷、パフォーマンスデスクトップの主流向けに提供できると考えている」と述べている。Intelの出荷量では、数10万個はほんの数%でハイエンドにへばりつく程度だが、四半期ごとに数100万個単位で出荷できるようになると、普通のユーザーにも手が届く範囲に入ってくる。さらに、2001年の後半にうまく0.13μmプロセスが立ち上がり、「Northwood(ノースウッド)」というコードネームでウワサされている0.13μm版Willametteへと代替わりすれば、一気にローエンドやモバイルの方にまで普及してくるだろう。
●Willametteの普及のアキレス健はDRDRAM
ただし、Willametteの普及にはCPUのコスト以外のハードルがある。CPUの膨大な消費電力に対応した電源や冷却機構、高クロックのFSB(フロントサイドバス)や2チャネルのRambusインターフェイスなどだ。Intelは、そのため今回のIDFでセッションの多くをWillamette時代の筺体や冷却などのソリューションのために割いた。
イニシャルのコストは、ある程度はマザーボードメーカーやPCベンダーの対応が進めばなんとかなるだろうが、Rambus 2チャネルによる6層マザーボードはどうしてもコストがかさむ。そのため、IntelはRambus 2チャネルの最初のチップセット「Tehama(テハマ)」のほかに、Rambusインターフェイスを1チャネルに落とした「Tulloch(タラク)」という普及版チップセットを用意していると言われる。業界関係者によると、IntelはTullochを来年半ばに投入することで、低コストな4層マザーボードでミッドレンジを狙うつもりだという。
もっとも、それでもDRDRAMが今の価格にはりついたままだと、Willametteが本格的にミッドレンジのパフォーマンスデスクトップを狙うのは難しい。Intelが、DRDRAMの普及戦略を堅持し続けている理由はここにあるわけだ。現状では、Willametteの正否はDRDRAMが握っていると言っていい。しかし、Intelにとって重要なのはCPU戦略であってメモリ戦略ではない。そのため、DRDRAMがもしあまりにWillametteの足を引っ張りそうなら、DRDRAM以外のソリューションを持ってくる可能性もあるだろう。
(2000年2月25日)
[Reported by 後藤 弘茂]