 |


■笠原一輝のユビキタス情報局■ダビング10にも対応したバッファローのUSB地デジチューナを試す |
前回の記事では、バッファローのPCIカードの地上デジタル放送チューナ「DT-H50/PCI」のレビュー記事をお届けした。今回は、それに引き続きUSB版となるDT-H30/U2のレビューをお届けしたい。
DT-H30/U2は、基本的にはPCIバス版と同じチップを採用しているため、リアルタイムに低解像度/低ビットレートに変換が可能になっており、モバイルノートPCなどCPUパワーがあまり充分ではないノートPCと組み合わせて利用するのに適している。
また、7月4日から「ダビング10」と呼ばれるHDD上のデータのコピー回数制限の緩和がスタートしたが、DT-H50/PCI、DT-H30/U2なども対応ドライバ/ソフトウェアがリリースされたので、さっそく、その使い勝手などもチェックしていきたい。
●ハードウェアトランスコードにより低いCPUパワーでも動作
 |
| バッファロー「DT-H30/U2」 USB2.0対応の地デジチューナで、PCI版と同じくトランスコード用チップを内蔵する。メーカー希望小売価格は22,050円 |
 |
| DT-H30/U2の内部 |
DT-H30/U2(以下、本製品)とDT-H50/PCIの違いは、PCとの接続バスがDT-H50/PCIがPCI(理論上は133MB/秒)であるのに対して、本製品はUSB(理論上は60MB/秒)となっていること。形状は外付けボックスになっており、内蔵の拡張スロットを持たないノートPCや省スペースデスクトップなどでも利用できる。
また、書き出しできる光学メディアの種類も異なる。DT-H50/PCIがBDへの書き出しにも対応しているのに対して、本製品はDVD-RW/RAM(CPRM対応)への書き出しまでの対応となる。
インターフェイス以外にもノートPCに適している理由はある。本製品はDT-H50/PCIと同じくViXSの「Xcode-2111」がコントローラチップとして採用されており、受信した地デジのデータを解像度やビットレートが低い形式に変換(トランスコード)して格納することができる。
通常の地上デジタル放送は、1,440×1,080ドット/16Mbps前後のMPEG2-TSという高解像度/高ビットレートになっており、これをそのまま再生するには、それなりに強力なCPUが必要になる。デスクトップPCの場合には、マザーボードごと交換して、より強力なCPUに交換することは不可能ではないが、ノートPCの場合にはそれは不可能だし、CPUだけを差し替えることが可能な場合でも、放熱の余裕がないため実際にはできないことの方が多い。
これについて、本製品ではCPUではなく、Xcode-2111に内蔵されている専用エンジンを利用して変換を行なうので、トランスコードによるCPUへの負荷はわずかで、CPUは再生など他の作業にまるまる利用することができるのだ。
| 解像度 | ビットレート | 動作CPUスペック | |
|---|---|---|---|
| DP | 1,440×1,080ドット | 最大16.8Mbps | Pentium D 925 3.0GHz同等以上 |
| HP | 720×1,080ドット | 8Mbps | Pentium D 925 3.0GHz同等以上 |
| SP | 720×480ドット | 6Mbps | Celeron D 330 2.66GHz同等以上 |
| LP | 720×480ドット | 4Mbps | Celeron D 330 2.66GHz同等以上 |
| LLP | 352×480ドット | 2Mbps | PentiumM 1.1GHz同等以上 |
前回の記事でも説明したように、本製品での録画にはDP/HP/SP/LPの4つのモードが用意されているが、バッファローが7月8日に公開した最新のドライバソフトウェア(Ver 1.10)では、LLPというモードが追加されており、解像度が352×480ドット、ビットレートが約2Mbpsで録画できる。
●Core Solo U1400ではSP以下のモード視聴可能
それでは、あまり処理能力があまり高くないCPUを搭載したノートPCを利用して、各動作モードでのCPU負荷率がどの程度になるのかを計測していきたい。テストに利用したのは、富士通の「LOOX Q(FMVLY7TN13)」という12型ワイド液晶を搭載した製品で、CPUにはCore Solo U1400(1.20GHz)という超低電圧版のシングルコアCPUを搭載している(DT-H30/U2の各視聴・録画モードにおける動作CPUスペックは表1に示した通り)。
この環境において各モードでライブ表示させた時には、以下のようなおおむねCPU負荷率になった。
| CPU負荷率 | |
|---|---|
| DP | ほぼ100% |
| HP | 90~100% |
| SP | 80~90%台後半 |
| LP | 60%前後 |
| LLP | 50%前後 |
正直なところ、DPでは頻繁に、HPでは時々、CPU負荷率が100%になってしまい、コマ落ちが発生する。観ることができないという訳ではないが、快適とは言い難いのも事実だ。しかし、SPでは80~90%台後半、LPでは60%前後、LLPでは50%前後というCPU負荷率になっており、SPではほかにアプリケーションを動作させなければ十分に、LPとLLPでは地デジソフトとそれ以外のアプリケーションを組み合わせても十分利用できることが分かった。
ただし、ノートPCで利用する場合には、HDD容量が問題になる可能性がある。特に、CPUがあまり強力ではないモバイルノートPCは、HDDが1.8インチで、容量が40GBや60GBなどのものが多い。そうした場合には、USB HDDなどを利用して録画するといいだろう。本製品では、HDD保存先は3カ所まで指定できるので、内蔵HDDだけでなく外付けHDDも利用できるので使いこなしの幅が広がる。
 |
 |
| LOOX QでDT-H30/U2を利用しているところ | LOOX Qにバッファローの1TB USB HDD「HD-HES1.0TU2」を接続して利用しているところ |
●MacintoshのBoot Camp環境でも動作可能
 |
| Boot Campを使うとiMac(Core 2 Duo 1.8GHzを搭載)でもDT-H30/U2を使用できる |
次に、ちょっと変わった使い方を紹介しよう。本製品はインターフェイスがUSBであり、Windows XP Service Pack 2以降、あるいはWindows Vista Service Pack 1に対応している。アップルのMacintoshシリーズには本来対応していないのだが、MacintoshでWindowsを動かすBoot Campを利用することで使えるようになる。今回は、手元にあったiMacに本製品をインストールしてみたが、何の問題もなく利用できた。
利用手順は通常のBoot Campを利用する場合と何ら替わりはない。ソフトウェアアップデートをかけて、Mac OS X 10.5を最新版にした後で、Boot Campを導入し、Windowsをインストール。その後はWindows OS環境で利用するのと全く同じ手順だ。動いて当たり前とも言えるが、現時点ではMac OS上で利用できる地上デジタル放送用のチューナカードはない。Windowsに切り替えるという条件はつくが、検討してみる価値はあるだろう。
●7月4日公開のアップデータでダビング10に対応
最後に、7月4日から開始された新しいダビング10に関して触れておこう。以前より本連載で触れてきたとおり、地上デジタル放送はHDDに格納したデータを一度だけ移動(ムーブ)できる「コピーワンス」と呼ばれる仕組みを実装することを受信機器に義務づける仕組みになっている。
このコピーワンスでは、ムーブすると同時にHDDに残ったデータは完全に消去することが求められているため、ムーブに失敗すると録画したデータが消えてしまうなどの問題点が早くから指摘されており、地上デジタル放送普及の足かせになってしまっていた。そこで、家電メーカーや放送業界、権利者団体などが話し合い、そのルールを緩和し、1世代に限り9回までのコピーと1回ムーブを可能にする新しいルールが策定された。ダビング10と呼ばれるのは、合計で10回のコピー(一度はムーブだが)できるからだ。
DT-H30/U2、および前回紹介したDT-H50/PCIもダビング10への対応が7月4日より開始されている。バッファローのWebサイトに用意されている最新のドライバソフトウェアをインストールすると、ダビング10に対応した番組を録画した場合に、従来は「1回ディスク作成可」となっていたところが、「10回ディスク作成可」と表示されるようになり、光学ディスクにコピーするたびに1回ずつ数字が減っていく仕組みになった。ちなみに筆者は7月4日公開のドライバVer 1.10β5にてテストしたが、7月8日には正式版のVer 1.11が公開されている。
 |
 |
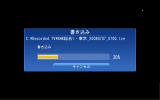 |
| 録画ファイルのリストを表示しているところ。ダビング10で録画された番組は「10回ディスク作成可」と表示される | 録画情報の詳細、ダビング10に対応した番組ではコピー制限がダビング10と表示される | BDにムーブしているところ |
 |
| DT-H50/PCIと組み合わせてBDへのムーブに利用したバッファローの外付けBDドライブ「BR-616U2」。メーカー希望小売価格は44,415円 |
なお、すでにコピーワンスの状態で録画した番組はバージョンアップしても、従来と同じようにコピーワンスで一度しかムーブできない。
従来であれば、一度光学メディアに書き出すとそれで終わりだったのに対して、1世代のコピーが10回可能になったのは進歩と言える。次は、編集がテーマとなるだろう。
従来のようにローカルにコピーデータを持つこともできなかったコピーワンスに比べて、ダビング10になることで複数のコピーを持つことが可能になるため、今後は編集ができるようになる道もでてくるのではないだろうか。特に本製品やDT-H50/PCIはハードウェアトランスコードチップを備えているだけに、そうした機能を実装するのも他製品に比べれば容易であると考えられるだけに、そうしたソフトウェアの提供を期待したいところだ。
このほかにも、ホームネットワークへの配信なども、DTCP-IP技術などを利用すれば可能になるだろう。今後も継続した機能追加/改良に期待したい。
□関連記事
【6月30日】【笠原】バッファロー DT-H50/PCIレビュー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0630/ubiq220.htm
【4月21日】バッファロー、ムーブ対応地デジチューナを正式発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0421/buffalo.htm
【4月18日】バッファロー、DVDムーブ対応PCI内蔵とUSB外付けの地デジチューナ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0418/buffalo.htm
【7月3日】「ダビング10」開始目前。注意点を再チェック(AV)
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080703/dub10.htm
【2月28日】「ダビング10」とは何か。デジタル録画緩和策の実際(AV)
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080228/dub10.htm
(2008年7月10日)
[Reported by 笠原一輝]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.