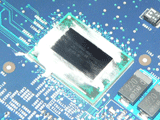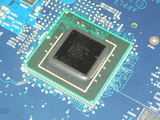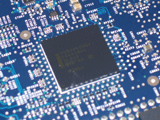|


■笠原一輝のユビキタス情報局■Apple TVハードウェアレポート |
 |
| Apple TV |
前回は、発売されたばかりのApple TVについてのレビューをお伝えしたが、今回はそのApple TVを分解して、わかったことをお伝えしていきたい。Apple TVを分解してみると、CPUなどは実に興味深いものが採用されていることがわかってきた。
本記事では、そうしたApple TVの内部構造や、“Intel Processor”と公表されていなかったCPUの謎などについて考えていきたい。
■■ 注意 ■■・分解/改造を行なった場合、メーカーの保証は受けられなくなります。 |
●トルクスネジでとめられていることをのぞけば簡単に分解できるApple TV
Apple TV(以下、本製品)の分解だが、ちょっとしたコツがわかってしまえば割と簡単に分解することができる。ただし、分解するとアップルの保証は受けられなくなってしまうので、元に戻せなかったらもう使わないという覚悟が必要になる。なお、分解した結果、動かなくなったとしても本誌も筆者も責任はとれないので、決して真似しないでいただきたい。
まずは、底面の蓋に貼られているゴムの蓋を強引にはがす。この蓋は両面テープで固定されているので、はがすと写真のようにテープが残ってしまって汚らしくなってしまうので、表面にゴミなどがつかないように注意したい。
次に底面の四隅にあるネジをはずす。このネジは一般的なプラス、マイナスのネジではなくトルクスネジと呼ばれる特殊な形状のネジになっており、注意が必要だ。トルクスネジ用のドライバを利用すれば、割と簡単に取り外すことができる。次に、見えるケーブルをコネクタから1つ1つ外していくが、この時注意したいのは無線LANのアンテナだ。
本製品では本体が無線LANのアンテナを兼ねており、無線LANモジュールから出ているアンテナケーブルは絶縁テープを利用して本体に固定されている。このため、アンテナは無線LANとの接続部分を外すようにして、本体に固定されているアンテナそのものを外さないようにしよう。その後、電源供給ユニットを固定している3本のネジ、無線LANモジュールのネジ(1本)、基板を固定している2本のネジを外すと基板が見えてくる。
 |
 |
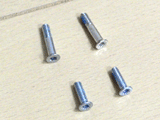 |
| ゴムの蓋をはがしたところ。両面テープでついているので、気合いではがす。シールが残ってちょっと汚い感じになってしまうが、そこは目をつぶって…… | 底面の裏蓋を外したところ。4本のトルクスネジで固定されていた | これがトルクスネジ |
 |
 |
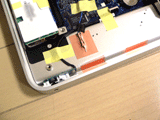 |
| 裏蓋にはHDDが固定されている。IDEのフレキシブルケーブルを外す | 裏蓋を外した状態。中央に見えるファンは、システム全体を冷やすためのもので、ヒートシンクなどは用意されていない。CPUやGPUなどはケースに接地しており、ケース全体をこのファンで冷やしている | 無線LANのアンテナ部分。本体のケースをアンテナとして利用している |
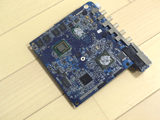 |
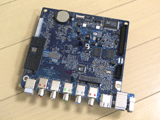 |
| マザーボードの裏面。CPUやGPUなどが集中している | マザーボードの表面。ビデオメモリやEthernetコントローラなどが実装されている |
●光学ドライブがないだけのフルPCアーキテクチャとなっているApple TV
それでは、基板に搭載されているコンポーネントを確認していこう。CPUはスペック通り、IntelのCPU、チップセットはIntel 945G Express+ICH7が搭載されている。これらのIntelのコンポーネントに関しては後述したい。
メインメモリはMicronの7AD22-D9GKWというチップが採用されている。このチップの情報はMicronのサイトにも掲載されていなかったのだが、他のD9GKWという型番のチップがいずれもDDR2-533だったので、おそらくDDR2-533である可能性が高い。チップ自体の容量がわからなかったので、メインメモリの容量に関してはわからないが、DDR2-533であれば256Mbitないしは512Mbitのいずれかである可能性が高いので、128MBか256MBあたりではないだろうか。
チップセットのIntel 945GはGPUを内蔵しているが、本製品ではこの内蔵GPUは利用されておらず、NVIDIAのGeForce Go 7300が搭載されており、こちらが画面描画として採用されている。GeForce Go 7300用のビデオメモリとして、Qimonda HYB18H256321AFL14が2つ搭載されている。Qimonda HYB18H256321AFL14は256Mbit/x32のGDDR3メモリで700~500MHzで動作する。256Mbit/x32のチップが2つなので、メモリ容量は64MB、バス幅は64bit幅となる。
HDMI出力にはSiliconImageの外部トランスミッタが利用されている。NVIDIAのG7x世代はHDCPの暗号化鍵をチップ内部に持ってはいるが、実際はオーディオのことも考えてSiliconImageの外部トランスミッタが採用されることが多い。本製品でも同じような理由で外部トランスミッタが採用されたと考えられるだろう。
オーディオコントローラにはRealtekのALC885というHDオーディオCODECが利用されている。ALC885は7.1ch出力が可能なHDオーディオCODECで、デスクトップPC用マザーボードなどでもよく利用されている。EthernetコントローラもRealtek製でRTL8100Cを搭載している。このほか、BIOS ROM用にSST 89V54RD2も搭載されている。
これらの情報を元に、本製品をブロック図を起こしてみると、図1のようになる。こうして見ると、光学ドライブがないだけで完全なPCアーキテクチャであることがわかるだろう。
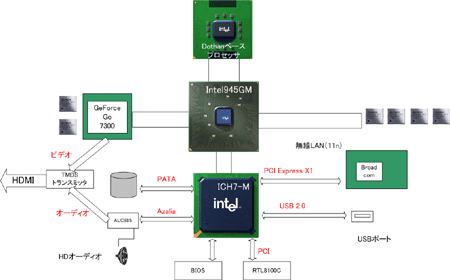 |
| 【図1】Apple TVの推定ブロック図 |
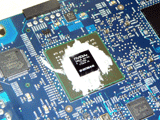 |
 |
| GPUのGeForce Go 7300。64MBのビデオメモリを64bit接続している。左に見えるSiliconImageのTMDSトランスミッタでオーディオからの入力をマージしてHDMI出力を実現している | EthernetコントローラはRealtekのRTL8100C |
 |
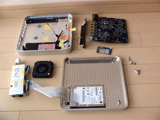 |
| 富士通のMHW2040ATは2.5インチ/40GB/4,200rpmのHDD | Apple TVの全部品 |
●LPIAプラットフォームのために用意された新パッケージの製品が利用されている
本製品に搭載されるプロセッサは、外見からではどのプロセッサかは正直わからない。しかし、ヒートスプレッダが用意されていないなどの特徴から、おそらくはモバイル向けのプロセッサであると推測できる。かつ、最大のヒントはパッケージがこれまでIntelのプロセッサでは見たことがない、非常に小さなものが採用されているということだ。
本製品に採用されているプロセッサのパッケージは14.5×19mm(幅×奥行き)と、一般的なモバイル向けのプロセッサの35×35mm(同)に比べて圧倒的に小さくなっている。実装面積で言えば275.5平方mmと、従来の1,225平方mmの4分の1以下となっているのだ。
おそらく勘のよい読者はこの“4分の1”で、もうわかったのではないかと思うが、Intelがすでに発表している“従来の製品よりも4分の1の実装面積になる製品”といえば、例のLPIA(Low Power Intel Architecture)向けの熱設計消費電力が3W以下になるプロセッサ(製品名は未発表)だと容易に推測できる。以前の記事で、このTDP3WのLPIAプロセッサの正体は、L2キャッシュが512KBに制限されたDothanコアであるとお伝えしたが、まさにこれではないかと推測できるのだ。そのもう1つの証明として、ダイサイズを計測してみると12.5×7mm(同)で87.5平方mmと、こちらもDothanのダイサイズ(87平方mm)とほぼ一致する。こうしたことからも、DothanコアベースのLPIAプロセッサであると考えてほぼ間違いないのではないかと思われる。
もう1つユニークなのは、チップセットのパッケージだ。今回採用されているチップセットは、「82945GUXL」と書かれたIntel 945Gベースと思われるノースブリッジと、「82801GUX」と書かれたICH7ベースと思われるサウスブリッジが採用されている。しかし、一般的なIntel 945GやIntel 945GMのパッケージが37.5×37.5mm(同)というサイズであるのに対して、この82945GUXLとかかれた945Gは22×22mm(同)となっており、サブノート向けのIntel 945GMS(27×27mm)よりもさらに小さくなっている。
| 通常パッケージ | 37.5×37.5mm | 1406.25平方mm |
| Intel 945GMS | 27×27mm | 729平方mm |
| 945GUXL | 22×22mm | 484平方mm |
実装面積で比べると、通常パッケージ版に比べて約3分の1になっている。
さらにサウスブリッジに関しても小型化されており、通常パッケージが通常のICH7が一般的なBGAパッケージであるのに対して、本製品のICH7はダイだけを直接実装したような、新型パッケージになっている。通常のパッケージが31×31mm(同)であるのに対して、本製品のICH7は15×15mm(同)で、実装面積はやはり4分の1以下となっている。
これら3つの新パッケージを従来の製品と比較してみると、図2のようになる。このように圧倒的に実装面積が小さくなっており、マザーボードの小型化、ひいては低コスト化に大きな貢献を果たしていると考えることができる。パッケージが小さくなると、配線の取り回しが難しくなってくるのだが、本製品の場合はメモリも128~256MBとサイズの小さく、その分の実装面積も少なくすんでいるし、外部I/OがHDMIとコンポーネント出力、オーディオ、Ethernet程度であるのでさほど実装は難しくないだろう。
こうした新しいパッケージが本製品のためだけに用意されるということは、製造コストの面からも考えにくく、おそらくこれはLPIAのために用意されたものが、本製品に使われている、そう考えることができるのではないだろうか。
本製品とは直接関係ないが、仮にこれが筆者の推定通りLPIA用の新パッケージであるとすれば、今後これをUMPCなどに使っていけば、かなり小さな基板を製造することが可能になりそうだ。VAIO type Uのような製品は、この図2で言うところの旧パッケージで作られているので、それを新パッケージにすれば実に4分の1近くに実装面積を抑えることができる。この点は大きなメリットといえ、そうした製品の登場を期待したいところだ。
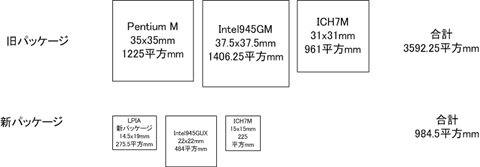 |
| 【図2】従来のパッケージと新パッケージの比較 |
●採用されているコンポーネントの原価を考えるとお買い得な価格設定
このように、本製品に採用されたコンポーネントを元に、本製品のコストモデルを計算してみると、おもしろいことがわかる。
表1は、筆者が予想した各コンポーネントの価格だ。基本的にはコンポーネントベンダがOEMに提供する価格を元に算出しているが、一般的なOEMへの提供価格なので、アップルのような大手ベンダの場合にはこれより安価に入手している場合もあるが、さほど大きく外れることはないと考えられる。CPUとチップセットに関しては、CPUが超低電圧版Celeron Mの価格で、チップセットに関してはIntel 945GMSの価格を採用することとした。今のところLPIAプロセッサやそのチップセットの価格に関しては伝わってきていないので、参考としてこれらの価格を採用することにした。
結果は見てわかるように、コンポーネントの入手原価(業界的にはBOM、Bill Of Materialと呼ばれる)だけでも425ドル(日本円で5万円前後)に達していることがわかる。実際は、この価格にさらに組み立て費用(数十ドル前後)に輸送費などがかかるため、実際の製造原価はもっとかかっている可能性もある。
冷静に考えてみれば、本製品の構成はほとんど光学ドライブがないMac miniと言い換えてもよい。もちろんCPU、メモリやHDDの容量などは異なるため直接比較はできないが、それでもMac Miniの価格、74,800円から3万円近く値段が下がっているとは考えにくく、前出のBOMの計算でも成り立たない可能性が高いことはわかっていただけるのではないだろうか。
それなのに、36,800円という値段設定がされている背景には2つの理由が考えられる。1つには、実際アップルが入手しているコンポーネントの原価が、一般的なOEM価格よりもさらに安いという可能性だ。BOMの表をよく見ていただけば、価格の大部分はIntelが占めていることがわかる。従って、実はIntelのLPIAプロセッサとそのチップセットが、現行のCeleron M+チップセットよりも安価に設定される可能性が考えれる。特に、大手OEMの場合、CPUベンダからのキックバックも含めて値段設定をしているため、一般に考えられているよりも安価に入手できている可能性はある。
しかし、おそらくそれだけではなく、アップルとしてもこの製品を戦略的に考えており、それゆえに戦略的な値段設定をしていると考えることはできるのではないだろうか。本製品のレビュー記事でも指摘したように、本製品の最大の特徴は、iTunes Storeで購入できるHDコンテンツと組み合わせて利用することにことにある。つまり、アップルとしては、ユーザーがコンテンツを購入してくれることにこそ最大の目的があり、別にハードウェアでもうける必要はないと考えているとも推測できる。つまりハードウェアは赤字かぎりぎり黒字でも、コンテンツを販売することで利益を出す、そうしたビジネスモデルを想定していると考えるのが自然だろう。
いずれにせよ、BOMコストから考えると、明らかに本製品はユーザーにとってお買い得な製品であるということはできるのではないだろうか。
| CPU | Celeron M ULV | 161 |
|---|---|---|
| チップセット | Intel 945GMS | 39 |
| GPU+VRAM | GeForce Go 7300(64MB) | 30 |
| メインメモリ | 256MB(4チップ) | 10 |
| HDMIトランスミッタ | SiliconImage | 5 |
| HDD | 富士通 | 40 |
| イーサネットコントローラ | Realtek | 5 |
| オーディオコーデック | Realtek | 5 |
| 基板製造 | アップル | 20 |
| ケース | アップル | 30 |
| リモコン | アップル | 10 |
| 電源供給ユニット | Delta | 30 |
| 無線LANモジュール | Atheros | 30 |
| コネクタ | HDMI端子など | 10 |
| 合計 | 425 | |
□関連記事
【3月29日】【笠原】リビングで使う“据え置き型iPod”「Apple TV」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0329/ubiq182.htm
【3月23日】【新製品レビュー】iTunesのビデオ/音楽をテレビで(AV)
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070323/np004.htm
【3月22日】アップル、メディアプレーヤー「Apple TV」を出荷開始(AV)
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070322/apple1.htm
【1月10日】アップル、HDMI/40GB HDD搭載のメディアプレーヤー「Apple TV」(AV)
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070110/apple1.htm
(2007年4月2日)
[Reported by 笠原一輝]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.