 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■ハンドヘルドXboxはMicrosoftの“iPodキラー”になる |
●のど元まで出かかったハンドヘルドXbox
今年のゲーム関連ショウ「E3(Electronic Entertainment Expo)」での、Microsoftの話題は、言うまでもなく携帯ゲーム機だった。Microsoftがハンドヘルドゲーム機のプロジェクトを2005年秋からスタートさせている、少なくとも検討していることは、業界の公然の秘密状態となっている。ニュースでも、Microsoftがハンドヘルド版Xboxを開発していることは、3月から流れていた。そのため、3月のゲーム開発者向けカンファレンス「GDC(Game Developers Conference)」の時点では、E3で携帯機への参入表明がされるのではとウワサされていた。あるMicrosoft関係者は、GDCで何らかのアクションがあるだろうと言っていた。そうなれば、携帯機でも三つ巴の戦いになるわけで、ふくらみつつある携帯ゲーム市場がますますブーストする。
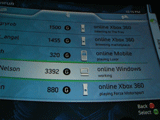 |
| Live Anywhereの例 |
実際、今回のE3のブリーフィングで、Microsoftはあと一歩でハンドヘルドXboxまで言及しそうだった。実際にはアナウンスされなかったわけだが、のど元まで出かかったのを飲み込んだような雰囲気だ。というのは、Microsoftが「Live Anywhere」構想を発表したからだ。Live Anywhereは、Xbox、Windows PC、ポータブルデバイスの間で、シームレスなネットワークゲームプラットフォームを構築するという構想だ。
簡単に言えば、Live Anywhereでは、MicrosoftがXboxのネットワークサービス「Xbox Live」で提供しているコミュニケーションサービスを、Windows PCや携帯デバイスからも利用できるようにする。また、同じネットワークゲームを、各ハードからシームレスにプレイすることも可能にする。タイトルによるが、例えば、MMORPG(Massively Multiplayer Online Role Playing Game)だったら、自宅ではXboxでプレイし、外出先では携帯機でプレイし、会社ではこっそりPCでプレイするといったことが可能になる。もちろん、同じプレーヤーキャラで。
この構想自体は、MicrosoftでXboxプラットフォームを担当してきたJ Allard氏(Corporate Vice President, Chief XNA Architect)が以前から語っている。2004年3月のインタビューでは次のように答えていた。
「Xbox Liveが重要なのは、ブリッジになることだ。今のXbox、次のXbox、今のWindows、次のWindows、これらの連結体(nexus)になる。ゲームクリエイタは、異なるプラットフォームの間で共有される世界の構築を考えることができる。Windows PCやゲーム機やモバイルデバイスのどれからでも、アクセスして触れることができる世界を作ることができる」
今回は、この構想に正式に名前がつけられ、具体的にスタートさせることがアナウンスされたわけだ。そして、その目的の1つは、ハンドヘルドXboxにあることは、まず間違いがない。Live Anywhereは、MicrosoftがハンドヘルドXboxを出した時にシームレスにつなげるためのブリッジになると見られる。
●意図が不明瞭なゲイツ氏の登場
 |
| E3に登場したビル・ゲイツ氏 |
今回のMicrosoftのE3ブリーフィングでは、直前になってBill Gates(ビル・ゲイツ)会長兼CSAが登壇することがわかった。それもハンドヘルドXboxへの期待をふくらませた。
前回、ゲイツ氏がゲーム系のショウ&カンファレンスで引っ張り出されたのは、ゲーム機参入を正式に発表したGDCだった。それくらい大きな節目の舞台でなければ、Microsoftの象徴はさすがに引っ張り出さないのが通例だ。そのため、当然、今回も、ゲイツ氏が何らかの大きなアナウンスを行なうと期待された。だから、Live Anywhereの話に続いてゲイツ氏が登場した時は、当然、ゲイツ氏の次の言葉は、Live AnywhereにつながるデバイスをMicrosoftが提供するという宣言だろうと予想した。ところが、ゲイツ氏はLive Anywhereをなぞるだけで終わってしまった。完全に不発で、肩すかしを食った格好だ。
もっとも、ゲイツ氏のスピーチは出だしの様子からも、今回はあまり大きな話は出てこない気配が漂っていた。
ゲイツ氏のスピーチには2パターンある。1つはほほえみながら、視線を聴衆に据えて、ゆったりとした口調で身振りを交えてしゃべる“オフィシャルモード”。もう1つは、あまり笑みを浮かべず、そわそわしながら、早口でまくしたてる“ネイティブモード”。前モードは、大きなカンファレンスや重大発表イベントなどでよく見られる。おそらく、下準備を重ねた時のモードだと推測される。後モードは、デベロッパ向けのカンファレンスや普通の発表会などでよく見られる。わりと、ぶっつけ本番的な時に出てくる、“地”のモードだと推測される。
E3の時のゲイツ氏はというと、後者のモードに近く、手に持った小さなタグを神経質にもてあそびながら、しゃべっていた。このあたりからも、ゲイツ氏が簡単に引っ込む気配はあった。
●Microsoftにとって必然的な携帯ゲーム機への進出
しかし、論理的に考えれば、Microsoftが携帯ゲーム機というか、複合型エンターテイメント端末に進出するのは必然だ。
Microsoftにとって携帯エンターテイメント端末は見過ごせる市場ではないからだ。iPodはすでに累計出荷が2006年1月で4,200万台で、現在は5,000万台を突破していると見られており、しかも、成長が衰えていない。この手のデバイスは、そのうちPCに台数で迫る可能性があり、一部では携帯電話とも融合して行く。化ければ、年間に億の単位のデバイスが出るようになる可能性があるわけだ。さらに、ハードとソフトだけでなく、サービスでも利益が見込めるため、ビジネスモデルとしてもおいしい。
Microsoftという企業を少しでも知っていれば、この会社が、こんな状況を見過ごすことはあり得ないとすぐにわかる。Microsoftは、一種のパラノイア企業で、自分の回りの情報機器市場で他社が覇権を取ると、自社への脅威と認識して、必ず対抗する。
つまり、Microsoftの覇権戦略としては「iPodキラー」を必ず持たなければならない状況にある。そして、Microsoftが対iPodで仕掛けるには、Appleが出遅れている部分から浸食するのが一番だ。となると、ゲームとビデオをテコに攻略するのが近道となる。最短コースにあるのは、Xboxのチームのパワーを活かすことだ。
また、iPodだけでなく、SCEIのPSPもMicrosoftにとっては嫌な存在だ。ニンテンドーDSに押されている日本市場はともかく、PSPは米国やヨーロッパではそれなりの成功を収めている。米国では、従来、成人はあまり携帯ゲーム機に手を出さなかったのが、PSPで状況が変わった。また、ゲーム、ビデオ、音楽という、PSPのカバーエリアはおそらくMicrosoftの構想とオーバーラップする。
しかも、Microsoftにとってさらに見過ごせないことに、PSP上で走る自作プログラムが、1つのブームになりつつある。PCも、ホビーとしてのプログラミングからスタートし、ここまで成長したわけで、Microsoftにとって、PSPがプログラミングのプラットフォームとして、いくらかでも支持されるのは嫌な予兆だ。
そもそも、携帯端末の制覇は、Microsoftにとって長年の宿願でもある。ゲイツ氏は、'95年に、著書「ビル・ゲイツ未来を語る(The Road Ahead)」を出版した時に、「Information at Your Fingertips」を唱え、「Wallet PC(サイフPC)」の構想を大きく掲げた。それ以来、Microsoftは携帯端末に何度もトライして来たが、メガヒットはまだ放つことができていない。その壁を、AppleがiPodで破ってしまったのだから、Microsoftは焦って当然だ。そして、iPodの成功を見て、テコになるのは、エンターテイメントだと気がついたと推測される。
●Xboyから紆余曲折でたどり着いたハンドヘルド機
Microsoftはいつからこの構想を持っていたのだろう。
よく知られているように、MicrosoftはXboxで参入時に、「Xboy」と呼ばれる携帯ゲーム機プランも検討をした。だが、ハードや市場などの条件が揃わないため、企画段階で取りやめたと言われる。おそらく、Microsoftが携帯ゲーム機を再考し始めたのは、それほど遠い時点ではない。
例えば、2004年3月のインタビューでは、Allard氏は、XNA(Microsoftのゲーム開発プログラミングフレームワーク)でモバイルデバイスもカバーするか、という質問に対して、次のように答えている。
「正直な話、モバイルコンポーネントが十分に統合され、モバイル機器でゲーム体験をユーザーができるようになるには時間がかかる。でも我々は近づきつつある」
あるMicrosoft関係者によると、Xboxチーム内では、少なくとも1年半ほど前はハンドヘルド機は、構想に上がっていなかったという。日本側からハンドヘルドという提案も出されたが、本社側では関心を示した様子がなかったと伝えられる。ところが、2005年3月のGDCでは、Allard氏がディナーの席で、“自分だったらPSPはこう作る”構想を熱を込めて語った。この時点では、プラットフォーム開発の責任者であるAllard氏は、少なくともかなり形になった構想を持っていた。そのため、Xbox 360のローンチ前から、それなりの下地はすでにできていたと推測される。
米国の著名なテクノロジージャーナリストDean Takahashi氏の新著『The Xbox 360 Uncloaked The Real Story Behind Microsoft's Next-Generation Video Game Console』(SpiderWorks, LLC)では、Microsoftがハンドヘルド機のプランに至った経緯が書かれている。
Takahashi氏が触れているのは、Xbox 360が完成したことでハードウェアエンジニア達が空いたこと、昨年9月のMicrosoftの社内組織統合によって、Xbox部門がモバイルと組み込み系の部門と統合され、Microsoft Entertainment & Devices Divisionへ生まれ変わったこと。組織統合の結果、Xbox部門のトップ達は、新たにモバイル&組み込み系プラットフォームも担当することになったという。
●E3でアナウンスしなかった意図は
2005年秋からプロジェクトがスタートしたとすれば、3月のGDC時点で社内スタッフがモックアップを見たことがなくても不思議ではない。E3時点でカタチにするのが間に合わなかったというのも十分考えられる。しかし、それ以上にありそうなのは、来週のMicrosoftのハードウェア開発者向けカンファレンス「WinHEC」で発表するというシナリオだ。例えば、直前になってE3アナウンスからWinHECアナウンスに変更があったとすれば、ゲイツ氏のE3への登場が、今一つしっくり来なかった理由もわかる。
もし、MicrosoftがハンドヘルドXboxをゲームショウであるE3ではなく、ハードウェアカンファレンスであるWinHECにわざわざ持って行くとすれば、そこには理由があるはずだ。想定できるのは、Microsoftが新しい携帯デバイスでは、ゲーム機ではなく、多目的エンターテイメントデバイスとしての性格を強調するということだ。だとすれば、ゲームイベントは避けようという話になってもおかしくない。その場合は、この携帯機は、“Xboxをハンドヘルドにしてビデオや音楽機能を加えた機器”ではなく、“ビデオや音楽が楽しめて、プラスゲームもできる機器”と位置付けられることになる。
言葉のアヤのように聞こえるかも知れないが、これはビジネスモデルにも関わる重要な意味を持っている。ゲーム機として訴求する場合には、ロイヤリティやゲームタイトルの上がりなどの収入をある程度あてにできる。そのため、ハードウェアの利幅はギリギリか、初代Xboxのように完全にマイナスに見込むこともできる。
しかし、ユーザーの自前の録画ビデオの再生やCDからの音楽取り込みのような使い方が主流になると想定すると、そうしたモデルが成り立たなくなる。だから、iPodの60GBモデルの方が、Xbox 360通常版よりも高価格で売られるわけだ。逆を言えば、ゲーム機としての性格を強く打ち出し、ゲーム機価格で出すなら、その他の使い方はある程度制限しなければならない。Xbox 360に、TV録画機能を持たせたモデルを作らないといったように。
このように推測して行くと、Microsoftがプランを変更した可能性も出てくる。例えば、Xbox系のように、自社でハードウェアを提供するモデルは取らないかもしれない。
だが、いずれにせよ、Microsoftが携帯エンターテイメントデバイスについて、何らかのアクションを用意していることだけは確実だ。Microsoftは、そうしなければならない状況にある。
●TransmetaとMicrosoftが提携
では、Microsoftの多目的エンターテイメント携帯機器は、どのような姿になるのだろう。
まず、CPUについては、Transmetaが最短距離にいる。既存のXboxタイトルを、最小限の変更で走らせるには、超低消費電力のx86 CPUが必要だからだ。Dean Takahashi氏は、The Xbox 360 Uncloakedの中で、ハンドヘルドXboxプランについて、MicrosoftがTransmetaと契約を結んだことに言及している。これは、大原雄介氏のレポートにもある通りだ。
Transmetaのハードウェア設計部門は、水面下で新CPUの設計を進めており、今週開催された「Spring Processor Forum(SPF)」でその概要を発表している。Transmetaの発表内容は、大原氏のレポートの通り、700MHz動作時の消費電力スペックをわざわざフィーチャしたプレゼンテーションで、かなり意味深だ。初代XboxはPentium III 733MHzなので、Efficeon 700MHzならいい勝負となる。Transmetaの消費電力は700MHz時に1Wを切る。
 |
| Transmetaの新CPUの資料 (別ウィンドウで開きます) PDF版はこちら |
 |
| LongRun2搭載Efficion (別ウィンドウで開きます) PDF版はこちら |
Microsoftがソフト移植の労力を最小限にするためにx86 CPUにこだわるとしたら、ほかに有力なアテがない以上、Transmetaという選択は論理的だ。そして、Microsoftは、今回は初代Xboxの時と同様に、リリースまでの時間が限られており、急いでいる。出遅れたら、AppleとSCEIに決定的な差をつけられる可能性があるからだ。ソフトウェアのためにx86を選ぶモチベーションはある。もっとも、Xbox 360の時と同様、フタを明けたらRISC CPUだったという可能性もある。
GPUについても、DirectXというインフラと、シェーダの継承性を考えると、ある程度限られてくる。Microsoftは初代Xboxでコスト削減ができずに苦しんだ。その主原因の1つは、自社のIPを堅固に守るNVIDIAとの戦いで、そのため、Xbox 360からはチップ製造の主導権を自社に持つようにした。IPを渡してくれるATI Technologiesをパートナーに選んだ理由の1つはそれだ。
Microsoftが、ハンドヘルド機でも同じことを考えているとすれば、パートナーの幅は狭まる。また、トランジスタ数が限られる携帯機器向けGPUの場合は、Programmable Shaderを、3Dグラフィックス以外に、ビデオなど多目的に転用できることが求められる。つまり、そうしたノウハウを持つ企業や部門をパートナーとする必要がある。
もし、MicrosoftがATIを再びパートナーに選ぶなら、携帯機器向けGPU「Imageon」を擁する、同社のコンシューマ部門Consumer Business Unitが最有力候補になるだろう。コンシューマ部門は、ATIの重鎮Adrian Hartog氏(Chief Technology Officer & Senior Vice President & General Manager, Consumer Business Unit)が統括しており、Hartog氏は携帯機器でのゲームに、意欲を燃やしていた。ちなみに、ATIはE3直前に、携帯機器向けGPUの有力ベンチャーであるBitboysを買収している。
Microsoftがどのような選択を取るにせよ、それは、遠からず明らかにされるだろう。
□関連記事
【5月19日】【SPF】復活したEfficeonはXboxポータブルに搭載か
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0519/spf04.htm
【3月24日】【海外】Microsoftのポータブル版Xbox計画浮上
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0324/kaigai256.htm
【2004年4月1日】【海外】見えてきたMicrosoftの次世代Xbox戦略(2)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0401/kaigai080.htm
(2006年5月20日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.