 |
|


■元麻布春男の週刊PCホットライン■Intelプラットフォームのキーワードは「仮想マシン」 |
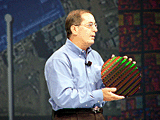 |
| 90nmプロセスにより製造されたウェハを紹介するオッテリーニ社長。今回のIDFでは穏やかな表情が目立つ |
9月16日から3日間のスケジュールで、2003年秋のIDFがスタートした。今回のテーマもここ数回のIDFと同じ「技術の融合(Converging Technologies)」で、冒頭を飾ったポール・オッテリーニ社長のキーノートもここから始まった。
現在世界では、15億台のブロードバンドPCと25億台の携帯電話が普及する2010年に向けて、これらのデバイスが急速に広まり続けている。すべてのPCが通信機能、特にブロードバンドに対応した通信機能を備えつつあるように、携帯電話も計算能力を備えつつある。
2010年の携帯電話の計算能力は、現在のPentium 4に匹敵するものになると予想されており、PCと携帯、両者の用途のクロスオーバーや両者の相互接続性は不可避なものになりつつある。現時点でIntelは携帯の世界ではメジャープレイヤーではないが、継続的に製品をリリースしており、虎視眈々とチャンスをうかがっているようだ。携帯により多くの処理能力が求められれば求められるほど、自分たちの出番が近づく、という意識は強いハズだ。
●クライアントPCでも、HyperThreadingの次はマルチコア
 |
| GHzだけでないプロセッサ(GHz & More)の鍵は4つの「T」 |
一方、PC分野におけるオッテリーニ社長のメッセージは、GHzだけでないプロセッサ(GHz & More)というもの。単純に動作クロックを高めるだけでなく、よりベターなコンピューティング体験を実現するための付加価値を加えていく、という方針だ。
動作クロック一辺倒、あるいは処理速度向上一筋からの転換は、この春に発売になったCentrino Mobile Technology(CMT)の発表の際に明らかにされた大きな方針転換だった。今回のIDFではこのCMTに加え、HT、LT、VTを合わせた4つのT(4つのテクノロジ)がベターなコンピューティング体験の基礎となる、というメッセージが打ち出された。
言うまでもなくHTはすでに製品化されているHyperThreadingの略だが、今回オッテリーニ社長は、HTの延長線上にあるものとして、クライアントPC向けのプロセッサにもデュアルコアのプロセッサを投入する方針であることを明らかにした。すでにサーバ向けプロセッサでは、90nmプロセスを用いたMontecitoでデュアルコアを採用する明らかにしていたが、クライアントPC向けの採用を明言したのはこれが初めて。同様に、来年登場するPotomacの次のMP対応XeonプロセッサであるTulsaでもデュアルコア化が図られる。
一足先にデュアルコア化の計画が発表されたIA-64では、Montecitoの次のTanglewoodで4個以上のコアを内蔵したマルチコア化を行うことが明らかにされた。これまでIntelは、3年後(つまりは2006年)のIA-64プロセッサの性能目標が現在のItanium 2(Madison)の8~10倍であると公言していたが、それを担うのがマルチコアを採用したTanglewoodになるわけだ。
●仮想マシンでセキュリティを実現する「LaGrande」
その次のTであるLTはLaGrande Technologyを指す。MicrosoftはWindowsの次期メジャーバージョンアップであるLonghornで、セキュリティ強化技術としてNext-Generation Secure Computing Base(NGSCB)の構想を明らかにしている。
LTは、NGSCBに対応したハードウェアプラットフォームの1つだ。つまり、NGSCB=LTなのではなく、両者の関係はOSによるUSBサポートとUHCIの関係に似ている。すなわちNGSCBを実現するための他の実装(USBでいえばOHCI)もあり得るということだ。言い方を変えれば、LTはNGSCBを実現するためのIntel独自の実装であり、オープンな規格や仕様ではない(将来の可能性は否定しなかったが、少なくともローンチ時にLTをサードパーティチップセットベンダ等にライセンスする予定はないという)。
 |
| LTで保護されたメモリ内のデータは、ハッカーから見られることはない |
NGSCBは、既存のOSと同じ保護されていないOSからNexsusモードと呼ばれるセキュリティを高めた一種の仮想マシンを起動し、その中でカーネルを含めたOSコンポーネントの一部と、アプリケーションを実行することでセキュリティを実現するもの。Nexsusモードでは、すべてのアプリケーションが実行可能なわけではない(すべてのOSの機能が利用できるわけではない)し、アプリケーションはNexsusモード用に書かれなければならない。
LTはそれを可能にするハードウェアによるマシンの仮想化技術であり、これにはCPUだけでなくチップセットも含まれる(少なくとも当初は、LTを利用するにはIntel製チップセットを組み合わせるしかない)。
さらにNGSCBの実現には、LTに加えキーボード(コントローラ)やグラフィックスチップの対応、さらには現行の1.1の次のバージョン1.2のTPM(Trusted Platform Module)と、プラットフォーム全体での取り組みが必要になる(ちなみにNGSCB/LTでサポートされるキーボード/マウスはUSBのみで、PS/2インターフェイスはサポートされない)。IntelはLTに対応したコンポーネントとしてCPUのほかチップセット(メモリコントローラ、USBホストコントローラ、内蔵グラフィックス等)を提供する。
が、LTが製品の機能としてリリースされる世代になっても、すべてのプロセッサがLTを実装するわけではない。例えば同じPentium 6GHzプロセッサ(あくまでも例えである)でも、LT付きとLT無しの両バージョンが提供される見込みだ。これは、Pentium IIIにおいて導入したプロセッサ・シリアルナンバが、一部の根強い反対によって頓挫したことから得た教訓らしい(LTの有無によって価格が変わるのかどうかは明らかにされていない)。
●1台のPCに2台の仮想マシンを作る「Vanderpool」
 |
| VTにより、1台のPCに2つの仮想マシンを構築 |
最後のVTは、Vanderpool Technologyの略で、PC内にソフトウェア的に独立な仮想マシンを設けるパーティショニングをクライアントPCにも持ち込むもの。これにより、子どもがPCで動画を見ている時に、それを妨げることなくお父さんがPCに新しいデバイスドライバをインストールしてOSを再起動する、といったことが可能になる。
高価なマルチプロセッサのサーバシステムではすでに利用されている技術だが、クライアントPCではVTが初めてだ。PCが199ドルで買える時代に、なぜわざわざPCに仮想マシンを構築するのか、という疑問も生じるが、たとえば上の例のように子どものPC利用を親の管理化においておきたい場合、あるいは1台のPCを仕事とプライベートの両方に用いる場合など、1台のPCに複数の環境が共存してくれた方が便利な事例はいくらでも考えられる。実現の際にはソフトウェアのライセンスをどうするか、など技術的な部分以外で解決しなければならない問題もあるが、注目に値する技術だろう。
LT、VTともマシンの仮想化に関する技術であり、Intelプラットフォームの方向性の少なくとも1つが見えてきたように思われる。仮想マシンを構築することと、HT(プロセッサのマルチスレッド化、マルチコア化)は直接関係しないが、相性が良いであろうことは容易に想像がつく。また、PCI ExpressがサポートするQoS機能やSerial ATA 2.0で追加されるコマンドキューイング機能等も、仮想マシンの性能確保に貢献することだろう。
その一方で、クライアントPC向けプロセッサの64bit化には、なお慎重な姿勢を崩しておらず、AMDとは全く異なる方向性を示している点が興味深い。またチップセットビジネスをサードパーティにゆだねる方針のAMDが、プラットフォーム全体の取り組みを必要とするNGSCBにどのような回答を提示するのかも注目されるところだ。
●2011年には22nmプロセスへ、ブッちぎりのIntel製造技術
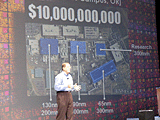 |
| Intelご自慢? のFabを紹介するオッテリーニ社長。100億ドル(1兆2,000億円)の価値があるという。左上の130nm 200mmと書かれているのがFab 20、90nm 300mmがD1C、Reserach 300mmと書かれているのが研究用のRP1で、その下の65nm 300mmと書かれているのがD1Dだと思われる。D1DがD1Cの2倍ほどもある巨大な工場であることが目を引く |
さて、これらの4Tを支えるものとして、オッテリーニ社長は、Intelのシリコンテクノロジを挙げることを忘れなかった。年内に始まる90nmプロセスによるプロセッサの提供はスケジュール通りで変更はないという。また、今後も新しいプロセスを2年毎に提供し続ける予定であり、2005年に65nm(ゲート30nm)、2007年に45nm(同20nm)、2009年に32nm(同15nm)、2011年に22nm(同10nm)というロードマップが提示された(加えて2007年にはTri Gateトランジスタの採用も検討されているようだ)。
このペースに一体どれだけの半導体製造会社がついていけるのか、他人事ながら心配になる。ある意味シリコンバレーの隆盛は、製造と設計が分離できたことと無縁ではない(ファブレスの設計会社の誕生とTSMCに代表されるファウンダリ企業の隆盛)。Intelが製造技術において他社をブッちぎってしまっては、アイデアがあってもそれを製品化できない(たとえ製品化しても製造技術の差で製品の競争力がスポイルされる)のではないかと懸念される。
もちろんこれは、日本の半導体メーカーにとっても他人事では済まない問題だろう。オッテリーニ社長のキーノートで、ふとこうしたことまで考えてしまった。
□IDF Fall 2003のホームページ
http://www.intel.com/idf/us/fall2003/index.htm
□関連記事
【9月17日】Intel、Itaniumのマルチコア版、Xeonのデュアルコア版のプランを明らかに
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0917/idf01.htm
【2002年9月10日】【海外】PCアーキテクチャの大変革を目指す「LaGrande」をIntelが発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0917/idf01.htm
(2003年9月18日)
[Text by 元麻布春男]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.