
 |
|
 |
| 会場となったSilicon Valley Conference Center |
会期:1月23、24日(現地時間)
Platform ConferenceはPCコンポーネント関連のメーカーを集めたカンファレンスで、エンジニアなどを対象にPCコンポーネントの最新トレンドを紹介するイベントだ。今回のカンファレンスにも、メモリチップベンダ、チップセットベンダなどPCコンポーネントに関連するベンダが集まっており、小さいながらも要注目のイベントとなっている。初日である23日はAMD、Elpida、Centaur Technologyによる基調講演が行なわれたほか、数多くのセッションが行なわれ注目を集めた。
●x86-64は「デジタル進化論」に基づく正常進化だ
 |
| AMD CPG(Computation Product Group)ディビジョンマーケティングマネージャ ボブ・ミットン氏 |
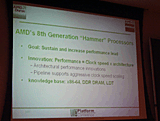 |
| ミットン氏の講演で利用されたスライド。Hammerに関する説明だが、基本的には昨年秋に公開された内容と同じ |
そうした意味ではx86-64のパフォーマンスに関しては気になるところだが、ミットン氏は「x86-64をサポートするHammerファミリーのCPUでは、我々がAthlonで築いている性能面でのリードを確実にしていく。Hammerではパイプラインに改良を加えることで2GHzのクロックを実現するが、単にクロックだけでなく命令セットなどアーキテクチャ面でも性能向上を図っていく」と述べ、Hammerの性能がクロックだけでなく、アーキテクチャ面での改良を含めて向上していくと述べた。
●「DRAM市場は今後も成長していく」とエルピーダメモリの犬飼氏
 |
| エルピーダメモリ取締役の犬飼英守氏 |
犬飼氏はエルピーダメモリに関する説明を行なった後で、DRAMのトレンドを説明した。それによれば、「2005年のDRAM市場構造は大きく変わっていく。2000年にはデスクトップPCの割合が6割近い市場構造となっているが、2005年にはサーバー/ワークステーション、家電、ネットワーク機器などの割合が増えていく」と今後家電や携帯電話などに代表されるネットワーク機器へのDRAMの搭載量が増えると述べ、「今後は家電やネットワーク機器などにも対応するDRAMを生産することがキーになる。これらに対応するためには、高いバンド幅、低いレイテンシ、低電力という3つの条件を満たすことが重要だ」と述べ、今後より高密度で、高帯域、低レイテンシで低電圧なDRAMを作っていくことが重要であるという見通しを明らかにした。
具体的には、チップ容量は2001年の半ばあたりから512Mbitを、2004年の半ばから1Gbitをという予測を示し、消費電力も次世代DDR SDRAMである“DDR II”以降では1.8V駆動も実現される、と述べるなどなど、今後より高密度/高帯域/低電圧化などが進んでいくことに言及した。
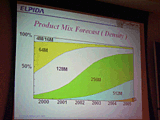 |
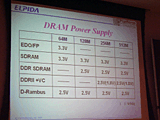 |
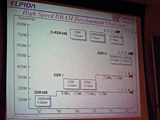 |
| DRAMの密度に関する予測のスライド。2001年の半ばあたりから512Mbitを、2004年の半ばから1Gbitと進化していく | 各容量のチップにおける電圧。DDR IIでは1.8Vもサポートされるようになる | エルピーダメモリのメモリチップ開発ロードマップ |
●Samuel2のベンチマーク結果も公開したCentaurのヘンリー氏
 |
| Centaur Technology社長のグレン・ヘンリー氏。いつも斜に構えた講演はエンジニアに人気 |
基調講演の一番最後に登場したがCentaur Technology社長であるグレン・ヘンリー氏だ。Centaur TechnologyはVIA Technology向けのCPUを開発している会社で、既にVIA Technologiesから出荷されているCyrix IIIは同社のCPUコアであるSamuel1(CentaurでのコードネームはC5A)に基づく製品だ。
ヘンリー氏はお得意のやや斜に構えたトークを展開し「我々のコンペティターは1.5GHzというクロックのCPUを出している。しかし、私の家族でこれを必要としているものはない。例えば簡単な文書しか作らない妻には240MHzのWinChip3で十分だし、それなりに重たい文章を作る私にはCyrix IIIの600MHzで十分だ。まぁ私の息子はゲームもするのでもうすこし速いCPUが必要みたいだが、それでも1.5GHzは必要ではないよ」と述べ、会場の笑いを誘っていた。「我々はコスト面でのリーダシップを獲得すべくCPUを設計している」と述べ、同社のCPU開発のターゲットが「コスト」であることを改めて強調した。その後、ヘンリー氏は同社のCPUコアロードマップについて語った(こちらに関しては後藤弘茂氏のレポートに詳しいので、そちら参照してほしい)。
さらに、ベンチマークについてふれ、「ベンチマークに関して言っておきたいことがある。我々が信じているのは(Ziff-Davis,Inc.の)Winstone99とOffice Benchだ。これらはいずれも信頼がおけるベンチマークと言えるが、ほかは駄目だね。なぜなら、単にCPUに命令を実行させるだけの実世界を反映していないものだったり、何よりもIntelのお金で開発されているものだったりするからね」と述べ、やはり会場の笑いを誘っていた。
なお、ヘンリー氏はSamuel2のパフォーマンスについて同社で計測した結果に関しても明らかにした。Winstone99の結果で、Samuel2は同クロックのCeleronを上回った。以前、AKIBA PC Hotline HotHotレビューでもふれたように、Samuel1ベースのCyrix IIIはWinstone 99などで同クロックのCeleronを大幅に下回っており、残念ながらパフォーマンスではあまり見るべきものはなかった。今回の結果が製品でも実現されるのであれば、すくなくともビジネスアプリケーションを使う限りはさほど差が無くなる可能性が高い。
ただし、今回の基調講演では浮動小数点演算を利用するアプリケーションのベンチマーク結果は公開されなかった。Cyrix IIIの浮動小数点演算はビジネスアプリケーションの場合に比べてさらにCeleronに劣る結果となっていたが、公開しなかったところを見るとSamuel2でもあまり変わっていない可能性が高いといえる(基本的にSamuel2はSamuel1にL2キャッシュを追加しただけなので、おそらくほとんど変わらないだろう)。なお、VIA Technologiesの関係者によれば、Samuel2ベースのCyrix IIIの出荷は第1四半期中が予想されているという。
□関連記事
Platform 2000レポートリンク集
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/link/pform00_i.htm
(2001年1月25日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]