
![]()
 |
|


2000年2月15日~17日 開催(現地時間)
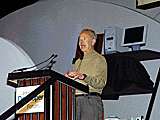
基調講演を行なうIntel会長のアンドリュー・グローブ会長
会場:Palm Springs Convention Center
Wyndham Hotel
Marquis Hotel
昨日の速報でもお伝えしたように、Intel Developer Forumにおいて、同社のアンドリュー・グローブ会長、マイクロプロセッサグループ担当のアルバート・ユウ副社長、デスクトッププロダクトグループ担当のパット・ゲルジンガー副社長による基調講演が行なわれた。今回の基調講演では実に多くの製品が発表され、新しいロードマップも公開されている。このレポートではそれらの内容をもとに2000年のIntelの製品群について整理しよう。
●10倍のトラフィックをどう処理するのか
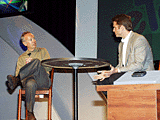 |
| 基調講演でeToysのCIOと語るクレイグ・バレット氏 |
さらに、グローブ会長は「インターネット企業は10倍のスピードで成長しており、トラフィックも10倍になりつつある。それらの企業は問題を抱えており、それらを解決する方策を探している」と述べた。その具体例として、検索エンジンのGoogleのCEO ラリー・ペイジ氏、オンライン玩具ショップeToys CIOのジョン・ハナニック氏、Eコマース企業のCommerce One副社長のサム・プラザー氏の3人が壇上に上がり、それぞれ自社のEコマースサイトにおける問題を語った。3人の問題に共通しているのは、Eコマースを実現するためのインフラが十分でないこと、実現するには非常にコストがかかることだ。3人はグローブ会長に「それを実現する半導体があれば欲しいかい?」と聞かれると「もちろん」と答え、IntelがリリースするItaniumに対する期待を見せた。最後にグローブ会長は「インターネットの確実な発展には半導体が不可欠。Intelは今後とも増え続ける需要に確実に対応できる会社になる」と締めくくった。
●WillametteとTimnaを壇上で披露
続いて登場したマイクロプロセッサ担当アルバート・ユウ副社長は、2000年のIntelのCPU戦略、チップセット戦略などについて説明した。はじめに先日ISSCCで公開されたPentium III 1GHzを搭載したマシンを公開し、「これが当社の最速のCPUを搭載したマシンだ」ととぼけて見せた。すかさず、グローブ会長が「そういえば、例のアレはどうしたかね」とつっこんでみせると、Willametteをポケットから出して聴衆に見せ、会場からは大きな拍手がわき起こった。見たところFC-PGAに見えるが、コアの部分が非常に大きく見える。このあと、既に速報でお届けしたようにWillametteを1.5GHzで動作させるデモを行なった(「速報!Intelが1.5GHz動作のWillametteを基調講演でデモ!」を参照)。
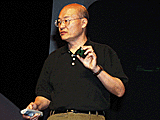 |
 |
| Timnaを手にもつアルバート・ユウ副社長 | Willametteをデモしてみせるアルバート・ユウ副社長 |
続いてユウ副社長はCPU、チップセット、グラフィックスアクセラレータを統合した統合型CPUとして注目を集めるTimna(コードネーム)の実物も公開した。Timnaについてユウ副社長は「Timnaは2000年後半にSDRAMが利用できるバージョンをリリースし、2001年にはRDRAMを利用できるバージョンをリリースする」と述べ、最初のTimnaはSDRAM版としてリリースされることを併せて明らかにした。
なお、パット・ゲルジンガー副社長は、注目されているWillametteやTimnaの製品名について、基調講演後の記者会見で「現時点では何も決定していない。もちろん“Pentium”というブランドネームの持つ重要性は認識しており、これから社内で話し合って決定したい。Timnaに関しては基本的にバリューセグメントの製品であり、なんらかの形でCeleronの名前を冠したものになるだろう」と述べた。
●Willamette、Intel 815、Camino2、Solano2、Tehamaなど続々製品名・コードネームを公開
さらにユウ副社長はIntel製品の2000年のロードマップを公開した。まずサーバー・ワークステーションでは、2000年前半中にPentium III Xeonの900MHz以上、後半にはPentium III Xeonの1GHzを出荷する。ユウ会長のプレゼン資料ではXeonはいずれも256KBのL2キャッシュを搭載したバージョンになるとされており、L2キャッシュの容量を1MBや2MBにしたコードネーム「Cascade 1M/2M」に関する言及は無かった。また、Itaniumに関しては先週のISSCC2000でお伝えしたとおり800MHzとアナウンスされた。
【2000年ロードマップ】
| 2000年前半 | 2000年後半 | |
|---|---|---|
| サーバー/ワークステーション | Pentium III Xeon ≧ 900MHz L2 256k | Itanium 800MHz Pentium III Xeon 1GHz L2 256k |
| Intel 840(*) | Intel 840/460GX(*) | |
| パフォーマンスデスクトップ | Pentium III ≧900MHz | Willamette > 1GHz Pentium III 1GHz |
| Intel 820/Intel 815 | Camino2/Solano2/Tehama | |
| バリューデスクトップ | Celeron ≧ 600MHz | Celeron ≧ 700MHz Timna |
| Intel 810E | Intel/810E/Intel 815 | |
| パフォーマンスモバイル | Pentium III ≧ 750MHz (w/SpeedStep) | Pentium III ≧ 850MHz (w/SpeedStep) |
| 440BX/440ZX | Solano2M/440ZX |
 |
| パフォーマンスデスクトップ向けのロードマップ |
続いて注目のパフォーマンスデスクトップ(いわゆるミッドレンジからハイエンドのデスクトップ)では、先日ISSCCで技術発表が行なわれたPentium III 1GHzが、実際に2000年後半にリリースされることが明らかにされた。もちろんWillametteも2000年の後半にリリースされる。注目のクロックについては、ユウ副社長は「1GHz以上」と語るに留まった。
なお、これまでコードネームSolanoと呼ばれてきたIntel 810Eの後継チップセットの製品名がIntel 815であることを明らかにした。さらに、Intel 820後継のチップセットとしてCamino2、Intel 815の後継チップセットとしてSolano2などのコードネームも公開した。Intel 815に関してはあとのセッションで正式にPC133 SDRAMをサポートするチップセットであることが明らかにされた。今回の基調講演では特に触れられなかったものの、Intel 815では内蔵のグラフィックスアクセラレータだけでなく、外部AGPスロットも利用できるようになると言われている。
Camino2、Solano2に関しての詳細はこのプレゼンテーションでは明らかにはされなかった。プレビューデーのレポートでも述べたように、I/OインターフェイスへのブリッジとなるICH2(I/o Controller Hub)を含み、Ultra ATA/100、イーサネットコントローラ内蔵、USB4ポートがサポートされる。
さらに、プレゼン資料には書かれていなかったが、Willamette用のチップセットのコードネームが「Tehama」であることも併せて明らかにした。
●ローエンドはCoppermineベースのCeleronとTimna
さらに、バリューデスクトップ(いわゆるローエンドデスクトップ)ではCeleronについての発表が行なわれた。ユウ副社長は「Coppermineをベースにした0.18μmで作られたCeleronを前半中に出荷する」と述べ、いわゆるCoppermine-128kのコードネームで呼ばれてきたCeleronを2000年前半中にリリースすることを明らかにした。これにより、デスクトップPCでも6月までにはインターネット・ストリーミングSIMD拡張命令(SSE)に対応したCeleronが出荷されることになる(モバイルでは既に出荷済み)。さらに、2000年後半にはCeleronのクロックを700MHzまで向上させることも併せて明らかにした。なお、FSBのクロックについては特に言及されていない。2000年後半には前述のTimnaもリリースされる。
パフォーマンスモバイル(いわゆるハイエンドのノートパソコン)では、2000年前半中にSpeedStep対応モバイルPentium IIIの750MHz以上、後半には850MHz以上がリリースされることが明らかにされた。また、注目されるのはチップセットとしてコードネームSolano2Mが2000年後半に投入されることだろう。Solano2Mはその名前の通りSolano2のモバイル版で、Solano2と同じようなスペックである可能性が高い(つまり、モバイル向けの統合型チップセットであると言えるだろう)。
●初めてUSB 2.0対応機器をデモ
 |
| パット・ゲルジンガー副社長はUSB 2.0に対応したスキャナのデモを行なった |
さらに、ゲルジンガー氏はUSB 2.0に対応した試作中のスキャナを公開し、それを利用して実際にUSB 2.0のデモンストレーションを行なった。具体的にはUSB 2.0に対応したスキャナを利用して文書をPCへ取り込み、それをUSBプリンタで印刷するというものだ。具体的な速度の比較が行なわれた訳ではないので、USB 1.0や1.1の機器との速度差はわからない。しかし、既にUSB 2.0に対応した機器がこの段階で動作しているということは、USB 2.0の普及に向けて意味のあるデモと言える。
□IDFホームページ
http://developer.intel.com/design/idf/
(2000年2月17日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]