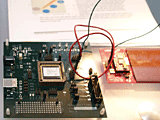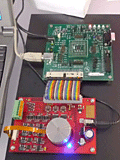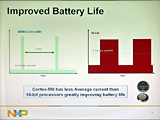【ESC SV 2009レポート】
MCUいろいろ
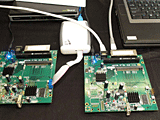 |
| 【写真01】左右のボードはどちらもIP7500のリファレンスボード。IP7500は右下のヒートシンクの下に位置し、左上のものは2chのGbE PHY/Switchだそうだ。IP7500とPHY/Switch、それと周辺電源回路以外に目立った部品がないという低コスト設計 |
会場:米国カリフォルニア州McEnery Convention Center
会期:3月30日~4月2日
今回のESCは、いろんな意味で「なんだこれは」という状況ではある(このあたりは後でまとめてレポートしたい)が、MCUに関してはそれなりに活気がある。特にMicrochip vs Atmelは凄まじい(これも別にレポートしたい)が、そうした中において「その他」のベンダーが、案外にしぶとくMCUを投入していたので、まずはこのあたりをレポートしたい。
●Ubicom IP7000/7500
初日のプレビューでもちょっと触れたが、ネットワーク向けの低価格プロセッサ(というか、ネットワーク対応MCUというべきか)をリリースし続けているのが米Ubicom。2003年のEPFでは、USBやPCIなどのバスまですべてGPIOポートを使ったソフトウェアI/Oでカバーしてしまい、しかも内蔵メモリで全部まかなうのでEBOMが非常に安く上がるという、ある種の極北に位置するプロセッサである「IP3023」を発表したりしたが、その後も同社の方向性はまったく変わっていなかった。2006年にはStreamEngineという、それまでの仕組みを発展させたようなメカニズムを開発し、さらにこれを順次新しい製品に投入していく。
今回展示されたのはその最新型である「IP7000」(写真01)である。この製品もまた最適化された構成と、内蔵されたメモリだけですべて動作するので外部にディスクリート部品をほとんど必要とせず、結果として非常に安く構成できるのが最大のウリである。
以前と比べて多少変わったのはソフトウェア環境だろうか。IP3023の場合、OSやアプリケーションはすべて自前のものという話だったが、IP7000の場合、Linux 2.6.28 SMP kernelを搭載したBSPが実装されており、この上で普通にLinuxアプリケーションが動作する、という話だった。もっとも、最適化次第で性能が変わるのは相変わらずだ。
写真01の2枚のボードは、ハードウェア構成は全く同一ながら、左は普通にLinux BSPを乗せ、この上で普通に記述したルーターアプリケーションが走っているだけで、この際のルーティング性能はおおむね200Mbps前後。一方右は構成に最適化したソフトウェアが搭載され、ルーティング性能は400Mbps以上(ピークで500Mbps近く)と、ほぼ性能が倍増している。
このIP7000はネットワークルーターなどのアプリケーションに向けた製品だが、これとは別にコンシューマネットワークオーディオデバイス向けの「IP7500」も同時に公開された(写真02)。IP7500はIP7000からEthernetを1ch減らし、代わりにオーディオやビデオをハンドリングするようにしたものだ。このIP7500の前世代にあたるものは、LogitechのSqueezeboxなどで採用されており(写真03)、このマーケットに向けた新製品という位置づけである。
Ubicomの場合、ターゲットとするのはあくまでエントリーレベルのマーケットで、より高付加価値・高価格のマーケットはターゲットとしないそうだ。ただ、そうは言ってもエントリーレベルのマーケットに求められる機能や性能も次第に高くなっていくので、それにあわせての機能強化は必要だ、ということらしい。
ちなみに「まだソフトウェアI/Oを使っているのか?」と聞いたところ、フィロソフィーは同じだがもう少し最適化したとの答えだった。PCIのIPのコストは(金額という意味でも、ダイエリアあるいはゲート数という意味でも)以前よりずっと下がっており、無理にソフトウェアI/Oを使うよりも、適度にハードウェアI/Oを使ったほうが良いとは思われる。もっとも、IP7000/IP7500は共に(相変わらず)12wayのマルチスレッドをサポートしており、完全にI/Oがハードウェア化されたというよりも、ソフトウェアI/O向けの簡単なアクセラレータが搭載された程度なのかもしれない。
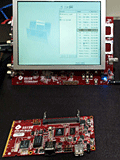 |
 |
| 【写真02】大きな特徴は2Dディスプレイをサポートしたこと。このディスプレイもやはり内蔵メモリをフレームバッファとして使うそうだ。「3Dは?」というと、3Dに限らず2Dでもアクセラレータの類は一切なく、あくまでCPUからソフトウェアレンダリングするのみだそうだ。ターゲットとするのは、ハイエンドの3D GUIを必要とするようなアプリケーションではなく、もっと安価な製品向けだからこれでいいのだ、との事 | 【写真03】Squeezeboxは何製品かあるが、たとえばこちらなど。さすがにアプリケーションまで実装すると内蔵メモリだけでは足りなかったようで、外部にメモリが増設されている |
●EPSON C17
昨年、EPSONはE-Inkと共同で電子ペーパーのコントローラを出展しており、今年も同じくS1D13521が展示されてはいたのだが(写真04)、それはほんの片隅であり、ブースの主役は同社の16bit MCUであるC17であった(写真05~07)。分野としては、温度管理系のほか、医療関係やリモコンなどの展開も狙っているそうで(写真08~09)、ANT+の実装例も同時に展示されていた(写真10~11)。
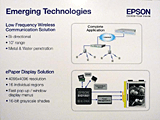 |
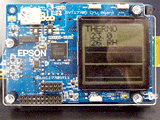 |
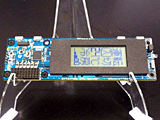 |
| 【写真04】ボードそのものについては、昨年展示されていたAM300が今年も展示されていた | 【写真05】C17を搭載したサーモスタットの実装例 | 【写真06】こちらはC17をつかったリモコンの例。基板の右端にIrDAのLEDがあるのが判る |
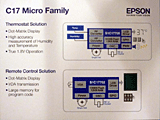 |
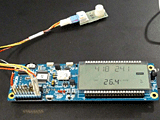 |
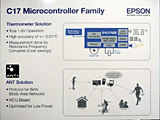 |
| 【写真07】内部構成。サーモスタットの方は、温度センサーと湿度センサーを内蔵する2chのRFコンバータで変換し、結果を表示するというもの。リモコンの方は、GPIO経由でキー入力を取り込んで、結果をIrDAで送信するといういわゆる従来型リモコン。「リモコンもワイヤレスの方向に進んでいるけど、ZigBeeを使ったRF4CEなんかのソリューションは?」と聞くと「ワイヤレスにはANT+がある」。いやそれはいくらなんでも無理だろう | 【写真08】デジタル体温計のプロトタイプ。おおよそ体温計にはでかすぎる気もするが、まぁ製品サンプルではないからこんなもんだろう | 【写真09】いくらなんでも普通の体温計でここまでの精度は要らない気もするが、精度が高ければ他の用途にも使えるわけで、その意味では高くて困るものではないだろう |
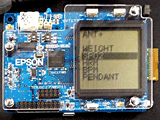 |
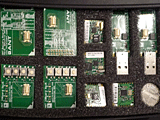 |
| 【写真10】ANT+とは、さまざまなセンサー(心拍数とか体重、あるいは自転車で移動時の速度や移動距離など)をワイヤレスで繋ぐ、BAN(Body Area Network)のためのプロトコルである。当然ながら到達距離はごく短い範囲でしかない | 【写真11】ANT+用のさまざまなモジュール類も同時に展示されていた |
理屈はわかるが、こうしたマーケットはMicroChipやAtmel、国内でもNECやルネサスなど、多数の競合メーカーが多数のラインナップを揃えているところであり、そうそう簡単にマーケットが掴めるとも思えない。このあたりを振ってみると、「我々は8bit並みのフットプリントで、32bit並の性能を実現できるソリューションであり、これで差別化したいと思っている」という、まるでTIがMSP430を紹介する時のような返事が返って来た。
現実問題として、(少なくともアメリカマーケットでは)16bit MCUが使われるような幅広い市場に全て対応するわけではなく、あくまで温度/湿度管理とか医療関係といった狭い分野をターゲットとして、まずは足がかりを築きたいようだ。
ちなみに「アメリカと日本のどちらがリーダーシップを取ってC17のプロモーションを決めたのか」と振ってみると、ちょっと答えに詰まりつつも「どちらがと言うわけではなく、コラボレーションだ。我々EPSON Americaはアメリカのマーケットについて責任があり、EPSON Japanはアジア全体を統括している。なので、お互いにマーケットの動向について情報を交換し合い、その結果として今回C17を積極的に展示することにした」という返事が返って来た。
実はEPSONのマイコン事業に関しては、以前内部の方に「実は我々マイコンも作ってるんですが、あんまりメジャーじゃないんですけど、どうしたらいいんでしょうねぇ」なんて話を伺ったことがある。実際、このマーケットは非常に大きいものの、だからといって簡単に参入して売り上げが確保できるほど甘いマーケットではない。それなりにシェアをつかんで売り上げが伸びるようにするためには、手厚い製品ラインナップや開発ツールチェーンの確立、サポートや製品の継続的な供給など、かなり思い切った初期投資が必要とされるマーケットでもある。
これを少しでも削減するための方法が、すでに共通化されたアーキテクチャを採用することで、この結果50MHzで動作する8051互換MCUなんてものが市場に出回る一因でもあるのだが、そうした安易な策をとらずにあくまで独自アーキテクチャを貫くという姿勢はなかなか潔いものがある。おそらくESCに展示しただけでは全然クライアントは増えないと思われるので、今後も継続してマーケティングを行ってゆく必要はあるだろう。差別化できる要因の1つはANT+で、これが広がるようであれば活路が見出せるかもしれない。
●NXP Cortex-M0
ついでに(とか書くと失礼だが)、NXPのCortex-M0の動作サンプルも、NXPのブースとARMのブースの両方で展示されていたので、ちょっと紹介しておきたい。Cortexファミリーは、「A」がハイパフォーマンスのアプリケーションプロセッサ向け、「R」がリアルタイム制御向け、「M」がマイクロコントローラ向けというラインナップで、そのMファミリーもまず登場した「M3」に続き、FPGA上で実装できる「M1」がリリースされ、ついで今回登場した「M0」となる。
Mに続く数字が大きいほど性能が高いとされるので、つまりM0はM1の下に位置する形だ。確認してみると、「もちろんFPGAの構成とか動作周波数で性能が変わるから一概には言えないが、ポジション的にはCortex-M0はCortex-M1の下に位置する」との事。Cortex-M1と異なり、FPGAに乗せることはできない(つまりASICオンリーのコア)ので、Cortex-M3の場合と同様に今後SoCの形で製品が登場することになると思われる。
今回NXPでは、太陽電池で駆動するCortex-M0の動作デモ(写真12)と、Cortex-M0を使ったモーター制御デモ(写真13)が展示されていた。写真12の方はやたらとパッケージが大きいが、これはエンジニアリング用のもので、実際のパッケージは写真13のように非常に小さい。
Cortex-M0の特徴は、高性能に起因する省電力性の高さ、というのがARMやNXPの主張である。例えばモーター制御の場合、1クロックサイクルで制御に必要な掛け算が完了するので、MCU自身の待機時間を長く取ることができ、これが省電力に繋がる(写真14)としている。
Cortex-Mシリーズは、ある種ARMの戦略的製品である。Cortex-M3は32bitのARM命令をサポートしておらず、実行できるのは16bitのThumb-2命令である。これはCortex-M1も同じで、Thumb-2のサブセットのみが実行できる。要するに32bitプロセッサと言いつつも、事実上16bitプロセッサであると筆者は考えている。Cortex-M0はそのローエンドになるわけで、つまり8bit MCUの領域に重なる製品と考えてよいと思う。Thumb/Thumb-2で、8/16bit MCUの世界を席巻するという遠大な野望の尖兵となるのがこのCortex-M0というわけだ。
そう考えると、NXPが(Triad Semiconductorと並んで)最初にCortex-M0のライセンスを受けたのも理解しやすい。NXPは8bit MCUは8051互換製品しかないし、16bitも独自アーキテクチャのXAのみで、あまり普及しているとは言えない。どちらのアーキテクチャも、MicrochipのPICなどに伍してローレベルのMCU市場でシェアを握るにはちょっと力不足である。ここにCortex-M0を導入するのは、なかなか面白い試みになりそうで、今後の展開に期待したいところだ。
□ESC Silicon Valley 2009のホームページ(英文)
http://esc-sv09.techinsightsevents.com/
□関連記事
【2003年6月24日】【PEF】コスト最優先の異色SMTプロセッサ「Ubicom IP3023」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0624/epf04.htm
(2009年4月3日)
[Reported by 大原雄介]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp お問い合わせに対して、個別にご回答はいたしません。
Copyright (c)2009 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.