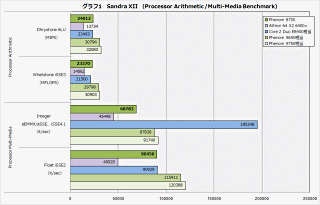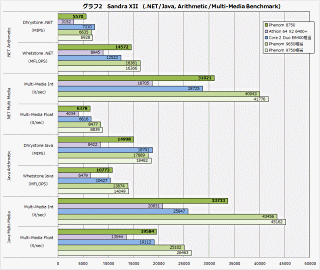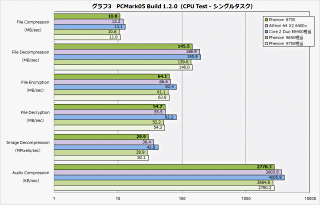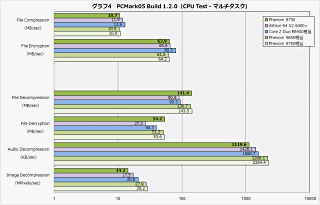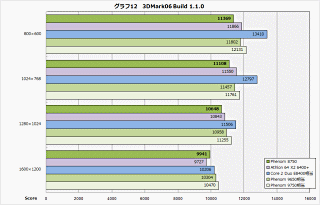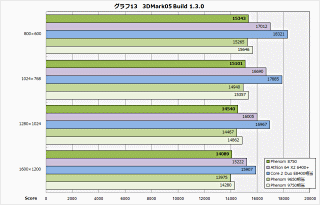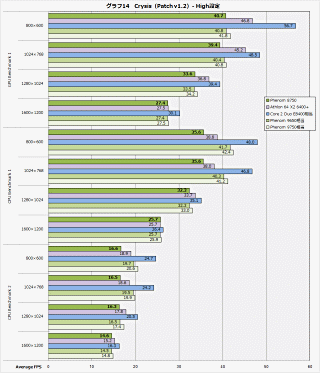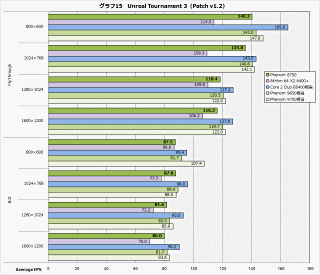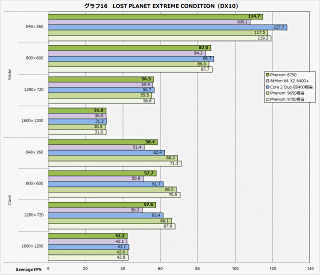|


■多和田新也のニューアイテム診断室■マルチコアCPUの新形態「Phenom X3 8750」 |
AMDが投入を始めているトリプルコアCPU「Phenom X3シリーズ」。ついに自作ユーザーにも利用できる形で発売されようとしている。デュアルコアを超えるコア数のCPUのバリエーションの1つとして注目しているユーザーも多いだろう。今回は、トリプルコア製品の最高クロック製品となる「Phenom X3 8750」のパフォーマンスを見てみたい。
●B3ステッピングを採用した2.4GHz動作製品
AMDのトリプルコア製品は、3月28日に正式に投入が発表されている。このタイミングではPhenom X3 8600/8400の2製品が明らかになった。しかし、これらはOEM向けのみに提供されるうえ、B2ステッピングを採用したものである。今回紹介するのは、B3ステッピングを採用したPhenom X3 8x50シリーズで、こちらはBOX製品としても発売される見込みだ。
このB3ステッピング版のPhenom X3シリーズのラインナップは3製品で、主な仕様は表1の通り。同じB3ステッピングのPhenom X4シリーズの仕様も比較のために掲載している。クアッドコアとは異なり、最高動作クロックは現時点で2.4GHzのモデルがラインナップされるに留まる。HT Linkも1.8GHzのみである。
| Phenom X3 8750 | Phenom X3 8650 | Phenom X3 8450 | Phenom X4 9850 | Phenom X4 9750 | Phenom X4 9650 | Phenom X4 9550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作クロック | 2.4GHz | 2.3GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 2.2GHz |
| L1データキャッシュ | 64KB×3 | 64KB×4 | |||||
| L2データキャッシュ | 512KB×3 | 512KB×4 | |||||
| L3データキャッシュ | 2MB | 2MB | |||||
| HTLinkクロック | 1.8GHz | 2GHz | 1.8GHz | ||||
| 動作電圧 | 1.05~1.25V | 1.20~1.30V | 1.10~1.25V | ||||
| 周辺温度(最大) | 70℃ | 61℃ | 70℃ | ||||
| TDP(最大) | 95W | 125W | 95W | ||||
| 価格(1,000個ロット時) | 195ドル | 165ドル | 145ドル | 235ドル | 215ドル | OEM向け | 209ドル |
何と言ってもPhenom X3の魅力は価格である。最上位モデルとなるPhenom X3 8750の価格は、B3ステッピングのクアッドコアとして最廉価モデルとなるPhenom X4 9550よりも安価に設定されている。デュアルコアよりも並列処理性能が高いCPUを、クアッドコアよりも安い価格で入手できるというのが、この製品の存在価値といえる。
今回テストに用いるのは、トリプルコア最上位モデルとなるPhenom X3 8750である(写真1)。OPNは「HD8750WCJ3BGH」となっており、末尾のGHからB3ステッピングであることが分かる。
マザーボードは、AMD 790FXを搭載する「GA-MA790FX-DQ6」を使用(写真2)。このBIOSバージョン“F4”以降でトリプルコアのサポートが行なわれており、今回も正しく認識した。
 |
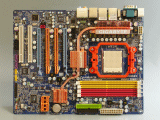 |
| 【写真1】B3ステッピングを採用するトリプルコア最上位モデル「Phenom X3 8750」 | 【写真2】AMD 790FXを搭載するGIGABYTE「GA-MA790FX-DQ6」 |
CPU-Zの表示でも2.4GHzで動作していることを確認できる(画面1)。また、3コアという初登場の製品ではあるが、Windows Vistaは3コアを正しく認識している(画面2)。使い勝手の面では、従来の新しいCPU同様、BIOSアップデートが必要になる可能性が高いことにだけ注意すれば問題ない。
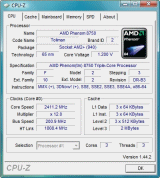 |
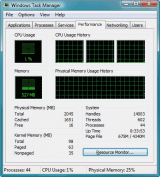 |
| 【画面1】Phenom X3 8750におけるCPU-Zの結果 | 【画面2】Windows Vistaではまったく問題なく3コアのCPUとして認識する |
●デュアルコア、クアッドコアとの性能差をチェック
それではベンチマークの結果を紹介していきたい。環境は表2に示した通り。デュアルコア製品としてPhenom X3 8750と価格帯が近くなりそうなAthlon 64 X2 6400+とCore 2 Duo E8400、クアッドコア製品は、同クロックのPhenom X4 9750と一段下のクロックとなるPhenom X4 9650を比較対象とした。
ただし、表中に“相当”と表記してある製品に関しては、BIOSから設定を変更して仮想的に作りあげたものである。具体的には、Phenom X4 9750/9650はPhenom X4 9850 Black EditionのHT Linkクロックと倍率を変更。Core 2 Duo E8400は、Core 2 Duo E8500の倍率を変更している。パフォーマンス面での影響はないが、消費電力は参考程度のスコアとなるので注意されたい。
| CPU | Phenom X3 8750 Phenom X4 9750相当 Phenom X4 9650相当 Athlon 64 X2 6400+ |
Core 2 Duo E8400相当 | ||
|---|---|---|---|---|
| マザーボード | GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6(AMD 790FX) | ASUSTeK P5K Pro(Intel P35) | ||
| メモリ | DDR2-800(1GB×2/5-5-5-18) | |||
| ビデオカード | NVIDIA GeForce 8800 GTX(ForceWare 174.74) | |||
| HDD | Seagete Barracuda 7200.11(ST3500320AS) | |||
| OS | Windows Vista Ultimate Service Pack 1 | |||
では、順に結果を見ていきたい。まずは、CPUの演算性能を見るSandra XIIの「Processor Arithmetic/Processor Multi-Media Benchmark」(グラフ1)、「.NET Arithmetic/Multi-Media Benchmark」、「JAVA Arithmetic/Multi-Media Benchmark」(グラフ2)、PCMark05のCPU Test(グラフ3、4)の結果である。
SandraXIIはバージョン14.20aからトリプルコアサポートも行なわれており、Phenom X4シリーズとの差異からしても妥当なスコアが出ている。SSE4.1が有効になる場面は仕方ないものの、おおむねCore 2 Duo E8400と同等以上のスコアになっており好印象を受ける結果だ。
一方、解釈が難しい結果となったのがPCMark05における4タスク同時実行テスト部分だ(グラフ4の下4項目)。結果を見る限り、同時に動く4タスクのうち、3つのコアが2タスクを優先的に処理させているような結果になっており、4タスクが平均的に性能を伸ばすことがない。トリプルコアにおけるOSのプロセス割り振りの独特さが表れている。
ちなみに、2タスク同時実行テストや、4タスク同時実行時に優先的に処理されたと思われる2タスク分のスコアは同クロックのPhenom X4 9750と同等程度となっている。
続いてはメモリアクセス性能を見るために実施した、Sandra XIIの「Cache & Memory Benchmark」(グラフ5)と、PCMark05の「Memory Latency Test」(グラフ6)の結果である。
SandraのCache&Memory Benchmarkのキャッシュ部分の速度については、CPUのアーキテクチャ、クロックがまったく異なるため、ちょっと参考にしづらい。クアッドコアより低いスコアが出るのはマルチスレッドでアクセスがなされるためである。PCMark05で見る限り、キャッシュ部分のメモリレイテンシは大きく変わららない。
メインメモリのアクセスについては、Phenom X4両製品と比べ、善し悪しが出ているものの差は大きくない。Core 2 DuoやAthlon 64 X2と比べると、明確に良い値が出ており、Phenomらしい優秀な結果である。
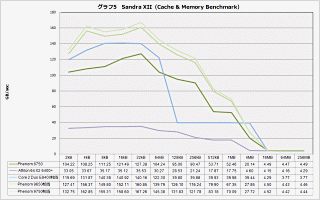 |
| 【グラフ5】Sandra XII(Cache & Memory Benchmark) |
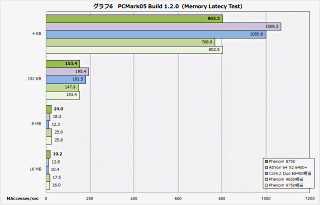 |
| 【グラフ6】PCMark05 Build 1.2.0(Memory Latecy Test) |
ここからは実際のアプリケーションを利用したベンチマークテストである。「SYSmark 2007 Preview」(グラフ7)、「PCMark Vantage」(グラフ8)、「CineBench R10」(グラフ9)、「動画エンコードテスト」(グラフ10)の結果を掲載している。
大局的にまとめると、まずクアッドコアとの比較では、クロックが一段低いPhenom X4 9650よりも劣るシーンが多い。Athlon 64 X2 6400+との比較では同等以上のシーンも多いが、CineBench R10の結果からも明白な通り1コアあたりの性能は劣る影響が出ているシーンも多い。Core 2 Duo E8400との比較ではH.264エンコードで優位に立った程度で、劣るシーンが目立つといった結果だ。
1つ、興味深い結果を見せたのがWMV9エンコードである。全体にマルチコア化の好影響が見られる動画エンコードにおいてAthlon 64 X2とほとんど差のない結果になっているのだ。そこで、Athlon 64 X2 6400+、Phenom X3 8750、Phenom X4 9650の各CPUで、TMPGEnc 4.0 XPress内蔵エンコーダによるMPEG-2エンコード時、WMV9エンコード(フロントエンドはTMPGEnc)時のパフォーマンスグラフをチェックしてみた。
コア数が増えるほどHDDなどのボトルネックの影響もあってCPU使用率が低くなりがちなのは妥当だとしても、Phenom X3 8750のWMV9エンコード時のみ、明らかにCPUがうまく活用されていないことが分かる。Phenom X3 8750のWMV9エンコード時はCPU使用率が明確に低いだけでなく、一番左に表示されているコアと、右2つに表示されているCPU使用率がはっきり異なっている。
WMV9エンコーダはマルチスレッドの効率が良いほうではないが、クアッドコアですらCPU使用率はもっと高くなっている。おそらく、WMV9のエンコーダが3コアというものを想定していない作りになっていると想像される。
先のPCMark05のマルチタスクテストでも3つのコアをOSがうまく活用できていないように見受けられるシーンがあったように、PCとしては前例のないトリプルCPUという環境へのソフトウェア側の適合が課題になるシーンが、ほかにも潜在している可能性もありそうだ。
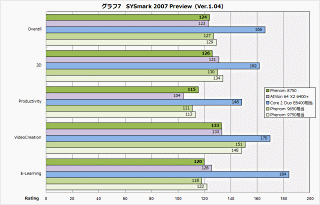 |
| 【グラフ7】SYSmark 2007 Preview(Ver.1.04) |
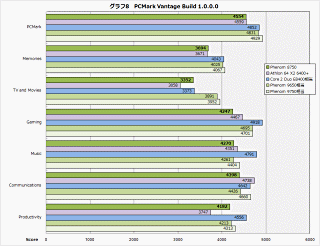 |
| 【グラフ8】PCMark Vantage Build 1.0.0.0 |
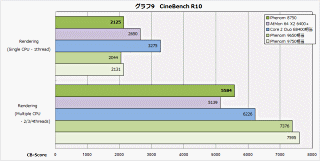 |
| 【グラフ9】CineBench R10 |
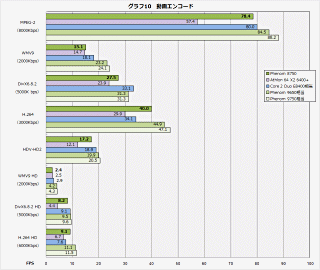 |
| 【グラフ10】動画エンコード |
続いては3D関連のベンチマークだ。テストは、「3DMark06」(グラフ11、12)、「3DMark05」(グラフ13)、「Crysis」(グラフ14)、「Unreal Tournament 3」(グラフ15)、「LOST PLANET EXTREME CONDITION」(グラフ16)である。
この結果は、全体にCore 2 Duo E8400のスコアの良さが目立つ。Phenom X3 8750はアプリケーションのマルチスレッド化がなされていれば、まずまずの結果ではあるものの、Athlon 64 X2 6400+に劣るアプリケーションもあることを考えると、3Dゲームにおいて安定した性能を求めるのは難しい。
もっとも、これはクアッドコアにもあてはまるわけで、良い方向に解釈すればクロックが重要になるアプリケーションも多い3Dゲーム用途においては、同じ2.4GHzならPhenom X3シリーズのほうが安く買えるのがメリットにはなり得るだろう。
最後に消費電力の結果である(グラフ17)。先述の通り、倍率やHT Linkクロックの調整によって仮想的に作り出したCPUが多いため、参考程度に捉えていきたい。
Core 2 Duo E8400は別格の省電力ぶりであるが、AMD製品同士の比較でいえば、クアッドコアのPhenom X4シリーズより低いのは当然として、ピーク時にはAthlon 64 X2 6400+も下回ることができている点は好印象だ。このバランスの良さは魅力といえる。なお、今回は正確なテストが行なえていないので予想の範囲を出ないが、同じTDPとなるPhenom X4 9650はもう少しPhenom X3 8750との差が小さいのではないかと想像している。
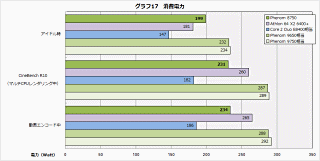 |
| 【グラフ17】消費電力 |
●トリプルコアならではの付加価値に期待
以上の通り結果を見てくると、やや中途半端さを感じる製品である印象は否めない。同じアーキテクチャ、クロックも近いクアッドコア製品との比較で劣るのは、価格分もあるので致し方ない。
Athlon 64 X2 6400+との比較ではマルチスレッド対応の度合いによって結果は左右される。このデュアルコア製品は、アーキテクチャ的には一世代古いことになるが、クロックの高さで押し切るシーンが多い点は留意すべきだ。
Phenom X3シリーズは、クロックについてはクアッドコアに対する優位性がない。AMDから提供された資料によればダイサイズは285平方mmとなっており、B3ステッピングのPhenom X4 9x50シリーズと同じ。つまり、ダイは同じものであるわけで、クロックでの優位性を期待するのは難しいかも知れない。
デュアルコアはコアが2つしかない代わりに、クアッドコアよりも動作クロックが高いという魅力があった。おまけに価格も安い。これは、Athlon 64 X2もCore 2 Duoも同じ性格を持っている。しかし、Phenom X3が持つクアッドコアに対するアドバンテージは価格しかないのである。
デュアルコアの登場以降、アプリケーション動作の並列性が高まっているなか、安い価格でマルチコアを提供するPhenom X3シリーズは興味深い製品だと思う。もちろん、クアッドコアやそれ以上のコアを持つプロセッサがシーンを問わずフル活用できるほどの並列処理が当たり前とは言えない、過渡期だからこその製品ではある。そうしたタイミングで、クアッドコアと比較して良くも悪くも価格相応という印象を受けるPhenom X3シリーズが登場したことは、マルチコア製品ブランドであるPhenomシリーズの製品ラインナップが充実したという意味を持つ。これは重要なポイントだ。
しかし、トリプルコアというほかにはない製品であるだけに、もう1つパンチが欲しいというのも筆者の本音である。クロックでも、消費電力でも何でも良い。Phenom X3シリーズならではの“何か”を期待するのは贅沢な願いだろうか。
□関連記事
【3月27日】B3ステッピング採用「Phenom X4 9850 Black Edition」速報レビュー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0327/phenom.htm
【3月27日】AMD、新ステッピングの「Phenom X4 9x50」シリーズ
~TDP 65W版やトリプルコアのPhenom X3 8000シリーズも
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0327/amd.htm
(2008年4月23日)
[Text by 多和田新也]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2008 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.