 |


■元麻布春男の週刊PCホットライン■Yorkfieldに見るHigh-kメタルゲートの威力 |
●QX6700より発熱量が小さいQX9650
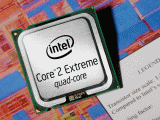 |
前回、筆者は初めて自分の環境で45nmプロセスのプロセッサ(Core 2 Extreme QX9650)を利用した。それまでテストに使っていたCore 2 Extreme QX6700に比べて、ベンチマークのスコアも良くなったのだが、それ以上に驚いたのは、発熱量が小さいことだ。
前回のテストでは、それまで使っていたQX6700をそのままQX9650に付け替えた。つまり、同じ電源、同じマザーボード、同じCPUヒートシンクである。なのに、明らかにCPUヒートシンクのファンの回り具合が違う。何というか、そよそよとしか回らないのである。当然、発生するノイズも違う。これで違いに気がついたわけだ。
ところが、スペックを調べて見ると、QX6700もQX9650もTDPは同じ130Wで改善されていない。TDPだけを見る限り、QX6700もQX9650も同じだけ発熱することになる。おそらくピークとしてはそうなのかもしれないが、実際にQX9650がどのような条件で130Wを消費するのか教えて欲しいと思うほど、ファンの回転数は抑えられている。そこで、もう少しデータシートを調べてみることにした。そして見つけたのがEHPという数字だ。
EHPというのはExtended HALT Powerの略。内蔵するすべてのプロセッサコアがHALT命令を実行し、動作クロック、電圧ともに低い状態になった低電圧ステートの一種、Extended HALT状態での消費電力を指す。おおざっぱに言えば、アイドル状態での消費電力といってもいい。
このEHPとTDPをクアッドコアプロセッサで比較したのが表1だ。QX9650とQX6700は、同じTDP(130W)でありながら、EHPは16Wと50Wで、3倍以上も異なる。Tc(プロセッサ表面中央の温度)も、QX9650のEHPである16W時に摂氏5度~45.1度であるのに対し、QX6500のEHPである50W時は同5度~50.9度とされている。さらに、このEHPが計測された時の条件としてデータシートに注意書きされている温度は、QX9650の37度に対し、QX6700は50度になっている。
| プロセッサ | 製造プロセス | 動作周波数 | FSBクロック | TDP | EHP | 左記EHP時のTc (min/max) | EHP計測時のTc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QX9650 (Yorkfield) | 45nm | 3.0GHz | 1,333MHz | 130W | 16W | 摂氏5度/45.1度 | 摂氏37度 |
| QX6700 (Kentsfield) | 65nm | 2.66GHz | 1,066MHz | 130W | 50W | 摂氏5度/50.9度 | 摂氏50度 |
| Q6700 (Kentsfield) | 65nm | 2.66GHz | 1,066MHz | 95W | 24W | 摂氏5度/51.1度 | 摂氏50度 |
要するにQX9650は、アイドル状態の消費電力が16Wで、その時にプロセッサ表面中央の温度が摂氏37度であるのに対し、QX6700は50Wの電力を消費し、温度が摂氏50度まで上がっている、ということだ。実際にはTcは取り付けられたヒートシンクの冷却力に影響されるが、同じヒートシンクをつけて、両方のプロセッサを利用した筆者の経験から考えて、QX9650のデータシートの数字(17W)が、特殊な冷却環境でのものとはとても思えない。おそらく冷却条件はあまり変わらず、両者でアイドル時の消費電力が34W違い、温度も13度違うということだと思われる。QX6700と同じ2.66GHz動作でも、後から登場したCore 2 Quad Q6700ではTDP、EHPともに引き下げられているが、EHP計測時のTcは摂氏50度でQX6700と変わらない。QX9650に比べれば、ファンは回ることだろう。
もちろん、EHPはあくまでもアイドル時の消費電力に過ぎないが、稼働時の平均的な消費電力も、QX9650とQX9700で相当違うように思われる。QX9650は、ベンチマークテストであるPCMark Vantageを実行している最中も、ヒートシンクがちっとも熱くならないのである。しかも実際にはQX9650が3GHzで動いているのに対し、Q6700は2.66GHz動作に過ぎない。QX9650は、65nmプロセスでは実現できなかった3GHzオーバーの動作クロックを実現しつつ、実質的な消費電力は下がっているのである。
●45nmプロセスだけでは到達できない差
げに恐ろしきはYorkfieldコアというところだが、何がこの違いを生み出しているのだろう。筆者はこれこそHigh-kメタルゲートの威力だと思っている。言い換えれば、従来のまま製造プロセスを45nmに縮小しただけでは、QX9650の高性能/低消費電力は実現しなかっただろう。
あまり知られていない、というより意識されていないことだが、90nmプロセスから65nmプロセスに製造プロセスが縮小された際、TDPの下げ幅が小さかった(あるいは変わらなかった)上、動作クロックも上がらなかった(上げられなかった、と言うべきか)。現時点において、Intelのプロセッサ(量産品の定格)で最も高い動作クロックを達成したのは90nmプロセスによるPentium 4 570/571/670/672(Prescott 2M)の3.8GHzであり、65nmのPentium 4(CedarMill)がこれを越えることはなかった。
Intelのプロセッサは65nmプロセスの途中から、主戦場をシングルコアのPentium 4から、デュアルコアプロセッサへと移し、さらに新しいマイクロアーキテクチャ(Core)へと移行したから、これだけで65nmプロセスのプロセッサが90nmプロセスを越えられなかった、というのは早計かもしれない。実際、デュアルコアプロセッサ同士の比較では、65nmプロセスのPreslerは、90nmプロセスのSmithfieldを上回っている。だが、そのPreslerの動作クロックも、3.8GHzに達することはなかった。
AMDのプロセッサでも、同じデュアルコアでありながら65nmプロセスのBrisbaneは、90nmプロセスのWindsorを動作クロックで越えられていない。製造プロセスの微細化には、今でも製造コストの引き下げに大きな効果が期待できるものの、それによって単純に動作クロックが上がる、とは言えなくなってきているわけだ。
その理由がリーク電流、特に動作していない時に消費されるゲートリーク電流の増加であることは良く知られている。製造プロセスの微細化を進めた結果、ゲート絶縁膜があまりにも薄くなりすぎて、電流がながれていない時(動作していない時)も、ゲートからチャンネルへ電子が漏れ出してしまうようになってしまったのだ(トンネル効果)。65nmプロセスのプロセッサが、動作クロックの点で90nmプロセスのプロセッサを越えられなかったのは、65nmで90nmよりさらに絶縁膜を薄くしなければならなかったからではないかと考えられる(IntelはマイクロアーキテクチャをNetburstからCoreへ変えることで、動作クロックを上げずに90nmプロセスより高い性能のプロセッサを提供したわけだが)。ゲート絶縁膜をより薄くすることで、ゲートリーク電流はさらに増えてしまう。
Intelが45nmプロセスから導入したHigh-kメタルゲート技術は、ゲート電極に金属材料を、ゲート絶縁膜にHigh-k材料(ハフニウム系の高誘電率材料)を用いることで、絶縁膜を厚くしつつ、従来以上の電界効果をゲートから得るというものである。絶縁膜を厚くすることでトンネル効果を防ぎ、ゲートリーク電流を大幅に軽減する。IntelによるとHigh-kメタルゲートにより、絶縁膜の厚さを5倍以上にまで戻せたらしい。これにより、非動作時の消費電力が格段に減ることになる。
QX9650のアイドル時の消費電力の低さは、このHigh-kメタルゲートの威力を反映したものだと思うのだが、これをTDPの数字から判断することはできない。QX9650とQX6700の現実に近い消費電力の差を、もっと分かりやすくユーザーに伝える指標が必要なのではないだろうか。
□関連記事
【12月20日】【元麻布】1GB=2,000円時代のメモリ増設を考える【番外編】
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1220/hot520.htm
【11月12日】Intel、45nmプロセスのプロセッサを正式発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1112/intel.htm
【10月29日】【多和田】45nmプロセスでCoreマイクロアーキテクチャをリフレッシュ「Core 2 Extreme QX9650」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1029/tawada114.htm
(2007年12月21日)
[Reported by 元麻布春男]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.