
|
テムザック“援竜”、新潟県で雪害対策性能テスト
 |
株式会社テムザックは1日、新潟県長岡市にある長岡技術科学大学で、同社が開発している大型レスキューロボット「T-52援竜(えんりゅう)」の雪害対策実験、性能テストを実施した。
「T-52援竜」はテムザックが北九州市消防局、独立行政法人消防研究所、京都大学等と開発した大型ロボット。全高約3.5m、幅2.4m、総重量は約5t。
片方の腕に9自由度を備えた大きな双腕が特徴で、片腕で500kg、両腕で1tのものを持ち上げることができる。
全身の自由度は22。移動方式はキャタピラで、走行速度は時速3km。油圧で駆動する。動力源は水冷3気筒直噴エンジン。エンジンで発電するため、燃料があるかぎり動き続けることができる。
当日は、「雪庇(せっぴ)の除去」と、「雪崩による埋没車両からの要救助者を救助する」デモを行なった。雪庇とは崖などで雪が張り出した場所のこと。放置しておくと崩れる危険があるため、崩して除去する必要がある。
 |
 |
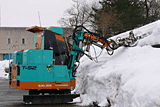 |
| T-52援竜。2004年に発表された | コクピットには金網が張られている | 雪庇に見立てた現場で雪を左右になぎ払う援竜 |
 |
 |
 |
| 除雪作業中の援竜。当初は除雪専用の腕も用意されたがあまり役には立たなかったという | ||
 |
 |
 |
| 援竜は油圧駆動だが、この程度の温度であれば問題なく動く | 【動画】雪庇をなぎ払う援竜(AVI、約16MB) | 【動画】最後にハサミをかみ合わせて、腕に詰まった雪を払い落とす(AVI、約38MB) |
 |
 |
 |
| 雪崩を模した現場で、雪崩に埋もれた車両を救出 | ||
 |
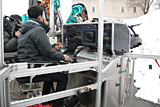 |
 |
| 【動画】車両をち上げて、安全な場所まで移動させる(WMV、約1MB) | 雪崩の場合は二次災害の可能性があるので、遠隔操作を使用を想定 | 人間、車と比較すると改めて援竜の大きさが分かる |
今回の実験・デモは、雪害において援竜がどの程度使えるかどうか、雪に援竜がどのように対応できるかを試すためのもの。
実験について長岡技術科学大学機械系において中心的役割を果たした木村哲也助教授はレスキューロボットの研究者。雪害は毎年あるが、高度技術がないことに不満を持っていたのだという。援竜については「精度が高く多関節。従来の建設機械ではできなかったことができるのではないか。雪国が豊かになるようなロボット技術に取り組んでいきたい」と語った。
また、雪害の専門家である同大の上村靖司(かみむら せいじ)講師は、「雪の問題は簡単なようで難しい。40年間、新しい技術が出ていない。現在は雪崩の危険性が高いところでも人間が作業を行なっている。そこにロボットが入ってくれれば新しい可能性があるのではないか」と期待を語った。
ただ、「明日から被害者が減らせるとも思っていない」という。「ロボットが実際に使えるものになるためのどのように性能アップを図っていくのか、そのための良い題材として雪を使ってもらいたい」と語った。
 |
 |
| 長岡技術科学大学機械系 木村哲也助教授 | 長岡技術科学大学機械系 上村靖司講師 |
たとえば、今回のデモ・実験のためにテムザックは雪を払うための板のようなアタッチメントを作っていたが実際に使ってみるとまったく歯が立たなかったため、通常の爪の腕に戻したのだそうだ。雪害処理の専門家である上村講師によれば、雪庇の処理のためにはむしろ、ノコギリのようなもので雪を羊羹のように切ったほうが良いという。今後、実用までにはさまざまな試行錯誤が続くことになりそうだ。
なお同大学ではこれから世界に先駆けてロボット安全の規格を提案していくために、社会人大学院生を受け容れて人材育成をはかっていくという。援竜についても「安全」という視点で見直し、アドバイスしていく。
テムザック営業開発室長の藤田志朗氏は「援竜は開発機。雪との戦いを通して改良していきたい」と述べた。また今後の援竜型のロボットについては、小型化して小回りの利くものにしたり、あるいは大型化してさらにパワーを持たせたりと、多様化していくのではないかと可能性を語った。
□「T-52援竜」のホームページ
http://www.enryu.jp/
□長岡技術科学大学 機械系
http://mcweb.nagaokaut.ac.jp/
□関連記事
【2004年3月25日】テムザック、大型レスキューロボット「T-52 援竜」公開
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0325/tmsuk.htm
(2006年2月2日)
[Reported by 森山和道]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp お問い合わせに対して、個別にご回答はいたしません。
Copyright (c)2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.