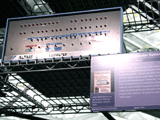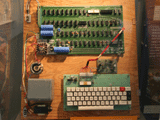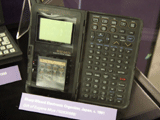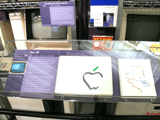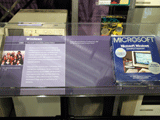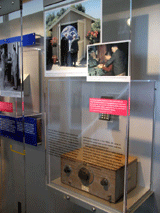|
前回はマイクロプロセッサが生まれたところまでを、写真を中心に紹介した。筆者自身は、学校ではNEACの16bitミニコンを使い、ラインプリンタのキャラクタ重ね打ち階調で絵を描いたりといった事はあるが、当時、計算機室にはTSS端末がほんの数台しかなく、プログラミングをインタラクティブな開発環境で学ぶ、といった環境ではなかった(その後、ワークステーションとX端末にリプレースされたが)。従って、PDPやVAXを学校で利用できたという話を聞くと、懐かしさよりもうらやましさを先に感じる。
PC Watchの編集長はVMSのプロジェクトリーダー、デビッド・カトラー氏を懐かしんで「闘うプログラマー」(日経BP)を読み返したそうだが、VMSがWindows NT 3.1を経てWindows XPへと繋がっていると思うと感慨深いモノだ。もっとも、カトラーの思想はWindows NT 3.51までで、マイクロカーネル思想を捨てた4.0以降はカトラーのOSではない、という意見もあるだろうが……。
さて、前回のレポートで、アナログコンピュータのキャプションにある“オプショナルアンプリファイア”は、オペアンプの事ではないか? との指摘をいただいた。オペアンプとはアナコンで使われた算術用のアンプモジュール(オペレーションアンプ)だが、ここでは「解決すべき問題を組み替える時の“追加の”アンプ」という意味で、Optional Apmlifireという言葉が説明の中に出てきた。本来なら「アルゴリズムを変更する際に、追加のアンプを」と書くべきだったかもしれない。紛らわしい表現だったことをお詫びしたい。
ではマイクロプロセッサの誕生前後から、コンピュータがパーソナルな機械になっていた様子を順に追っていこう。
●コンシューマ市場に向け多用な製品が登場
コンピュータが小型化され、応用範囲が拡がってくると、大幅なコストダウンも可能になってきた。コストダウンが始まると、次にコンピュータ会社が狙うのはコンシューマ市場である。
ミニコンの時代、PCの時代、それぞれにコンシューマ市場への調整が行なわれたが、結局、コンシューマ市場への進出に成功したのは、機能を限定した組み込み用プロセッサのみ。汎用に利用可能なコンピュータがコンシューマに降りてきたのは、大規模LSIで大幅な小型化を果たしたマイクロプロセッサ以降だ。
 |
 |
 |
| '69年に米国の百貨店Neiman Marcusが、得意先向けの商品カタログに掲載したキッチンコンピュータ。コンピュータが小型化したことで、その能力を活かそうと、当時から様々なトライが行なわれていた事が忍ばれる。内部はHoneywell製316ミニコンピュータなので、この時点ではまだマイクロコンピュータではない。0.6MHz動作、16bitで16Kワードのコアメモリを内蔵し、レシピデータの保存と取り出しが可能だった。価格は10,600ドル。キッチン向けのコンピュータは、今でもたまに展示会で提案商品として登場してくる定番コンセプトだ。Microsoftが本社レドモンドに設置しているeHOMEデモルームにも、キッチンコンピュータの提案があった。とはいえ、いまだにキッチンコンピュータが普及しそうな気配はない。ちなみに、写真のキッチンコンピュータも、かつて“実際に売れた”という証拠はどこにもないとか |
特定機能に絞った計算機であれば、古い技術でも十分に造ることができた。電卓はその中でも、もっとも広く使われたアプリケーションだろう。しかしその電卓も、ICを用いた回路の集積が可能になってくると、ソフトウェアを用いて製品開発を行ないたいというニーズが生まれてきた。Intelが日本のビジコンからの依頼で作ったストアードプログラム方式コンピュータの心臓部が、i4004という4bitプロセッサだった。その後、電卓は猛烈な低価格化の波に揉まれつつ、プログラマブル電卓やポケコンなどに発展。シャープやカシオの電子手帳も、元はといえば電卓に端を発したものだ。その延長線上に、現在のザウルスシリーズやカシオペアシリーズがあると思うとなかなか興味深い。米国ではHPのプログラマブル電卓が、「HP 100LX」などのポータブルDOSマシンに発展するなど、商品形態の変遷が国ごとに微妙に違うところが面白い |
電卓の棚から1つピックアップしたのは、HPの腕時計付き計算機、もとい計算機付き腕時計のHP-01。'77年に発売された。アラーム、ストップウォッチ、200年分のカレンダーなど36機能を標準装備。写真は14金を貼ったゴールドモデルだが、ステンレスモデルもある。重量は160g。機能が豊富すぎて、使いこなすには相当に使い込まなければならなかったとか。使われている半導体は実に6個に及び、総数3万8千個のトランジスタで構成されていた。当時の価格は795ドル |
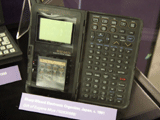 |
 |
 |
| 写真は英語版だが、日本で言うと「PA-7000」に端を発するICカードでの拡張性を備えた電子手帳の親戚と思われる。左下からICカードを挿入すると、その上の透明な部分がタッチパネルとして機能して追加機能を利用できた。当時、筆者はカシオの電子手帳派だったのでほとんど使ったことがない |
PDAが電卓の派生物と言い切ると異論、反論はあるだろうが、汎用コンピュータとして機能と性能を追うのではなく、用途に合わせて作り込んだ製品として登場した点において、機能限定版PCよりも電卓の進化型と考える方が正しいような気がする。写真の右側にはAppleのPDA「Newton」が見える。しかし機能や性能、信頼性を追い求めたPDAよりも、ユーザーが必ず欲しがると証明されている機能に絞って安価に作り、メモリ保護もなくバグ付きアプリの追加ですぐにハングアンプしていたU.S.Roboticsの「Pilot」の方がはるかにヒットした。後付けで「こうだから売れた」とはいくらでも言えるが、マーケットの予測なんて誰にもできはしない良い例である |
“専用機向け組み込みプロセッサ”を使った製品という切り口で言えば、電子タイプライターもその一つ。この製品はソニーが作ったマイクロカセットレコーダと電子タイプライターの複合機。'80年製である。昔のソニー製PC「SMCシリーズ」を使ったことがあるユーザーなら、キーボードのデザインがよく似ていることがわかるだろう。筆者が購入した初めての8bit PCは、実はNECではなくソニーだった。「SMC-70」というCP/Mマシンだが、たぶん実家のどこかにまだあるはず……。ソニーのコンピュータ事業は、こうしたところから始まって、ワープロ、PCへと繋がっていったのか |
●パーソナルな“汎用”コンピュータへの道
用途に応じて必要な機能を作り込み、それに必要なハードウェアを、という緻密な物作りの発想からは、現在のPCのような製品は生まれてこなかったのかもしれない。
「汎用プロセッサが入手しやすくなったから、汎用コンピュータを安価に作っちゃえ」という発想は、余分な能力がコスト的に“もったいない”と感じる民族からは生まれにくい。汎用のコンピュータをたくさん作って安くしようという、アメリカンな合理的発想が、パーソナルコンピュータという箱を生み出したのかな? とも思ったりするのだが。
ともかく、汎用プロセッサを搭載したコンシューマ製品は、実用製品であるとともに、プログラミング能力を持つ人間をミニコン時代よりも多く輩出するようになり、プログラミングをビジネスとする人々を増加させた。
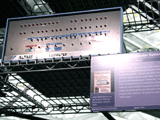 |
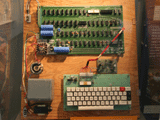 |
 |
| MITSがCPUにIntelの8080を採用したマイコンキット「Altair 8800」を375ドルで'75年4月に出荷した。MITSはこの年の1月にこのキットを発表したが、当時ハーバード大学の学生だったビル・ゲイツ氏は、実機を見ずにBASICインタプリタをプログラム。そのプログラムをポール・アレン氏がMITSに持ち込んでデモすると見事に動作したとか。MITSはそのBASICインタプリタをライセンスしAltair 8800に搭載。直後にゲイツ氏とアレン氏はMicrosoftを設立。Microsoftはその後、日本企業へのBASICインタプリタの売り込みに成功し、さらにIBMとの長期的なパソコン用OSの開発/ライセンス契約を結び飛躍した |
'76年にスティーブ・ジョブズ氏、スティーブ・ウォズニアック氏、ロン・ウェイン氏の3人で設立されたAppleの最初の製品「Apple I」。右の写真はAppleが生まれたジョブズ家のガレージ(現在は別の人が住んでいる)。1ボードマイコンにキーボードも繋ぐことが可能で、木箱などにキーボードと共に収めてパソコンとして使われた。価格は666.66ドル。'75年に開発されたMOSテクノロジ製6502/1MHzを搭載し、オンボード8KB、最大32KBのメモリが利用可能。生産台数は200台で実売数は175台。Briel Computerがレプリカを開発/販売中。Appleはこの後、'77年にApple Iをベースにカラーグラフィック機能を追加し、キーボードや電源をケースに内蔵した「Apple II」を発表。ほぼ同時にCommodoreが「PET 2001」を発表。本格的なパソコン時代が幕を開ける |
●カラーグラフィック機能の発展と応用
「Apple II」を振り返って見ると、Appleが昔から一貫して、ユーザーフレンドリーなコンピュータを作ろうと考えていた事がわかる。Apple IIはコンポジットビデオ出力で、家庭にあるテレビにコンピュータの画面を映し出す事ができたため、購入してテレビに繋げばスグに利用することができた。当時、ややコスト高でも早期からFDDを用意したのも、おそらくはユーザーに簡単にパッケージソフトを利用してもらうためだったと考えられる。
そのApple IIのもうひとつの特長が、カラーグラフィック機能が装備されたこと。Apple II向けには多数のゲームが登場した。グラフィック機能は、コンピュータ好きの少年を惹き付けて止まなかった。高価なビデオカードが、いまだに売れていることを考えると、今も昔もグラフィック機能に対する少年のあこがれは同じということか。
PCの性能の向上やメモリ価格の低下は、コンピュータグラフィックスを身近にし、コンピュータをより簡単で、誰もが使えるものへと押し上げていった。
 |
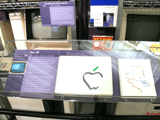 |
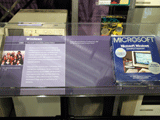 |
| GUIの歴史はXeroxのパロアルト研究センター(PARC)で'72年にアラン・ケイ氏が開発した「Alto」から始まったとされている。当時の価格は32,000ドル。アラン・ケイ氏はDynabookコンセプト(東芝のDynabookもアラン・ケイ氏のDynabookコンセプトに由来している)を、当時の技術で実装しようとしたと後に書物で述べている。子供でも使えるグラフィカルでインタラクティブなコンピュータ環境の実装をAltoで行ない、OSも独自開発の「Smalltalk」が採用されていた。Smalltalkはオブジェクト指向の言語であり開発環境。今では当たり前の、デスクトップ、フォルダ、書類といった概念や、様々なオブジェクトをアイコンとして表現したり、マウスを用いでカーソルを動かす、あるいはEthernetで通信を行なえるなど、画期的な機能/技術が満載されていた。Altoは第3世代の「Alto III」まで開発されるが、商品化されることは無かったという。その後、Altoの成果はドキュメント作成/管理ワークステーションの「Star」へと繋がっていく。Starは日本語化も行なわれ、「JStar」として販売された。スティーブ・ジョブズ氏がPARCを見学した際、Altoのユーザーインターフェイスに感動し、Macintoshの前身であるLisaのプロジェクトを発足させた話は有名 |
'84年と'85年、現在のパソコンで動作しているOSの元になったMac OSとWindowsが登場する。1年遅れのWindowsがタイル型ウィンドウな事からわかるように、(商業的にはともかく)技術面ではAppleの方が数段進んでいたように思う。当時、MicrosoftはIBMとOS/2の開発に取り組んでおり、WindowsはDOSの上にビジュアルな操作環境を追加するだけの役割だったことも、その理由かもしれない。Windowsのパッケージは“Operating Environment”と記されており、独立したOSとして開発されていないことがわかる。Windowsのリリースとほぼ同時期、Mac OS向けにはAldusの「PageMaker」が生まれ、DTPの夜明けが始まっていたのだから、ずいぶんと差がついていたことがわかる。その後、OS/2を共同開発していたIBMと次第に距離を取るようになるにつれ、Windowsは徐々にOS的機能を備えるようになり、Windows 3.0/3.1で両社の溝は決定的なものに。そしてWindows 95ではほぼ独立したOSとなり、晴れて“Operating System”を名乗るようになる。ちなみに'85年はIntelのi386が生まれた年だ |
●PCのポータブル化
機能が固定された専用機では技術的にもコスト的にもポータブル化が容易だったが、プログラミングで汎用的に使えるコンピュータのポータブル化というと難しい側面も多い。
現在のように、システムの絶対的な能力がアプリケーションに対して十分に高ければいいのだが、ほんの少しでも高い性能が欲しい時代、実装の制限が大きくコストも高いポータブル機は、あまり投資効率の良いフォームファクタではないからだ。
コンピュータのパーソナル化が進んだ後、それがポータブルなものになるには4半世紀を必要とした。バッテリ駆動とワイヤレス通信機能により、自由な場所でコンピュータを道具として使えるようになったのは、本当につい最近の事だ。
 |
 |
 |
| Altoと同じくアラン・ケイ氏を中心に'76年に開発した「Notetaker」。Altoのプロジェクトは、GUIを用いたオフィスワークの効率化や一般ユーザーが誰でも使える容易な統合環境の実現だったようだが、企業としてのXeroxはAltoを開発者向けワークステーションとしてしか見ていなかった。が、PARCの技術者は会社の意に沿うように見せかけつつ、理想のコンピュータ開発を追い求めていた。改良を重ねた「Smalltalk-78」を搭載したNotetakerは、Altoの環境をポータブルな筐体に押し込めた初のポータブルワークステーションだが、研究用に開発されただけで、製品としては販売はされなかったようだ。ちなみに重さはバッテリ込みで約22kg、プロセッサは1MHz動作、メモリ128KBを搭載。CRTとFDDを内蔵するほか、マウスを収める場所も付けられている。Notetalerのラゲッジケースに似たスタイルは、その後の初期のポータブル機に影響を与えた |
実際に製品として出荷された初のポータブルコンピュータは、'81年の「Osborne 1」とされている。Z80/4MHzとメモリ 64KBを搭載したCP/Mマシンだった。'81年というと、日本ではNECの「PC-8801」やシャープの「MZ-80B」が発売された年。MZ-80Bが高解像グラフィックモニタを内蔵していたことを考えると“驚愕”というほどコンパクトというわけではないが、なによりこのサイズと重さ(約10.6kg)でポータブル機として製品にしてしまうところに、米国的おおらかさを感じる。価格は1,795ドルとなかなか安価。左右のFDDの下に見える挿入口は、実はFDDを収納するための棚というのも面白い。Osborne 1が参考にしたというNotetakerとは異なりGUIベースではないので、マウスは付属していない |
'83年になるとCompaqが「Compaq Portable」を発売(発表は'82年12月)。プロセッサはIntelの8080/4.77MHz、メモリ128KB(最大640KB)、モニタはグリーン表示の9型で重さは約12.7kg。価格は3,590ドルだった。CompaqはTI出身のロッド・キャニオン氏が'92年に設立した会社で、新しい技術を積極的に採用し、IBM PC互換機どころかIBM自身のシェアまでも奪っていた。'84年、i286を採用したIBM PC/ATが登場するが、その後、IBMはATのアーキテクチャを捨ててPS/2へと進む。しかしCompaqはATアーキテクチャをそのままに、プロセッサやメモリのバスと外部拡張スロットを分離したFlexアーキテクチャを開発し、i386による高速PCを実現。このアーキテクチャはその後の業界標準となった |
 |
 |
 |
| NECが'83年に発売したハンドヘルドPC(ただし'82年にエプソンの「HC-20」(海外では「HX-20」)が発売されているため、世界初というわけではない)。開発元は京都セラミック(現在の京セラ)で、日本ではNEC、米国ではTandy、欧州ではOlivettiがOEM供給を受けて製品化した。重さ1.7kgと抜群に軽量で、プロセッサは8085のCMOS版。クロック周波数は2.4MHz。液晶部分は240×64ドットの解像度だが、CRTに接続すると640×200ドットを表示できた。バッテリは単3電池4本と専用ニッカドパックが利用できた上、内蔵バックアップ電池で電源が落ちた後でも26日以上もメモリ内容が紛失しない仕組みになっていた。当時の価格は138,000円。通信ソフトやワープロを備えており、このマシンにより、原稿を出先で書いて送るモバイラーが生まれた。ただし漢字表示を可能にするROMは別売り |
'85年の「HP Portable Vectra CS」。このころになると、FDDは3.5インチとなり、ディスプレイも液晶パネルに。CPUは8086/7.16MHzのIBM互換。このころのものは現存する可動マシンも多く古さを感じない |
Macintoshの世界では、あまりに重くてラップクラッシャーとも言われた「Mac Portable」があるが(COMDEXにこれを持って行った人もいるらしいが)、個人的に初めて使ったノートタイプのMacは、この「Powerbook Duo 230」(プロセッサは68030/33MHz)。Duoドックに挿入すると、デスクトップとして利用でき、Duoドックから外して持ち出すとモバイルコンピュータになる、という画期的な仕組みを備えていた。ただし日本語環境で使うと猛烈に遅く、初めてのCOMDEX取材にDuo 230と「QuickTake 100」を持たされた筆者は、原稿の入力もままならずに四苦八苦した記憶がある。なにしろ、原稿の中身を考える時間よりDuoが漢字入力処理を行なう方がずっと遅かったぐらいだ。筆者が初めて書籍を執筆した時に使ったi286/16MHz搭載の超薄型(当時)AXマシンの方が、はるかに日本語入力は楽。自前のモバイルPC購入の必要性を強く感じさせた思い出のマシン |
ということで、ポータブルからラップトップ、ラップトップからノートPCへの進化を並べてみた。ノートPC以降の進化に関しては、米国の博物館よりも日本でのコンピュータの歴史を追う方がはるかにいい。Computer History Museumにもラップトップ以降の製品はあまり多く並べられてはいない。
しかし、こうして歴史を振り返ってみると、どのモバイルPCも、なんだかものすごいスーパーコンピュータに見えてこないだろうか? 現在、僕らが使っているノートPCは、超低電圧の低クロックなバージョンでさえ、昔のスーパーコンピュータをはるかに超える計算能力を持っている。
だが、計算能力の向上もいいが、昔の長時間駆動が可能だったハンドヘルドコンピュータが持っていた可搬性も、業界のリーダーやメーカーには忘れないで欲しい。僕は使ったことがないが、聞くところによればエプソンのHC-20はニッカドバッテリのフル充電で50時間は使えたという。
反射型のモノクロ液晶だったり、プロセッサの能力が低かったりと、直接比較することができない事は承知している。しかしあれから20年以上を経て、計算能力は大幅に向上しているのに対して、バッテリ駆動時間はむしろ少なくなっているのだから、どこか進化のバランスが間違っているような気がしてならない。
●おまけ
ちなみに博物館の入り口正面には、パーソナルコンピュータへの歴史を作ったコンピュータとソフトウェアのパッケージが並べられている。そこにはLisaやBe、NeXTなど、商業的には“大”の付く失敗作もあるが、そうした多くの失敗作は、技術者が理想を追ったが故のものだった。
同じ棚にはアドベンチャーゲームの草分け「Zork I」のパッケージもあるが、現在、これはフリーで配布されている。簡単な英文入力を解析してくれるユーザーインターフェイスは、文字だけの世界ながらなかなか斬新なものだった。今からでも遊んでみてはいかがだろう?(Windows XPで動作させるには、ANSIエスケープシーケンスに対応させる必要がある)。
なお、同博物館は2009年を目処に、所蔵物を年代順に並べて展示することを目標としているそうだ。館内には古いコンピュータを修復する部屋もあり、PDP-11の修復を行なうプロジェクトも進行していた。近くを通った際には、訪問してはいかがだろう。場所もハイウェイ101を降りてすぐなので、レンタカー初級者でも迷わずに到着できるだろう。
博物館の後には、シリコンバレー発祥の地と言われる「368 Addison Avenue, Palo Alto」、つまり巨大企業HPが生まれたガレージも久々に訪ねてみた。前回訪問した'98年当時は、別のオーナーが所有し住んでいたが、昨年、HPが所有権を買い取り、現在はリフォーム中。夏が終わる頃には、そのリフォームも終わる予定のようだ。
 |
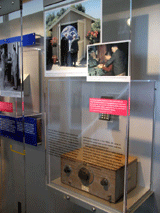 |
| HPの創立者ウィリアム・ヒューレット氏とデビッド・パッカード氏 |
HP最初のプロダクトである「HP Model 200 Audio Oscilator」。'39年、Walt Disneyは8台のModel 200を購入。映画“ファンタジア”の効果音製作に利用し、HPはその名を広く知られるようになったという |
 |
 |
| “シリコンバレーが生まれた場所”と記された記念碑。'89年に設置されたもの |
残念ながらリフォーム工事中だった |
□米Computer History Museumのホームページ(英文)
http://www.computerhistory.org/
□関連記事
【3月2日】【本田】Computer History Museumに見る小型化の歴史(その1)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0302/mobile278.htm
【2004年7月16日】「テレビゲームとデジタル科学展」7月17日から開催
~ENIACからゲームボーイまで一斉に展示
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0716/tvgame.htm
【2001年3月13日】写真で見る歴史的なコンピュータ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20010313/ipsj.htm
□バックナンバー
(2005年3月7日)
[Text by 本田雅一]
PC Watch編集部
pc-watch-info@impress.co.jp
ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
|