 |
|


■元麻布春男の週刊PCホットライン■未来のリビングルームはx86だらけ?
|
前回取り上げたメルコのHD-LANシリーズを引き合いに出すまでもなく、このところ筆者はパーソナル向けのネットワーク接続型ストレージ製品に触れる機会が少なくない。アダプタ方式になっているアイ・オー・データ機器のHDA-i120G/LAN2、ファミリーサーバーとしての機能を備えた富士通のFMFNS-101、パーソナルな価格帯ながら企業向けのNASに近いネットワーク機能を備えたロジテックのLHD-NASなどだ。
これらの製品を取り上げながら、あることに気づいた。それは、製品が高機能・高性能を志向したものと、手軽さや低価格を志向したものに分かれることだ。上で挙げた製品で言うと、FMFNS-101やLHD-NASは前者、HD-LANやHDA-i120G/LAN2は後者に属する。そして、この分類がもう1つの分類と合致することに気づく。それは、前者が用いているプロセッサがx86系、後者が用いているプロセッサが組み込み用RISCプロセッサである、ということだ。
 |
 |
| メルコ HD-LANシリーズ |
アイ・オー・データ機器 HDA-i120G/LAN2 |
 |
 |
| 富士通 FMFNS-101 |
ロジテック LHD-NAS80 |
●組み込み分野でも有利な、x86の豊富な資産
FMFNS-101が用いているのはNational Semiconductor(NS)のGeode GX1、LHD-NASが採用しているのはVIA Technologies(VIA)のEdenプラットフォームであった。一方、HD-LANはMotorolaのPowerPC系組み込み用RISCプロセッサであるMPC8241を、HDA-i120G/LAN2は日立のSH4をそれぞれ用いている。
 |
 |
| National Semiconductorのセットトップボックス向け組み込みCPU「Geode SC1400」 | |
たとえば「ファミリーネットワークステーション」をうたうFMFNS-101は、ネットワークストレージとしての機能以外に、ブロードバンドルータ、無線LANのアクセスポイント、USBポートによるプリントサーバー、PCカードスロットを用いたJPEGファイルの読み取り、家庭向けのグループウェアサーバーなど様々な機能を持つ。こうした多機能性は、x86互換プロセッサに蓄積されたソフトウェア資産と、開発環境無しに実現可能だったかというと、はなはだ疑問だ。
LHD-NASの重要なビルディングブロックであるNASソフトウェアのSynology Filerにしても、ベースとなるのはx86プラットフォームであり、x86互換プロセッサでなければ利用できないビルディングブロックである。LHD-NASに限らず、数十万円クラスのラックマウント型のNASにしても、多くはx86互換プロセッサをベースにしたものが主流となっている。その大きな理由の1つが組み込み用のWindows NTやLinuxの利用だと思われるが。
性能という点では、少なくともストレージデバイスとしての性能を見る限り、x86互換に決定的なアドバンテージがあるわけではない。LHD-NASやFMFNS-101はデータ転送速度という点で、若干上回る印象はあるが、MPC8241を用いたHD-LANもそれに近い性能を示した。だが、これまで触れてこなかったもう1つ別の部分での性能で、x86互換プロセッサとRISCプロセッサの間に大きな差を感じる。それは、設定ユーティリティのレスポンスだ。
上述したいずれの製品も、ブラウザベースの設定ユーティリティを備える。だが、ブラウザから設定項目のリンクをクリックして、画面が更新される速度となると、x86互換プロセッサを用いた製品が圧倒的に速い。これがプロセッサとしての性能差なのか、ソフトウェアの最適化の差なのかは分からない(おそらくは両方なのだろう)が、x86プラットフォームは最も数量が出ることに加え、最も厳しい競争を勝ち抜いてきたものだけに、こうした部分にも利点があることは間違いない。
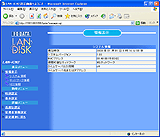 |
 |
| HDA-i120G/LAN2の設定メニュー | FMFNS-101の家庭用グループウェア |
●組み込み用x86の源流はCyrixに
 |
| Cyrix M II-333 |
現在、組み込み用のx86プロセッサとして広く使われているNSとVIAの製品だが、共通するのはCyrixと深いかかわりがある、という点だろう。
NSがCyrixを買収したのは'97年のこと。以来、Cyrix事業をVIAに売却するまで、NSはCyrixの親会社であり、Cyrix製CPUの製造元であった。2000年にCyrix事業をVIAに売却した際も、売却したのはスタンドアロンのプロセッサのみで、統合型のMediaGXは手元に残した。それが現在主力のGeode GX1になり、そして2003年に量産が始まったばかりのGX2へとつながる。0.15μmプロセスで量産されるGX2は最高クロックが366MHzに達し、GX1の2倍の整数演算性能、4倍の浮動小数点演算性能を持つ。消費電力は1W以下(Typical)で、ヒートシンクを必要としない点がPC用のプロセッサと大きく異なる部分だ。
GX1、GX2ともに、メモリインターフェイスやグラフィックスコアを内蔵しており、いわばスタンドアロンのプロセッサに、チップセットのNorth Bridge機能を統合したもの、と考えられる。が、逆に言えば様々なI/O(USB、IDE、UART等)機能のために、South Bridgeチップ(コンパニオンチップ)が欠かせない。そこで、CPUコアにSouth Bridgeチップの機能まで1チップに取り込んだのが、SCシリーズである。現在はGX1コアのものだけだが、いずれはGX2コアをベースにしたものも登場するものと思われる。
SCシリーズの動作周波数は266MHzまで到達しているが、266MHzのx86ではMPEG-2/4やWindows Mediaのエンコーディングにはまだ力不足だ。そこでSCシリーズのコンパニオンチップとしてMultimediaコンパニオンチップ(CS1301/CS1311)が用意される。Philipsが開発したTriMediaアーキテクチャに基づくVLIW CPUで、動作周波数は180MHzあるいは166MHz。アナログオーディオおよびビデオの入出力とSPDIF出力をサポートしている。Multimediaコンパニオンチップがサポートされれば、ファミリーサーバーに新たにAV機能を加えることが可能になるハズだ。
●源流は同じでも、NSとVIAのスタンスは違う
一方、NSからCyrixのスタンドアロンプロセッサ事業を買い取ったVIAだが、現在同社の製品にその直接の後継製品は見当たらない。VIAのスタンドアロンプロセッサ製品であるC3にしても、EdenプラットフォームのCPUであるEden ESPにしても、コアを設計したのは同じくVIAがIDTから買収したCentaur Technologyである。わずかにC3の名称がCyrix IIIにちなんだものであることが、VIAとCyrixのかかわりを物語っているのみだ。
VIAの組み込み用x86プロセッサであるEden ESPは、バスインターフェイス等も含め、電気的には通常のSocket 370用プロセッサと変わりない(物理的にはBGAパッケージを採用しており、実際にSocket 370に挿すことはできないが)。つまり、Geodeのように、組み込み用途向けに追加された機能は特に存在しない。ただ、ファンレスでの運用を前提に、スペックが設定されているのみだ。
したがって、Edenプラットフォームにしても、通常のSocket 370プロセッサに対応した2チップ構成のチップセットが使われており、CPUと合わせて3チップ構成となる。コスト的に1チップとどちらが得なのかは、第三者からは分からない(単純に考えれば1チップの方が得に決まっているが、市場規模/量産規模により、デザイン変更を加えるコストが許されるかどうかが変わる可能性がある)が、実装面積的には不利に違いない。量産規模の極めて大きなPC向けのリソースを徹底的に再利用することがVIAの組み込み向けx86の基本的な戦略で、組み込み用途向けに最適化されたデザインを行なうことを重視するNSとは異なっている。
 |
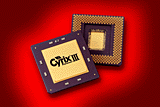 |
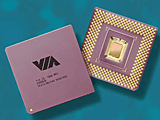 |
| IDT WinChip 2 | VIA Cyrix III | VIA C3 |
●デジタル家電はx86に?
冒頭で触れたように、現時点では組み込み用途に対してx86互換プロセッサはコストの点で必ずしも有利ではない。それが1つの理由となって、応用分野がPC関連商品(x86用のソフトウェア資産が最も活用できる分野)に限定されているものと思われる。
しかし、動画といえばMPEG-2、オーディオといえばMP3という時代はそう遠くない将来終わりを告げ、多数のCODECが乱立する時代がやってきそうだ。すでにMPEG-4、DivX、Windows Media 9など、動画だけでも複数のCODECが有望視されている。こうした時代、特定のCODEC用にハードウェアを作りこむより、汎用性のあるハードウェアの上で多くのソフトウェアCODECを走らせるソリューションが有効になると考えられる。
ひょっとすると将来のデジタル家電には、GeodeやEdenのような組み込み用x86プロセッサが多数使われることになるかもしれない。
□関連記事
【2001年3月26日】VIA、0.15μmプロセスのSocket 370 CPU「C3」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20010326/via.htm
【'99年7月27日】【海外】Cyrix売却後も独自にx86コアを拡張するNational Semiconductor
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990727/kaigai01.htm
【'99年7月9日】【海外】National SemiconductorのワンチップPC“Geode”
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990726/kaigai01.htm
【'99年7月1日】【海外】VIAがCyrix買収で本当に欲しかったものは何か
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990701/kaigai01.htm
【'99年6月30日】VIA、Cyrixのx86CPU事業をNSから買収
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990630/via.htm
(2003年2月13日)
[Text by 元麻布春男]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.

