
 |


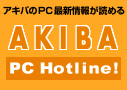 |

|
Pentium 4 2.40GHzを試す
|
IntelからPentium 4プロセッサの最新モデルとなるPentium 4 2.40GHzが発表された。このPentium 4 2.40GHzは、システムバスが400MHzのPentium 4としては最高クロックの製品となる。
先月のCeBITでは、AMDがAthlon XPの最新モデルとなるAthlon XP 2100+(1.73GHz)をリリースしており、両社の最高クロックモデルが出揃ったことになる。本レポートでは、ベンチマークなどの結果を基に、両CPUの性能を考えていきたい。
 |
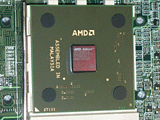 |
| Pentium 4 2.4GHz | Athlon XP 2100+ |
●5月に533MHzに切りかわるPentium 4
既に何度かレポートしているように、Pentium 4のシステムバスは5月に533MHzに切りかわる。OEMメーカー筋の情報によれば、IntelはPentium 4 2.40B GHz、2.26GHzを5月に追加する予定で、両製品ではシステムバスのクロックが533MHzになるという。
3月に開催されたCeBIT 2002( http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/link/cebit02_i.htm )では、システムバス533MHzに対応したチップセットであるIntel 850E、Intel 845G、Intel 845Eを搭載したマザーボードが展示( http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0320/cebit11.htm )されており、これらを搭載したマザーボードも、533MHzベースのPentium 4と同じようなタイミングで登場することになると言う。
今回発表されたPentium 4 2.40GHzは、533MHzへ切りかわる直前のタイミングに登場したシステムバス400MHzの製品となる。CPUコアは1月に発表されたPentium 4 2.20GHzや2A GHzでも利用されていた0.13μmプロセスのNorthwoodコアに基づいている。
さらに今回は300mmウェハという、より大型のウェハで製造されているという。CPUのダイ(要するにチップそのものだ)は、ウェハと呼ばれる円盤を切りわけることで製造されている。これまでは200mmウェハを使って製造されていたのだが、それが直径にして1.5倍となる300mmウェハという、より大型のウェハを利用して製造する工程に切りかえられたというわけだ。
半導体メーカーにとってウェハのサイズを大きくすることは、コストの削減につながる。というのは、300mmウェハにすることで、ウェハあたりにとれるダイ数は240%増、ダイ1つを製造するのにかかるコストは30%減、さらにダイ1つを製造するのに必要な電力や水などは40%も削減できるという。一度に沢山のダイが作れて、1つを製造するのに必要なコストはすくなくて済むというわけだから、半導体メーカーにとっては非常に美味しい。
ただし、300mmウェハで製造するには、既存の200mmウェハのラインを300mmウェハ用の機材で置きかえる必要があり、実際には300mmウェハ用に新しい工場を建設する必要がある。このため、初期投資は膨大で、実際には量産効果がでなければ、あまりメリットがでない。300mmウェハになったからといって、半導体の値段が劇的に下がったりするわけではないので、ユーザーに今すぐメリットがもたらされる話ではない(その証拠に今回のPentium 4 2.40GHzも1,000個ロット時の価格は74,820円と決して安くない)。ただ、将来的にはより高性能なCPUを安価に作れるようになるはずであり、そういう意味ではメリットがないわけではない。
●主要なベンチマークプログラムがバージョンアップ
さて、今回からCPUの評価に利用するベンチマークを切りかえることにした。前回、Pentium 4 2.20GHz、Athlon XP 2000+を評価したときまでは、BAPCO( http://www.bapco.com )のSYSmark2001、MadOnion.comの3DMark2001、id SoftwareのQuake III Arena(timedemo demo1)などを利用していたが、これらのバージョンアップなどにともないSYSmark2001をSYSmark2002へ、3DMark2001を3DMark2001 SE(Second Edition)へ変更し、さらに新たにMadOnion.comのPCMark2002、BAPCOのWebMark2001を追加することとした。
3DMark2001 SEは3DMark2001のマイナーバージョンアップ版で、新たにAdvanced Pixel Shaderのテストが加わったものだ。特にCPUに関する新しいテストが加わったわけではなく、これはバージョンが上がったのにともない変更しただけで、特に結果に対するインパクトはない。
PCMark2002は、MadOnion.com( http://www.madonion.com/ )がリリースしたベンチマークソフトウェアで、CPU、Windowsの2Dグラフィックス、ハードディスクの転送速度など、PCのサブシステム単位の性能を計測するベンチマークだ。オプションとしてDVDビデオの再生性能などを計測することも可能で、以前MadOnion.comがリリースしていたVideo2000の機能も一部採りいれられている。今回は、このPCMark2002のうち、CPU TESTだけを抜きだして実行した。CPU TESTにはJPEG画像のデコード(JPEG decoding)、ファイル圧縮、解凍(Zlib Compression、Zlib Decompression)、テキスト検索(Text Search)、音楽ファイルの変換(Audio Conversion)、3Dジオメトリ演算(3D Vector Calculation)などの処理をCPUに行なわせ、それぞれのスコアと総合スコアが弾きだされる。以前、Ziff-DavisのWinBench 99に含まれていたCPUmark99に近いテストだと考えればいいだろう。
PCMark2002のCPUテストは主にCPUそれ自体の性能を計測しているが、実際のPCのシステムとしての性能はCPUだけでなく、メモリやハードディスクの性能などによって決まる。特に、現代のCPUはチップセットをぬきにしては語ることはできない。そうした意味では、サブシステム単位での性能を見るベンチマークでは不充分で、システム全体の性能を反映するアプリケーションベンチと呼ばれるベンチマークを利用するのがCPUの評価では一般的となっている。
筆者は、アプリケーションベンチとして、4つのベンチを利用する。それが文書やコンテンツを作成するプロダクティビティと呼ばれるアプリケーションでの性能を示すSYSmark2002、3Dでの性能を示す3DMark2002 SEとQuake III Arena、インターネットを利用する環境での性能を示すWebMark2002の4つだ。3DMark2002 SEとQuake III ArenaはPC Watchの読者にはお馴染みだと思うので改めて説明しない。SYSmark2002に関しては後述するとして、ここではWebMark2001について説明しておきたい。
BAPCOのWebMark2001はユーザーがインターネット環境を利用する場合のパフォーマンスを計測するためのベンチマークで、XML、マクロメディアのFlash、Java、SSL、Quicktime、Windows Media Player、Real Playerなどの代表的なインターネット技術やアプリケーションを実行する場合のパフォーマンスを計測する。テストはB2B(Business-to-Business、企業間のEコマースなど)、B2C(Business-to-Consumer、個人ユーザーが企業のWebサイトに接続してEコマースなどを行なう場合)、Intranet Business(ビジネスアプリケーションをイントラネット環境で使う場合のパフォーマンス)の3つの項目が用意されており、アドビシステムズ、マクロメディア、リアルなどの実在のインターネットアプリケーションを利用して性能を計測し、総合スコアを出す。
●Pentium 4への最適化が進んだSYSmark2002という存在
最後にSYSmark2002は、PC業界の標準ベンチマークとなったBAPCOのSYSmark2001の最新バージョンだ。SYSmarkの特徴は、バックグランドタスクをベンチマークの動作に取りこんでいることで、単に1つのアプリケーションを実行するだけでなく、実際にユーザーが利用するのに近い環境をつくりだしている。SYSmarkにはインターネットコンテンツ作成系のアプリケーションを実行して計測するInternet Contents Creationと、オフィスアプリケーションを実行して計測するOffice Productivityという2つの結果が導きだされる。
SYSmark2002は、基本的にはSYSmark2001のバージョンアップ版で、SYSmark2001に較べて含まれるアプリケーションが新しくなっている。
| SYSmark2001 | SYSmark2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォアグランドアプリケーション | サポートOS | Windows 2000/Me | Windows XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーラー | Outlook2000 | Outlook2002
| Officeスイート | Office 2000 | Office XP
| データベース | Access 2000 | Access 2002
| Webブラウザ | Netscape Communicator 6.0 | Netscape Communicator 6.0 |
音声認識 | Dragon Naturally Speaking 5.0 | Dragon Naturally Speaking 5.0 |
フォトレタッチ | Adobe Photoshop 6.0 | Adobe Photoshop 6.01
| 動画編集 | Adobe Premiere 6.0 | Adobe Premiere 6.0 |
Web作成 | Macromedia Dreamweaver 4 | Macromedia Dreamweaver 4 |
Webアニメーション | Macromedia Flash 5 | Macromedia Flash 5 |
動画エンコード | Windows Media Encoder 7.0 | Windows Media Encoder 7.1
| バックグランドアプリケーション | 動画エンコード | Windows Media Encoder 7.0 | Windows Media Encoder 7.1
| ウィルススキャン | McAfee Virus Scan 5.13 | McAfee Virus Scan 5.13 |
ファイル圧縮 | WinZip 8.0 | WinZip 8.0 |
|
主な強化ポイントは標準でWindows XPに対応したこと(従来のSYSmark2001はパッチによる対応)により、Windows XPの機能を活かしたベンチマークが可能になったこと、Officeスイートが最新のOffice XPにバージョンが上がったこと、さらにはPhotoshopのバージョンが上がって6.01になったこと、Windows Media Encoderが7.1にバージョンアップしたことなどがある。大きな変更はWindows XPとOffice XPへの対応であると考えることができるだろう。
さて、このSYSmark2002だが、SYSmark2001とはやや異なる傾向の結果を示している。下記の表はPentium 4 2GHzとAthlon XP 2000+におけるSYSmark2001とSYSmark2002の結果だ。
| Athlon XP/2000+ | Pentium 4/2GHz | |
|---|---|---|
| SYSmark2002 | 213 | 238 |
| SYSmark2001 | 195 | 212 |
| 上昇率 | 9.2% | 12.3% |
| Athlon XP/2000+ | Pentium 4/2GHz | |
|---|---|---|
| SYSmark2002 | 139 | 138 |
| SYSmark2001 | 192 | 162 |
| 下落率 | 27.6% | 14.8% |
Internet Contents Creationではさほど大きな変化はない。SYSmark2001の時にも言われていたように、Pentium 4が優勢という結果になっている。Athlon XPは9.2%アップ、Pentium 4 2GHzは12.3%アップとなっている。注意しなければいけないのは、Office Productivityの方で、Athlon XPが27.6%のスコア下落となっているのに対して、Pentium 4 2GHzは14.8%で納まっており、Athlon XPに較べてPentium 4に有利な結果となっている。
Office Productivityの大きなアップデートはWindows XPとOffice XPへの対応なので、Pentium 4、言いかえればSSE/SSE2命令により最適化されているのだろう。
これにたいして、異議を唱える人もいる。その大きな根拠となっているのが、IntelはBAPCOのメンバーであるのにたいして、AMDはそのメンバーではないため、BAPCOがIntelに有利なベンチマークを作っているということだ。
だが、筆者はそれには同意しない。第一の理由は、BAPCOは独立の非営利企業で、メンバー企業の会費などにより成りたっている。現在のメンバーはC/NET、Compaq、Dell、Hewlett-Packard、IBM、InfoWorld、Intel、Microsoft、VNU Business Publications、ZDNetであり、各企業は会費を払ってメンバーになっている。
メンバーは会費を払いベンチマークを作るプロセスに対して意見を述べることができるとなっており、そのメンバーであるIntelがそのプロセスに対して何らかの意見を述べることはあるだろう(実際にどの程度の関与があるかは外部の人間である筆者にはわからない)。だが、それはメンバーになれば誰にでもできることであり、もし異論があるのであればメンバーになって意見を述べればよいのだ(BAPCOのホームページにはどんな組織でもメンバーになれるとうたわれている)。
第二に、今回のバージョンアップではWindows XPやOffice XPへの対応がメインで、そうしたバージョンアップを進めた結果、こうなったとも考えることができる。
現代のCPUは、こうした活動や、拡張命令に対応するソフトウェアを増やす活動などマーケティングプログラムもすべて引っくるめて製品となっている。(繰り返すようだが実際にIntelが影響を与えたかどうかの真実はわからないが)もし仮にIntelが何らかの影響をあたえたとしても、それはIntelが“上手くやった”ということに過ぎない。
そういう意味ではAMDもBAPCOのメンバーとなって、来るべき次のバージョンではAMDの立場から意見を述べるなり、どこか別の第三者機関と提携して、より優れたベンチマークをだすなどの戦略が必要になってくるだろう。
筆者は日本AMDにこの件を問いあわせてみた。現時点では特に公式なコメントはないようだが、AMDでもSYSmark2002のスコアがSYSmark2001に較べて落ちる件は調査中であるという説明を受けた。今後なにかAMD側からアナウンスがあればお伝えしていきたい。
このように、ベンチマークは1つのスコアだけですべてを表すものではない。現時点ではSYSmark2002は優れたベンチマークであるとは思うが、それだけですべての性能を示しているとは思わない(だからこそ複数のベンチマークをやっているのだ)。
要は、ユーザー側の受けとり方次第だ。例えば、3D性能を何よりも重視するというのであれば、3Dアプリケーションの結果をメインに参考にすればよいし、Office XPをメインに使っているというのであれば、Office Productivityをメインに参考にすればよい。ベンチマークとはそういうものだ、というのを今後こうした記事を読むときなどに頭の片隅にでも置いておいて頂ければ、本レポートに限らず、PC関係の記事をより深く読むことができるだろう。
●やはりPentium 4 2.40GHzは最高の性能を発揮
さて、それでは実際に各ベンチマークの結果を見ていこう。テスト環境では、基本的にCPU、チップセット、メモリ以外のデバイスは同じものを利用している。CPUはPentium 4が1.80A GHz、1.60A GHzを除くmPGA478(いわゆるSocket 478)の全CPU、Athlon XPが2100+~1700+までの各クロック(1.73GHz~1.4GHz)を用意した。
チップセットは、両プラットフォーム共に最高性能を発揮できると思われるものを採用するため、Pentium 4にはIntel 850、Athlon XPにはApollo KT266Aを搭載したマザーボードを用意した。Athlon XPではKT333という選択肢もあったが、プラットフォームがでたばかりでまだ信頼性が確立されていないこと、DDR266でもレイテンシを2-2-2に設定すれば、2.5-3-3のDDR333とあまりパフォーマンスが変わらないことなどを考えて、KT266Aの環境を選択した。
| CPU | Pentium 4 | Athlon XP |
|---|---|---|
| チップセット | Intel 850 | VIA Apollo KT266A |
| マザーボード | Intel D850MDL | EPoX EP-8KHA+ |
| BIOSバージョン | 10A.86A.0020.P08 | 8khi2304(2002/03/04) |
| チップセットドライバ | 3.10.1008(2001/10/8) | 4in1 v4.38 |
| メモリ | Direct RDRAM | DDR SDRAM |
| メモリモジュール | PC800 | PC2100(CL=2) |
| 容量 | 256MB | |
| ビデオチップ | NVIDIA GeForce3(64MB、DDR SDRAM) | |
| ビデオドライバ | NVIDIA Detonator XP(v28.32) | |
| ハードディスク | IBM DTLA-307030 | |
| フォーマット | NTFS | |
| OS | Windows XP Professional | |
なお、全結果は非常に膨大になっているので、グラフには一部のクロックのみ掲載している。そのほかの全ベンチマーク結果については、今回からExcel及びCSV形式ファイルで掲載しているので、興味があるユーザーは別途参考にして欲しい。
また、グラフは公正を期すため、すべて0から始まるグラフに統一している。このため、一部見にくいグラフもあるが、途中から始めると、どちらかが非常に高い性能を発揮しているかのように見えるグラフになってしまう場合もあるので、そうした恣意的な部分を排除するためにわざと0から始めている。予め御了承頂きたい。
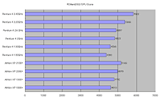 |
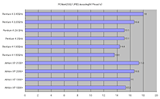 |
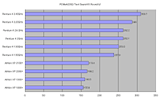 |
| グラフ1 | グラフ2 | グラフ3 |
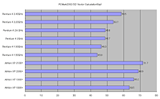 |
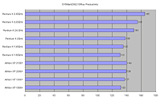 |
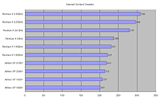 |
| グラフ4 | グラフ5 | グラフ6 |
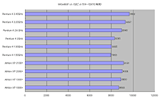 |
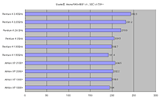 |
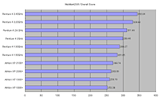 |
| グラフ7 | グラフ8 | グラフ9 |
グラフ2、グラフ3はより詳細なスコアのうちJPEGのデコード(グラフ2)とテキスト検索(グラフ3)、ジオメトリ演算(グラフ4)の結果だ。グラフ2ではAthlon XP 2100+はPentium 4 2.2GHzを上まわったが、グラフ3では逆にPentium 4 1.8GHzも下まわった。このように、同じCPUテストでも得手不得手があるのがわかる。
SYSmark2002だが、Office Productivityでは、Athlon XP 2100+、2000+は、L2キャッシュが256KBのPentium 4 2GHzは上まわったが、512KBのPentium 4 2A GHzは下まわった。こうした結果から、SYSmark2002のOffice Productivityでは大容量のL2キャッシュを効率的に使っていると考えることができるだろう。Internet Contents CreationではAthlon XP 2100+はPentium 4 1.80GHzも下まわった。これは、SYSmark2001の時と同じように、Windows Media Encoder 7.1がAthlon XPのSSE互換機能を認識できないことにも原因がある。
グラフ7(3DMark2001 SE)、グラフ8(Quake III Arena)は3D環境における結果だ。グラフ8(Quake III Arena)においてPentium 4のスコアがよいのは、L2キャッシュの容量が大きいことと、システムバスとメモリの帯域幅がAthlon XPに較べて広いためだ。いわゆる一般的なDirect3Dにおけるパフォーマンスを示す3DMark2001 SEでは、Athlon XP 2100+および2000+はPentium 4 2A GHzを上まわった。
グラフ9(WebMark2001)においてはAthlon XPはあまりふるわなかった。こちらもシステムバスおよびメモリの帯域幅が影響していると考えることができ、こうしたタイプのアプリケーションにおいてはIntel 850のメリットがでていると考えることができるだろう。
すべての結果に共通していることは、ほとんどの結果でPentium 4 2.40GHzが最高性能を発揮しているということだ。Pentium 4 2.40GHzは現時点での最高性能を持つx86プロセッサといっていいだろう。
●第4四半期までは533MHzである必要はあまりない
このように、Pentium 4 2.40GHzは現時点において最高性能を誇っている。だが、既に述べたように5月には同じ2.4GHzながら、システムバスが533MHzとなる2.40B GHzがリリースされる。これは待たなくても良いのだろうか?
実は待つ必要はあまりない。というのも、同時にリリースされるチップセット(Intel 850E、Intel 845E、Intel 845G)のメモリ帯域幅がシステムバスに較べると十分ではないからだ。
Intel 850EはPC800の2チャネルで3.2GB/sec、Intel 845E/GはDDR266の1チャネルで2.1GB/secとなっており、533MHzのシステムバスの帯域幅である4.2GB/secに較べて十分ではない。このため、400MHzのシステムバスである3.2GB/secでも十分なのだ(3.2GBに対して1/3の帯域幅でしかないPC133のIntel 845-SDRAM版が、性能があまり高くなかったことを思いだして欲しい)。
Intelは第4四半期にワークステーション向けにGranite Bayと呼ばれるDDR333が2チャネル(5.4GB/sec)を実現するチップセットを投入する(この他、SiS655、VIAのP4X600とサードパーティも似たような製品を予定している)が、その段階までシステムバス533MHz化のメリットはあまり大きくないのだ。つまり、Granite Bayが登場するまでは、533MHzである意味は将来の投資以外にないわけで、現時点では400MHzベースのPentium 4で特に問題はないだろう。
ところで、今後システムバス400MHzのPentium 4はどうなるのだろうか? 現在のところIntelが公開しているロードマップによれば、第3四半期には2.53GHz(533MHzベース)と2.5GHz(400MHzベース)、第4四半期には2.80GHz(400/533MHzベース)、2003年の第1四半期には3GHz以上(400/533MHzベース)となっており、暫くは並存していくことになりそうだ。そのため、当分は400MHzのプラットフォームでもCPUのアップグレードは可能なわけで、いま買い控える理由は特に見当たらないといっていいだろう。
価格は既に述べたように、1,000個ロット時で74,820円と決して安くないが、少なくとも現時点で最高性能であることは間違いない。最高性能が必要であるユーザーで、予算に余裕があるというのであればPentium 4 2.40GHzはよい選択肢となるだろう。
(2002年4月3日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]