|
|
 主催:全日本カラーラボ協会連合会
主催:全日本カラーラボ協会連合会編集部注:【デジタルカメラ編】に続き【ラボ機器編】を追加しました。
現像・プリントを中心としたラボ(現像所)関係機器を一堂に集めた、異色のイベント「'98ラボシステムショー」が、今年も東京・五反田のTOCで6月17日~19日まで開催された。もともとは、ごく普通の銀塩フィルムを中心としたイベントであったが、ここ数年はデジタル化への移行が顕著。とくに今年は、大手メーカーがデジタルイメージングをメインとした展開を図っており、いよいよこの分野も本格的なデジタル時代に突入した感じだ。
また、今回のラボショーをターゲットに、各フィルムメーカーがデジタルカメラの新製品を発表しており、大半のモデルを、実際に手にとって見ることができた。そのほかにも、近い将来展開される店頭でのデジタルカメラからのプリントサービスシステムなどについても数多く展示されていた。
●コニカ:デジタル現場監督など、最新の業務用デジタルカメラ
コニカはラボショーにあわせて発表した、「Q-M100V」ベースの防水モデル「デジタル現場監督 DG-1」を出品。このモデルは、ネーミングからわかるように工事現場での記録撮影をメインにしたヘビーデューティ指向のもの。工事記録用の写真は国内のカラーフィルム全体の数%を占めるほど大量に消費されており、フィルム式コンパクトカメラでは従来からコニカや富士などが発売している。
昨年には建設省から工事記録へのデジタルカメラの使用が正式に認可された(興味のある方はここを参照)ことから、デジタルカメラでもこのようなモデルが登場したわけだ。
一足先に登場していた「富士フイルム BIG JOB」に比べ、ハウジングタイプではなくボディー自体を防水仕様(JIS7級)にしているため、かなりコンパクト。ちょうど「Q-M100V」の角を角張らせて、若干大きくした程度で、十分持ち歩ける大きさとなっている。デザインはなかなか個性的で、ボディー表面の処理も衝撃を吸収するような素材に改められている。もちろん、ベースは「Q-M100V」なので、機能や画質面は先だってレポートしたとおり、実用十分な実力だ。業務用モデルだけに価格的には135,000円と高価だが、デジタルカメラをヘビーに使いたい人には必見のモデル。
このほか、同社ブースではラボシステム編でレポートしている店頭プリントシステムを使った、主だった機種のプリントサンプルが展示されている。同一シーンでの実写データになっているため、各機種の性能が比較できるようになっていた。このあたりにも今回の「Q-M100V」「デジタル現場監督DG-1」への自信のほどがうかがえるが、実際に実写データを手にとって見ている人は、意外なほど少なかった。
●富士フイルム
富士フイルムは、ラボショーの初日にあわせて発表した、140万画素3倍ズームモデル「DS-330」と、130万画素のレンズ交換式一眼レフ「DS-560/565」などの業務用モデルを出品。これらはそれぞれ、昨年春に発売された「DS-300」と、一昨年発売の「DS-505/515」の後継機だ。
両機に共通した特徴は、基本性能の向上はもちろんだが、新開発の液晶ビューファインダーユニット「LV-D3」(24,800円)と組み合わせることで、カメラ一体型の液晶ディスプレイ付きモデルとして利用できる点にある。残念ながら「DS-560/565」では液晶ファインダーとしては利用できないが、「DS-330」では液晶ファインダーとしてリアルタイム表示も実現している。
このユニットは、ビデオカメラの液晶ビューファインダーのような覗き込むタイプとなっている。目にピッタリとくっつけて使うことができるため、日中屋外など明るい場所でも、画像をきちんと確認できる点が最大のメリット。また、表示品質も上々で、なかなか魅力的なものだった。ちなみに、このユニットは前モデルの「DS-300」でも撮影後の画像確認用としては利用できるが、リアルタイムでのファインダー表示はできないという。
このように各種デジタルカメラが展示されていたわけだが、来場者は現像所やミニラボ関係者など、大半が銀塩フィルム系の人で、デジタルカメラを見ながら「フィルムサイズは35mm?ブローニー?」と平気で質問している人も見受けられた。
●コダック
ただし、他社(ノーリツ鋼機)のブースでは、本機を使った実写デモが行なわれていた。
このモデルは、液晶ディスプレイ付きの150万画素モデルで、ニコンの交換レンズを使った本格的な撮影ができるもの。まだ、米国での製品発表のみで,日本国内での展開や価格も未定という状態。しかし、リリースを見ると、一般の写真ユーザーも意識したものになっているので、国内での価格設定が楽しみだ。
●各社出揃ったデジタルカメラ対応デジタルプリントシステム
「ラボシステムショー」という名称からもわかるように、このイベントのメインはもちろん、現像所やミニラボ(店頭処理タイプのDP店)用の現像・プリント機器だ。
この世界もデジタル化の波が急速な勢いで押し寄せているが、今年の「ラボシステムショー」最大の特徴は、大量処理を前提とした本格的なデジタルプリント用システムが各社から出揃ったところ。つまり、今年発表された新システムの多くは、「デジタルカメラからの大量プリント」への対応を前提とした展開がメインとなっている。
昨年までもデジタルデータのプリント機器は出展されていたわけだが、それらはどちらかというと、少量のプリントなら対応できる程度のものがメインだった。
しかし、今年のシステムは、一台のデジタル対応ラボマシンで、普通のフィルムからも、デジタルデータからもプリントが可能で、処理スピードも従来のフィルム専用タイプに近い大量処理ができるものへと進化している。このようなマシンが今年は、富士フイルム、コニカ、ノーリツ鋼機といった大手ラボ機器メーカーから発表され、各ブースで来場者の注目を浴びていた。ちなみに、ここでいう大量処理というのは、1時間当たり1,000枚単位のプリントを指しており、パーソナルプリンタのスピードとはケタが違う。
もちろん、これらのマシンは、従来と同じくカラー印画紙にプリントするので、従来からのカラープリントと同じ品質を実現している。そのため、デジタルカメラからのプリントでも、データさえしっかりとしたものであれば、通常のフィルムからのプリントと見分けがつかないほど高品位なプリントが得られる。
プリント方式には、インクジェットや昇華型、レーザープリンタなどいろいろあるが、保存性や再現性、作業効率、コストといった点を考えると、このカラー印画紙へのプリントという方式が一番現実的な選択といえる。
さらに、このような本格的なプリントマシンを、従来からのミニラボマシンと同程度のスペースで実現している。この点が、今年発表された各本格派デジタルプリントマシンの最大の特徴だ。このようなマシンが街中のミニラボに導入されていけば、デジタルカメラからのプリントも、銀塩の1時間仕上げのようなスピードが実現できる時代になるだろう。
●富士フイルム、ミニラボ用レーザー露光式高画質プリンタ
サイズ的にもミニラボの店頭に楽に設置でき、一台でフィルムからはもちろん、デジタルデータからのプリントもカバーできる。しかも、価格はフロンティア(3,000万円前後)よりも低価格を実現しているという(現時点では価格は未定)。
●ノーリツ鋼機、現実的なデジタル対応ミニラボシステムを展開
また同社は、セルフサービス型のデジタルプリント受付端末である「デジQ」を出品。これは現在すでに稼働中のデジタルプリント社のマシンとほぼ同じセルフサービス型システムで、ユーザー自身が店頭のマシンにメモリーカードやMOなどでデータを持ち込んでプリントするもの。このマシンには、昇華型プリンタ(プリントサイズはキャビネ判程度)が内蔵されており、その場でプリントすることができるほか、同社のデジタルラボマシンにネット経由でデータを転送して、カラー印画紙でのプリントもできる点が大きな特徴だ。
これに近い考え方のセルフサービス型デジタルプリントシステムは、コダックブースでも出品されていたが、こちらはA4判の昇華型プリンタを内蔵しており、出力はA4判のみ。「デジQ」との決定的な違いは、マシン本体に決算機能が備わっていないところだ。
●コニカ、手軽にデジタルプリントができる本格システム
同社ブースでは、この「QD-21」を使った、近未来のデジタル・ミニラボ店をイメージしたスペースも設けられており、そのカウンター上には大型液晶ディスプレイとVAIOが設置されていたのが印象的だった。
●来るべきデジタル時代への布石
今回のラボショーで出品された新システムは、すぐに発売されるというわけではなく、今年の年末あたりから市場に導入される機器だ。そのため、すぐにミニラボなどで、デジタルカメラからのプリントができる時代になるというわけではない。また、現実的にはまだまだデジタルカメラからのプリントサービスは一般的なものではない。さらに、残念ながら、デジタルカメラからのプリントだけでは現時点では採算がとれない。
当然、各社とも、これらのデジタルプリントマシンを、デジタルカメラからのプリント専用に作っているわけではない。むしろ、当面はかなりの量を占めるカラーネガフィルからのプリントでの画質向上を狙った機能を付加することで、市場への普及を図っているのが現状だ。
これらのラボ用マシンは、数百万から数千万円もするため、一度導入してしまうと、そう簡単に買い換えられるようなシロモノではない。それだけに、各社ともデジタルカメラが今後も普及し、そのプリント需要を見越した展開を図っているわけだ。もちろん、普通のカメラ店やミニラボに導入されれば、デジタルカメラからのプリントを、いちいち自分でしなくてもラボに頼めばいい時代になる。また、そうなればパソコンを使っていない人でも安心してデジタルカメラを、コンパクトカメラと同じ感覚で使えるようになる。その意味で、デジタルカメラからのプリント環境が整うことは、そのまま、デジタルカメラ普及のカギにもなる。
ただし、そのときに問題になるのは、これらを扱うカメラ店やミニラボ店などが、意外なほど、デジタルに対しての知識がないことだ。写真という産業自体、十年一日のごとく、のんびりと進んできたのだから、ある意味では仕方のないことかもしれない。だが、今回のような業務系の写真関係イベントでの来場者の反応を見ていると、個人的には一抹の不安を感じざるを得ない。デジタルの時代に、写真業界はこれまでと同じ業態で、21世紀を無事迎えられるのだろうかと……。
□'98ラボシステムショーのホームページ
('98/6/22)
[Reported by 山田久美夫]
【デジタルカメラ編】
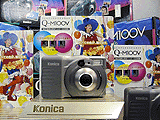 また、同社はラボショーにあわせて発売した「Q-M100V」のデモも、行なっていた。
また、同社はラボショーにあわせて発売した「Q-M100V」のデモも、行なっていた。



 このほかにも、まだ発売されていない「FinePix500」や「Clip-it50」なども出品されていた。
このほかにも、まだ発売されていない「FinePix500」や「Clip-it50」なども出品されていた。

 コダックは、とくにデジタルカメラ用のコーナーは設けておらず、セルフサービス式プリンタのうえに「DC260」が無造作においてある程度。また、ラボショー初日に発表された、ニコンのAPS一眼レフ「プロネア」ベースの150万画素のデジタル一眼レフ「DSC-315」(詳細はこちら)も展示されてはいたが、アクリル越しで,製品名のみという寂しい状態だった。
コダックは、とくにデジタルカメラ用のコーナーは設けておらず、セルフサービス式プリンタのうえに「DC260」が無造作においてある程度。また、ラボショー初日に発表された、ニコンのAPS一眼レフ「プロネア」ベースの150万画素のデジタル一眼レフ「DSC-315」(詳細はこちら)も展示されてはいたが、アクリル越しで,製品名のみという寂しい状態だった。
【ラボ機器編】
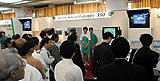 富士フイルムは、一昨年秋に発表された同社のデジタルプリントサービスの中核である大型のデジタルプリントマシン「フロンティア」と同じ技術を使った、ミニラボ対応マシン「フロンティア350」を発表。
富士フイルムは、一昨年秋に発表された同社のデジタルプリントサービスの中核である大型のデジタルプリントマシン「フロンティア」と同じ技術を使った、ミニラボ対応マシン「フロンティア350」を発表。

 ノーリツ鋼機(世界で初めてミニラボシステムを開発し、世界シェアで50%近いといわれるラボ業界の大手メーカー)も、「QCC-2701」という400dpiのミニラボタイプのデジタルプリントマシンを出品。それと同時に、MacintoshやWindowsマシン上からデジタルプリンタを集中制御できる専用ソフトウエアも出品しており、これを使えば、デジタルカメラからの同時プリントなどもごく簡単な操作でできるシステムを構築していた。
ノーリツ鋼機(世界で初めてミニラボシステムを開発し、世界シェアで50%近いといわれるラボ業界の大手メーカー)も、「QCC-2701」という400dpiのミニラボタイプのデジタルプリントマシンを出品。それと同時に、MacintoshやWindowsマシン上からデジタルプリンタを集中制御できる専用ソフトウエアも出品しており、これを使えば、デジタルカメラからの同時プリントなどもごく簡単な操作でできるシステムを構築していた。
 コニカは、今春のアメリカのPMAで発表したデジタルプリントシステム「QD-21」(価格未定)を国内で発表。この製品も従来のミニラボマシンと同じ設置面積を実現している。また、マシン本体に直接メモリーカードを挿すことができ、周辺機器の追加なしに、デジタルカメラからのデータを手軽にプリントできるという大きな特徴を持っている。これなら、デジタルカメラやパソコンの知識に乏しいミニラボでも、安心してデジタルカメラのプリントに対応できそうだ。
コニカは、今春のアメリカのPMAで発表したデジタルプリントシステム「QD-21」(価格未定)を国内で発表。この製品も従来のミニラボマシンと同じ設置面積を実現している。また、マシン本体に直接メモリーカードを挿すことができ、周辺機器の追加なしに、デジタルカメラからのデータを手軽にプリントできるという大きな特徴を持っている。これなら、デジタルカメラやパソコンの知識に乏しいミニラボでも、安心してデジタルカメラのプリントに対応できそうだ。
http://www4.mediagalaxy.co.jp/photo/labo/labo.html
【PC Watchホームページ】
ウォッチ編集部内PC Watch担当
pc-watch-info@impress.co.jp