 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■イスラエルから発信されるIntelの次世代CPUテクノロジー |
●北イスラエルに位置するIntelの設計センター
Intelは、イスラエル北部の都市ハイファ(Haifa)にある開発施設「Haifa Design Centre(ハイファデザインセンター)」で、同センターのCPU開発の基本戦略を説明した。同デザインセンターは、IntelのMobility Groupの元で、多くのモバイル向けCPUを開発してきた。その中には、「0.25μm版MMX Pentium(Tillamook:ティラムーク)」「Pentium M(Baniasバニアス/Dothanドタン)」「Core Duo(Yonah:ヨナ)」、「Core Microarchitecture(Core MA)」が含まれる。また、2010年の次々世代マイクロアーキテクチャ「Sandy Bridge(サンディブリッジ)」も、ここで開発されているという。
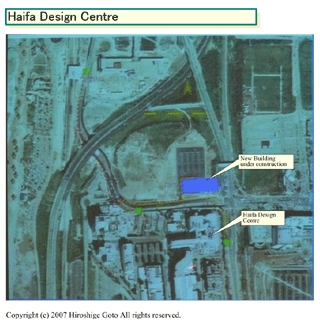 |
| ハイファデザインセンター ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
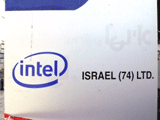 |
 |
| Intelイスラエルの看板 | センター外観 |
ハイファデザインセンターのCPU開発の焦点は、消費電力を引き下げることにある。TDP(Thermal Design Power:熱設計消費電力)を下げることはもちろんだが、平均消費電力の削減にフォーカスしているという。そのため、CPUのアイドル時のリーク電流(Leakage)を低減する技術を開発してきた。
そして、同センターの省電力技術は、ちょうど時代に合致した。ノートPCだけでなく、デスクトップPCでもTDPだけでなく、アイドル時の電力消費の削減が求められるようになったためだ。サーバーでも、コンピュート密度を高めるために電力削減が急務となっており、同センターの開発したCore MAが全ての市場の要求に見合うようになった。
また、電力削減と同時に、IntelはTDP枠の中で最大限にパフォーマンスを発揮するためにターボモードの適用を拡張して行くという。Intelが今後のCPUで実装しようとしているターボモードは、Penrynの説明であった、1つのCPUコアがアイドル状態で、もう片方がビジーな状態に限定されるものではない。室温が規格以下の時やプラットフォームの温度が低い時など、さまざまな機会を捉えて周波数をアップするという。
ハイファデザインセンターのCPUに実装されたこれらの技術は、Intel全体に移転されつつある。
●ますます強まる電力削減への圧力
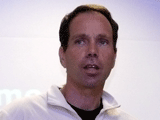 |
| Ron Friedman(ロン・フリードマン)氏 |
IntelのRon Friedman(ロン・フリードマン)氏(Vice President, General Manager, Mobile Microprocessors Group)は、同センターの産み出したPentium M(Banias:バニアス)の目的は、上がる一方だったモバイルCPUのTDPカーブを“曲げる”ことにあったと説明する。同じ25WのTDPなら、Pentium 4(NetBurst)マイクロアーキテクチャよりもよりパフォーマンスを高くする。そして、Pentium 4では実現できなかった5Wレベルで現実的なパフォーマンスの動作を実現する。
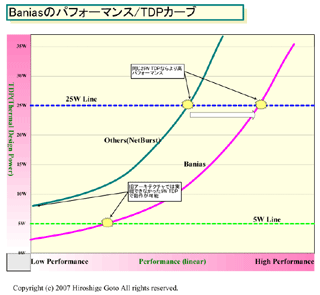 |
| Baniasのパフォーマンス/TDP ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
Friedman氏は、同センターがモバイル向けプロセッサ開発からスタートしたが、現在は全ての市場をカバーしていると説明。その理由として、消費電力が全ての市場で重要になったと指摘した。
例えば、デスクトップでは、エンターテイメントPCとしてリビングルームにフィットさせるためにSFF(Small Form Factor)に納められる低TDP化への圧力が高まっている。これは、日本では以前から当たり前の話だが、日本以外の市場でもようやくそうした動きが活発化している。
そして、新たな要素として、今年(2007年)からアイドル時の電力消費の削減も求められるようになったという。
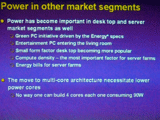 |
| デスクトップ市場に影響を与えている要素 |
「デスクトップ市場に影響を与えているもう1つの要素は、グリーンPCイニシアチブ群だ。数種類のイニシアチブが、低消費電力で環境に優しいコンピューティングを推進しており、その1つが『Energy Star』スペックだ。
Energy Starは、さまざまなコンピューティングプラットフォームの電力消費を規定している。多くの政府機関や企業が、「OK、もしデスクトップやサーバー、ノートPCを我々に売りたいのなら、Energy Starスペックに合致する必要がある。そうでなければ、少量しか買わないだろう」と言っている。そのため、グリーンPCイニシアチブは、デスクトップにとって非常に重要な電力削減の要素となっている。
SFFへの流れは低TDPを推進する要素となっている。しかし、(デスクトップPCの)アイドル電力に関しては、明確にEnergy Starが大きな推進力となっている」とFriedman氏は説明する。
●Energy Star 4.0がデスクトップのアイドル電力削減をけん引
Energy Starは、米国環境保護局(EPA)と米国エネルギー省(DOE)が推進する電子機器向け省電力プログラムだ。元々は、IntelによるSL Enhanced 486の開発と同期して産まれた。強制力は持たないにもかかわらず、米国では大きな影響力を持っている。なぜなら、米国の政府機関の多くが、原則としてEnergy Starに準拠した機器を購入するためだ。米政府機関は世界のコンピュータ市場最大の顧客であるため、PCメーカーに与える影響は大きい。そして、今年(2007年)7月に発効した新バージョンのEnergy Star 4.0では、PCのアイドル時の消費電力について次のように規定された。
Energy Star 4.0では、デスクトップPCは3カテゴリに分けられ、それぞれアイドル電力が決められている。
カテゴリAがシングルコア、シングルプロセッサシステムで、アイドル電力は50W以下。
カテゴリBがマルチコアまたはマルチプロセッサで1GB以上のシステムメモリを備えるシステムで、アイドル電力は65W以下。
カテゴリCが、マルチコアまたはマルチプロセッサで128MB以上の専用ビデオメモリを持つGPUを備え、さらに、次の3つの特徴のうち2つを備える。2GB以上のシステムメモリ、TVチューナまたはHD解像度のビデオキャプチャ機能、2台以上のHDD。アイドル電力は95W以下。
つまり、Energy Star 4.0に準拠させるためには、CPUベンダーはマルチコアのオフィス向けデスクトップPCのアイドル電力を65Wに抑える必要がある。システム全体で65Wなので、CPUはラフに言って20W程度かそれ以下に持ってくる必要があると推定される。そのため、デスクトップCPUでは、アイドル時の電力低減が大きな課題になっている。
●平均消費電力を大きく削減して来たイスラエルCPU
ハイファデザインセンターの設計が、こうした環境にフィットするのは、同センターがアイドル時の消費電力の削減に注力して来たからだ。同センター設計のCore MAなどは、低いTDPばかりが注目されがちだが、実際には平均消費電力の削減の方が目覚ましいという。
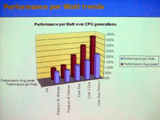 |
| 【図】パフォーマンス/ワットのトレンド |
右が、Friedman氏が示した図で、TDPに対する性能を示すパフォーマンス/ワットと、平均の電力消費に対する性能を示すパフォーマンス/平均電力の伸びを示している。どちらも、Pentium 4からBaniasへの移行による向上分を100%として、それ以降のハイファデザインセンター設計CPUの世代間の伸張を示している。Penrynではパフォーマンス/ワットは200%の伸びであるのに、パフォーマンス/平均電力は350%も伸びている。相対値だが、これまでの5世代で、平均消費電力の削減の比率の方が大きかったことがよくわかる。
Penrynで平均消費電力を大きく削減できた理由は、Penrynの各動作ステイトでの消費電力の内訳を見てみるとよくわかる。下の図の左端は最高周波数モード(High Frequency Mode)時、左から2つ目は低周波数モード(Low Frequency Mode)時、3つ目がPentium Mまでのスリープステイトである「Deeper Sleep State」時、右端がPenrynで実装された「Deep Power Down(C6)」ステイト時を示している。消費電力の中の赤い部分はトランジスタの動作で発生するアクティブ成分、グリーンの部分はトランジスタから漏れるリーク電流(Leakage)によるスタティック成分だ。
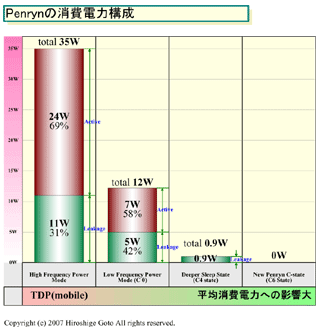 |
| Penrynの消費電力構成 ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
CPUがスリープ状態に入ると、トランジスタはOFFされるため、電力消費はリーク電流によるものだけになる。そして、目立つのは、Penrynでは右端のステイト時の電力が0Wになっている点だ。厳密には0Wではなく、0Wに近い超低消費電力という意味だ。
ほとんどのPC向けアプリケーションでは、使用時間のほとんどでCPUがアイドル状態にある。そのため、アイドル状態の電力消費を抑えると、平均消費電力を引き下げることができるとFriedman氏は説明する。
図を見るとわかる通り、Penrynでもアクティブ時のスタティック成分も膨大な電力消費となっている。TDPである35Wのうち31%の11Wがリーク電流による。現在の高パフォーマンスCPUでは、TDPのうち1/3以上、多い場合は半分程度をリーク電流が占めるが、Penrynでも、その点は変わっていない。そのため、アクティブ時のリーク電流を減らすところに注力すれば、Penrynでも、もっとTDPを下げる余地があるように見える。しかし、Friedman氏は、スリープ時の低消費電力化の方に、よりフォーカスすることを示唆する。
「CPUの全体の時間のうち、高周波数モード、低周波数モード、スリープステイトそれぞれが占める割合を考える必要がある。また、バッテリ駆動時間に最適化するなら、各省電力ステイトがどれだけの割合になるかも、考えなければならない。単純に電力を減らすのではない。多分、ここ(高周波数モード)は、全体の時間のうち5%しか占めないだろう」
もちろん、モバイルとデスクトップ&サーバーでは、アイドル時の制御も話が違ってくる。しかし、現在のグリーンPCのトレンドが示しているのは、デスクトップでもより積極的なモバイルライクなアイドル電力制御が重要になってくることだ。
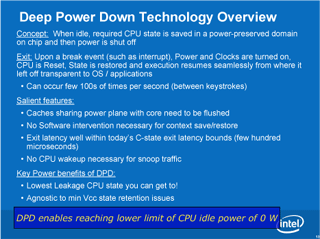 |
| Deep Power Downテクノロジーの概要 |
●クアッドコアCPUの平均消費電力は11Wレベルに
下が、Friedman氏が示したデスクトップCPUのアイドル時の消費電力のトレンドだ。
「2007年に(アイドル電力が)大きく減っているのは、Energy Starスペックが発効したからだ。70Wから10~20Wへと減らした。しかし、同じペースで(デスクトップPCの)アイドル電力を削減することはできないだろう。2005年には、誰もデスクトップのアイドル電力には注意を払っていなかったために、電力が大きかった。だから、大きな削減ができた。しかし、これから先のアイドル電力の削減は、より厳しくなって行くだろう。
2008年と2009年については予想で、(Energy Star)スペックがもっと低くなる可能性すらある。しかし、低消費電力化が進んで行くと、それ以上、省電力にすることが難しいポイントが来る。
また、図ではクアッドコアとデュアルコアが交差しているが、この図は厳密なものではない。基本的には、デュアルコアとクアッドコアは、どちらも同じレベルのアイドル電力、おそらく11W程度に近づいて行くだろう」
図中の2008年と2009年は、Intelのオレゴン州ヒルズボロのデザインセンターで設計している「Nehalem(ネハーレン)」が目指さなければならないアイドル電力を示している。このことは、NehalemのデスクトップCPUで、かなり積極的なアイドル電力削減が図られることを示唆している。
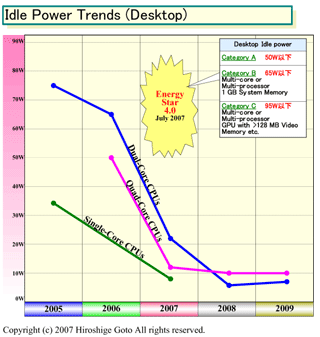 |
| アイドルパワーのトレンド ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
●C6ステイトのために独立電源のSRAMを実装したPenryn
モバイルでのPenrynのアイドル時の消費電力が極めて低い理由は、Penrynから実装された「Deep Power Down C6」ステイトにある。C6によって、PenrynではCPUが待機時の電力を大幅に下げることが可能になった。
C6ステイトが極端に消費電力を減らすことができる秘密は、CPUのほとんどの部分に供給する電圧を従来のCPUより低く下げられる点にある。なぜなら、C6ステイトでは、CPUコアのステイトを保持できるだけの電圧をかける必要がないからだ。これまでは、CPUコア内のレジスタなどにステイトを保持できる電圧レベルが、CPUコアの電圧を下げる際の下限となっていた。
そこで、PenrynではCPUの中にCPUコアのステイトを待避させる独立電源のSRAM領域を実装。CPU全体の電圧を落としても、CPUステイトをCPU内に保持できるようにした。わかりやすく例えれば、非常灯をつけることで、メインの照明を極端に暗くすることができるようになったようなものだ。
下の図がPenrynの省電力ステイトだ。ステイトはC1からC6まで、細かな段階に分かれていて、下の図の右へ行けば行くほど電力消費が少なくなる。しかし、低リーク電流のトレードオフとしてアクティブ状態への復帰にかかる時間(Wakeup time)が長くなる。「CPUがスリープした状態の電力を削減するためにしなければならないことは、リーク電流を削減しながら速いレスポンスタイムを得られるようにすることだ」とFriedman氏は省電力ステイト開発のポイントを説明する。実際、Intelイスラエルのデザインセンターは、現実的なウエイクアップタイムの中で、より少ないリーク電流を実現するために新しい省電力ステイタスを開発して来た。C6はその最新版だ。
Penrynでは、このC6と、ターボモードである「Enhanced Dynamic Acceleration Technology(EDAT)」によって、アイドル電力を抑えつつ、ピークパフォーマンスを引き上げる。そして、その思想は、この先のCPUにも受け継がれて行くことが明らかになった。次の記事では、「Silverthorne(シルバーソーン)」プロセッサのキーテクノロジでもあるC6の詳細と、Nehalem世代で拡張されるターボモードの展開について紹介したい。
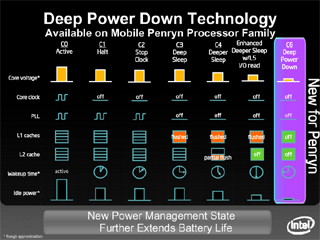 |
| PenrynファミリーにおけるDeep Power Downテクノロジー |
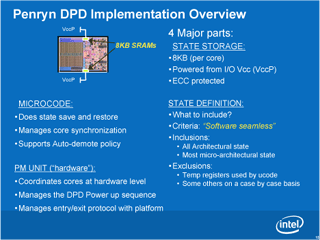 |
| PenrynのDeep Power Down組み込みの概要 |
□関連記事
【11月30日】Core 2 Duoの故郷を報道陣に公開
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1130/intel.htm
【11月16日】【海外】Intelが新製品発表で“45nmプロセス”を前面に押し出した理由
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1116/kaigai401.htm
【11月9日】【海外】2008年中に95%をデュアルコアにするIntel CPUロードマップの秘密
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1109/kaigai399.htm
(2007年12月11日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.