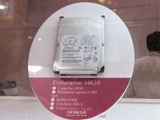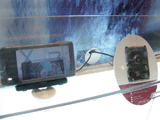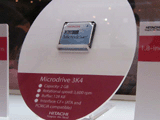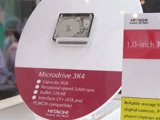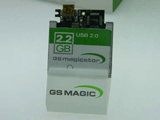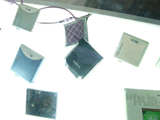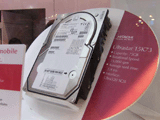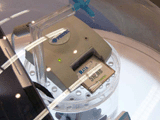|
1インチ以下の超小型HDDの戦いが激化
|
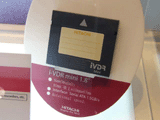 |
| 1.8インチHDDを利用するiVDR mini。アイ・オー・データ機器から容量20GBのiVDR miniメディアと、iVDR mini対応USBアダプタが発売されている |
Taipei International Convention Center
会期:6月1日~5日(現地時間)
ストレージはデータやプログラムを記録する役割を果たす、PCにとって必要不可欠な存在である。ストレージの代表がHDDであり、より大容量に、より高速にと進化を続けてきた。そこでここでは、COMPUTEX TAIPEIで見つけたストレージ関係の展示の中から、特に注目したい製品を取り上げる。
●iVDRに関する展示を行なっていた日立GST
日立GSTのブースでは、iVDRに関する展示が行なわれていた。iVDRとは、Information Versatile Disk for Removable usageの略で、AV機器からPCまで幅広い用途に対応したリムーバブルHDD規格だ。
iVDR規格は2002年3月に設立されたiVDRコンソーシアムによって策定されており、2.5インチHDDを利用するiVDRとiVDR Parallel、1.8インチHDDを利用するiVDR mini、1インチHDDを利用するiVDR microの4種類が規定されている(iVDR microは暫定仕様)。iVDR Parallelのみインターフェイスとして、パラレルATAを採用するが、それ以外はSerial ATAを採用する。
しかし、iVDRコンソーシアムができて、2年以上が経過したが、現時点で発売されているiVDR対応製品は、アイ・オー・データ機器のUSB 2.0/1.1アダプタと、20GBのiVDR miniメディアのみである。iVDRは本来、PCだけでなく家電でも広く使われることを目指して誕生した規格であり、対応機器が出揃わないと、それらの機器の間で自由にデータをやりとりできるという、iVDRのメリットが活かされない。
日立GSTのブースに展示されていたiVDR関連製品も、iVDR miniおよびiVDRメディアと、iVDR mini対応ドライブ程度で、あまり目新しいものはなかった。そこで、担当者にiVDRの今後について尋ねたところ、「現在iVDRコンソーシアムに属する企業を中心にさまざまな検討を行なっている段階なので、iVDRが本格的に広がるのは来年以降になると思います」というコメントをもらった。
こうした製品は、鶏と卵の関係にも似ており、普及しないと使い道が広がらず、使い道がないと普及しにくい。日本では、リムーバブルHDD自体が今まであまり成功してこなかったという事情もあり、iVDRがどこまで普及するかは全くの未知数であるが、今後に期待したい。
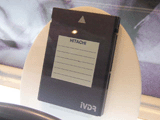 |
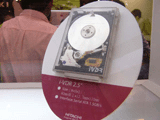 |
| 2.5インチHDDを利用するiVDR。こちらはまだ対応機器は発売されていない | iVDRのトランスルーセントサンプル。HDDがぴったり内部に収まっており、サイズ的にはギリギリであることがわかる |
 |
 |
| iVDR mini対応ドライブ。USB経由でPCに接続してアクセスが可能だ | 写真中央のマルチメディアプレーヤーは、隣に並んでいるiVDR miniドライブを接続できる |
●2.5インチHDDの大容量化と高速化は?
2.5インチHDDは、主にノートPC用HDDとして使われている。9.5mm厚2.5インチHDDの最大容量はしばらく80GBで停滞していたが、2004年4月に東芝から容量100GBを実現した2.5インチHDD「Aries」が発表されたことで、ようやく100GBの大台に届いた。Ariesは、現在サンプル出荷が開始された段階とのことで、実際にノートPCに搭載されるのはもうしばらく先になるようだ。100GB品では東芝の先行を許した日立GSTも、近日中に100GB品を投入する予定とのことだ。
また、高速化については、日立GSTの「Travelstar 7K60」が、2.5インチHDDとしては現時点で唯一7,200rpmを実現しており、一歩先んじている。
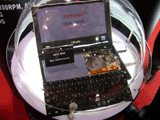 |
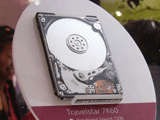 |
| 東芝の2.5インチHDD「Aries」。容量は100GBで、2.5インチHDDとしては現時点で最大容量を誇る。ただし、回転数は4,200rpmである。サンプル出荷は5月から開始されているが、量産出荷はもう少し先になるようだ | 7,200rpmという高回転数を実現した日立GSTの「Travelstar 7K60」。容量は60GB品のみだが、2.5インチHDDでは最速を誇る |
●耐衝撃/耐振動性、利用可能温度範囲を広げて車載用途を狙う2.5インチHDD
2.5インチHDDのノートPC以外の使い道として、最近脚光を浴びているのが車載用途である。HDD搭載カーナビゲーションシステムは、地図データとしてDVD-ROMを利用するカーナビゲーションシステムに比べて、容量が大きく、データの転送速度が速いことがメリットだ。
しかし、車載用途では、振動が激しく、温度も高温や低温にさらされやすい。そこで、日立GST、東芝とも、耐衝撃性や耐振動性を高め、利用可能温度を広げた車載用HDDを投入している。COMPUTEX会場でも、東芝がファームウェアの改良によって、耐振動性を高めた2.5インチHDDのデモを行なっていたほか、日立GSTの車載用2.5インチHDD「Endurastar」も展示されていた。
 |
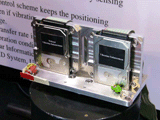 |
| 東芝の2.5インチHDDの耐振動性を示すデモ。左が振動対策をしていない通常の製品で、右が振動対策が施された製品。HDDからの動画再生中に振動を与えると、左の動画はときおりコマ落ちするのに対し、右の動画はとぎれることなく再生される | 左が通常のHDD。右が振動対策済みのHDD。この振動対策は機械的な改良ではなく、ファームウェアの改良によって実現されているという |
●1.8インチや1インチといった超小型HDD分野での戦いが激化
iPodに代表されるポータブルオーディオプレーヤーでは、1.8インチHDDや1インチHDDといった超小型HDDを搭載する製品が増えている。また、今後はいつでも動画の再生が楽しめるポータブルビデオプレーヤーの普及も予想される。こうしたデバイスの実現には、小型で大容量なHDDが欠かせない。1.8インチHDDは、東芝や日立GSTなどが製造しているが、日立GSTの製品は、2.5インチHDDとコネクタ形状が同じであるため、2.5インチHDDの代わりにも使えることが特徴だ。
1.8インチより小さい1インチHDDは、日立GSTの「Microdrive」シリーズが有名だが、2002年に設立されたベンチャー企業のGS Magicstorが、1インチHDDの製造を開始することを表明し話題を呼んだ。
GS Magicstorの1インチHDDは、すでに2.2GB品が量産されているが、COMPUTEX TAIPEI 2004のGS Magicstorブースには4.4GB品が展示されていた。説明員によると、4.4GB品の量産出荷は2カ月後を予定しているという。
日立GSTのMicrodriveの現時点での最大容量は4GBであり、GS Magicstorから4.4GB品が登場すると容量的には負けてしまうことになる。しかし、Microdriveも今年年内により大容量化した製品を投入する予定とのことだ。具体的な容量は明らかにされなかったが、おそらく6GB程度になると予想される。
東芝は1インチHDDを製造していないが、その代わりさらに小さい0.85インチHDDの開発に成功している。0.85インチHDDは、世界最小のHDDとしてギネスブックにも掲載された製品だが、現在はサンプル出荷中である。1インチHDDの製造にも高度な技術が必要だが、さらにサイズが小さくなった0.85インチHDDは、さらに量産が難しくなる。
しかし、GS Magicstorは、1インチHDDの製造だけでは飽きたらず、0.85インチHDD市場にも参入するようだ。GS Magicstorブースには、東芝と同じ0.85インチHDDのモックアップが展示されていた。
GS Magicstorの説明員によると、0.85インチHDDは2005年第1四半期の出荷を予定しているという。また、容量は4GBになるようだ。さらに、GS Magicstorブースには、日立GSTの1.8インチHDDと同じ形状の1.8インチHDDが展示されていた。こちらは実働デモも行なわれており、2カ月後には出荷が開始される予定とのことだ。
GS Magicstorは、明らかに東芝や日立GSTを意識した製品展開を行なっており、やや露骨に感じるほどだ。このあたり、他社の真似をしてもいいから、今後成長が期待される分野には積極的に進出していこうという強い意志が感じられる。
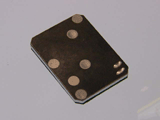 |
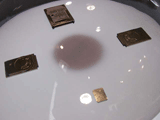 |
 |
| 東芝の0.85インチHDD。世界最小のHDDとして、ギネスブックにも掲載されている | 東芝の小型HDD。奥にあるのが2.5インチHDDで、左右両側が1.8インチHDD、手前が0.85インチHDDである | GS Magicstorの1インチHDD。容量は4.4GB。2カ月後に量産が開始されるとのことだ |
 |
 |
| GS Magicstorが開発中の1.8インチHDD。日立GSTの1.8インチHDDと同様、コネクタの形状は2.5インチHDDと互換性がある | GS Magicstorの1.8インチHDDは、すでに実働デモが行なわれていた。容量は40GBで、量産は2カ月後に開始されるとのことだ |
●3.5インチHDDの進化もまだまだ続く
3.5インチHDDは、デスクトップPC用や家電のハイブリッドレコーダー用などに広く使われている。日立GSTでは、3.5インチHDDに関する展示も行なわれていた。400GBという現時点での最高容量を実現した「Deskstar 7K400」や、15,000rpmという超高速回転を実現した「Ultrastar 5K73」が展示されており、技術力の高さを盛んにアピールしていた。
●12GB CFカードやMMC 4.0準拠製品を出展していたPretecブース
CFカードやSDメモリーカード、MMCなど、フラッシュメモリカードの大手Pretecブースでは、現時点で最大容量となる12GB CFカードが展示されていた。このCFカードは、先日ソリッドアライアンスから発売が予告されたものと同じで、165.9万円という価格が付けられたことで話題を呼んだ製品だ。
この製品はPlatinum CFシリーズと呼ばれ、Pretecが独自に開発したコントローラの搭載により、高い転送速度を実現してることが魅力だ。なお、12GB CFカードの量産出荷は2004年第4四半期になるとのことだ。
また、2004年2月にMMCの標準化団体MMCAからリリースされた最新規格MMC 4.0に準拠した製品も、いちはやく展示されていた。MMC 4.0では、バス幅が最大8倍に拡張されたほか、クロック周波数も向上し、従来のMMCに比べて最大20倍もの高速な転送が実現できる。
もちろん、MMC 4.0の性能をフルに発揮するにはMMC 4.0対応機器が必要になるが(物理的な形状は変わっておらず、従来の機器でも利用可能)、PretecブースではMMC 4.0対応のカードリーダーが展示されていたほか、年末にはノキアやモトローラなどから、MMC 4.0対応の携帯電話が登場する予定とのことだ(日本での発売は未定)。
PretecのMMC 4.0対応機器では、リード22.5MB/sec、ライト18MB/secという高速転送を実現しており、現在出荷されているフラッシュメモリカードの中で最速となる(高速SDメモリーカードの約2倍)。
そのほか、超小型USBメモリ「i-Disk TINY 2.0」の1GB品(日本ではソリッドアライアンスから購入可能だが、現時点で発売されているのは512MB品まで)や、世界最小のUSBメモリ「i-Disk TINY」も展示されていた。i-Disk TINY 2.0は、USBコネクタ部分が回転する構造になっており、カバーをなくしてしまう心配がなく、持ち運び時にはコネクタ部分をしっかり保護できる。
 |
 |
 |
| MMC 4.0規格に対応した9in1カードリーダー | USB 2.0対応超小型USBメモリ「i-Disk TINY 2.0」。容量1GB品が展示されていた | 世界最小のUSBメモリ「i-Disk TINY」。こちらはUSB 1.1対応となる |
□COMPUTEX TAIPEI 2004のホームページ(英文)
http://www.computex.com.tw/computex2004/
(2004年6月3日)
[Reported by 石井英男]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答はいたしません。
Copyright (c) 2004 Impress Corporation All rights reserved.