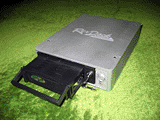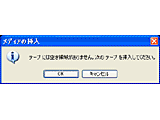|
|


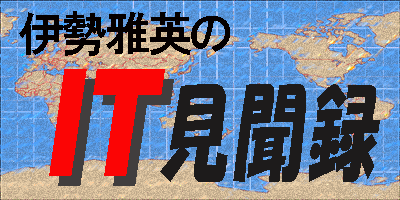
Disk to Disk Backupのススメ |
筆者は、データバックアップにテープドライブを活用している。しかし、HDDとテープメディアの容量差は年々開きつつあり、このままテープを使い続けるには、ドライブを新調するなど、そろそろ莫大な投資が必要になってきた。
とはいえ、一個人の筆者が大金をはたいて最新のオートローダなどを買うわけにもいかない。そもそも本連載の第1回目「サーバーからクライアントまですべてをノートPCでまかなってみる」では、皆様の前でデカブツの排除を高らかに宣言している。
だったら、こうした現状を逆手にとり、大容量化と高速化の著しいHDDを使ってバックアップを行なえないものか。というわけで、今回のお題は、HDDのバックアップにHDDを利用する「Disk to Disk Backup」についてだ。
●筆者が渡り歩いてきたテープ遍歴
筆者は、もともとデータバックアップに3.5インチMO(230MB)や5インチMO(2倍密)を使用していた。しかし、どちらも容量面で納得がいかず、初めて手を出したテープドライブがDDS-2(Digital Data Storage - 2)だった。DDSは、ソニーとHewlett-Packardがオーディオ用のDAT(Digital Audio Tape)をデータバックアップ向けに改良した規格で、DDS-2はネイティブ(非圧縮)で4GBの記憶容量を持つ。
次に手を出したのが、エクサバイトの8mmデータドライブだった。筆者が手に入れたドライブはEXB-8500で、ネイティブ記憶容量は5GB(テープ長112m)である。テープドライブ本体は5インチフルハイトと大きく、テープカートリッジにもDDSと比較して多少ハイエンドな雰囲気が漂っている。こんな8mmデータドライブに対して、「これぞオレが求めた最強ドライブ」と一度は思った。しかし、そんな幸せな時間は長く続かなかった。目の前にDLT(Digital Linear Tape)が立ちはだかったからだ。
DLTはもともとDECが開発した製品だが、QuantumがDECのストレージ部門を買収した時に、Quantumブランドとなった。DLTのテープ幅は12.65mm(約2分の1インチ)と広く、テープカートリッジはドライブ内部のテイクアップリールでテープを巻き取る1リール方式である。ネイティブ記憶容量も、最大35GB(DLT 7000)と当時のテープ規格の中ではダントツに大きかった。
DLTの最大の特徴は、データの記録方式としてリニア記録方式を採用していることだ。リニア記録方式は、テープを一直線に始端から終端まで往復して記録していくため、テープパスをシンプルにでき、ヘリカルスキャン方式よりも信頼性を高めやすい。DLTは、テープ記録面に走行系がいっさい接触しないHGA(Head Guide Assembly)を採用しており、記録面に接触するのはヘッドのみとなる。
大容量、高速バックアップ、高い信頼性、デカイ本体、インパクトのあるテープカートリッジ……と、数多くの興味深い特徴を備えたDLTに筆者があこがれるのも無理はなかった。とはいえ、当時学生だった筆者に100万円超の出費はどだい無理な話であり、しばらくの間は指をくわえたままの状態が続いた。
しかし、こんな貧乏学生を救ってくれる神様が突然目の前に現れた。それは、Quantumの日本法人である日本クアンタム(現在はHDD部門がマックストアに吸収され、テープ部門は日本クアンタムストレージに引き継がれた)だった。「最新のDLT 7000はさすがに無理ですが、DLT 2000の評価機なら差し上げられます」とのこと。そして、さらに興味深い言葉が続く。「このドライブは、日本に初めて上陸したDLT 2000なんですよ」。なんだかとってもレアものを用意してくださったようだ(笑)
DLT 2000を手に入れてからというものの、DLTなしには生活できなくなった。その後は、新品ながら安く出回っていたDLT 7000を'99年に購入し、さらに一度は手にしてみたかった7連装オートローダ(Sun MicrosystemsブランドのDLT 4700)も2000年に中古で購入している。もちろん、DLTのテープテンションが実は思った以上に強いのではないかと不安になってみたり、カートリッジからテープを引き出すリーダ部分でごくたまにトラブルが発生するなど、実際に使ってみて気になった点はいくつかある。しかし、おしなべていえばDLTによるバックアップ生活は筆者にとって十二分に満足できるものだった。
●HDDとテープの容量に大きな開きが生じつつある実情
さらに、時が経つにつれて、1つの“乖離”が生じていることにも気づき始めた。それは、HDDとテープの大容量化が互いに歩調を合わせていないことだった。
HDDの大容量化(面記録密度の向上)はきわめて著しい。薄膜誘導型ヘッドのみを搭載していた'90年前半までは年率25%(10年に2倍)の伸びだったが、AMRヘッドが登場して年率60%(10年で100倍)に、さらにGMRヘッドが登場して年率100%(1年で2倍)までに加速している。一方のテープは、メーカが公表しているロードマップを見ても分かるように、だいたい数年で2倍のペースがいいところ。HDDも2002年後半あたりから年率が大きく落ちているものの、一度広がった差はそうそう簡単に縮まるわけがない。
ここで、1つの結論が生まれる。それは、HDDのバックアップを行なうにあたり、たとえ最新の規格に対応したものであっても、“単体”のテープドライブではちょっと力不足であるということだ。例えば、現在比較的入手の容易な大容量テープドライブには、SDLT 320(ネイティブ記憶容量は160GB)やLTO Ultrium-1(同100GB)があるが、対するHDDの記憶容量はATA HDDですでに250GBにも達している。つまり、テープカートリッジ1本では、HDD 1台の丸ごとバックアップにはすでに対応できない状況にある。
もちろん、テープカートリッジを入れ替えていけばスケーラブルにバックアップ容量を増やせるが、テープカートリッジを“手動”で入れ替える作業はあまり現実的ではない。テープカートリッジ1本あたりのバックアップ所要時間はだいたい数時間が一般的なので、夜寝る前にバックアップを始めようものなら、乳飲み子の夜泣きではないが、数時間ごとに起こされてテープカートリッジを入れ替える羽目に陥る。
こうした理由もあり、エンタープライズ環境では、テープカートリッジの入れ替えが完全に自動化されたオートローダやテープライブラリが多く導入されている。いや、業務で使うのであれば、テープカートリッジの入れ替えやヘッドクリーニングなどが自動化されていなければまったく使い物にならない。結局のところ、オートローダ以上のものを使用しなければ、テープの本当の良さを味わうことは難しいというのが現状なのだ。
●Disk to Disk Backupという新たな選択肢
従って、筆者はもうテープという選択肢をあきらめることにした。そこで着目したのが、HDDでバックアップをとるというアプローチである。HDDの大容量化が著しいのであれば、こうした事情を逆手にとってしまおうという魂胆だ。
実は、このようなアプローチはすでにエンタープライズ向けのソリューションとして昨年あたりから採用され始めている。例えば、QuantumのADAM(Adaptive Disk Array Management)テクノロジが有名だ。これは、HDDの高いアクセス性能に基づくDisk to Disk Backup技術で、安価で大容量のATA HDDが登場したからこそ実現できたものといえる。
エンタープライズ系のシステムでは、サービスの可用性を高めるためにバックアップに割り当てられる時間(バックアップウィンドウ)が年々短縮されており、テープライブラリで直接バックアップを行なうことが難しくなってきている。ライブラリに内蔵されるテープドライブの台数を増やし、並列処理を強化することで高速化を図ることは可能だが、Disk to Tape Backupで実用に耐えうる高性能なテープライブラリはきわめて高価だ。
そこで、オンラインストレージ(HDD)とオフラインストレージ(テープライブラリ)の間に「ニアラインストレージ」と呼ばれる中間のストレージを配置し、オンラインストレージからニアラインストレージへのデータ移動にDisk to Disk Backupを導入する。HDDはシーケンシャルデバイスであるテープドライブよりも格段に高速なので、短時間でバックアップを完了できる(障害発生時にはリストアも短時間で行なえる)。ニアラインストレージにバックアップデータを格納できれば、あとはテープライブラリでゆっくりとそのデータのアーカイビングを行なえる。
多少話が脱線してしまったが、筆者はこうした世の中のトレンドを踏まえつつ、自分のPC環境にもDisk to Disk Backupを導入してみることにした。とはいっても、エンタープライズ環境のようにテープとの併用は考えておらず、あくまでもDisk to Disk Backupによるお手軽バックアップまでで止めておく。
●リムーバブルタイプの外付けHDDボックスでお手軽バックアップ
筆者のファイルサーバはノートPCなので、バックアップ機器の接続に利用できるインタフェースは原則としてUSB 2.0かIEEE 1394しか選択肢がない。しかし、筆者はストレージ機器をUSBで接続することにためらいのある人間なので、他のストレージ機器と同様にバックアップ機器もIEEE 1394で接続することにした。
次に、どんなバックアップ機器を接続するかということだが、テープのようにメディアを自由に入れ替えられる必要があるので、リムーバブルタイプの外付けHDDボックスを選択した。同時に、交換用のトレイをいくつか用意しておくことで、複数のHDDを自由に使い分けられるようにした。
結局、筆者が選択した外付けHDDボックスは、ラトックシステムのFireDockシリーズ(メタルボディのFR-DK1ALB)だ。HDDでありながらドライブ自体はリムーバブルデバイスとして認識され、さらには同社が開発したATA-IEEE 1394変換ブリッジのリムーバブル・エミュレーション機能によって、PCの電源を入れたままでもHDDを自由に換装できるという点が購入の決め手となった。
なお、HDDの耐久性はテープカートリッジよりもはるかに低いが、リムーバブルHDDに格納されたデータは事実上オフライン状態にあるため、仮にそのHDDが壊れたとしても致命的なデータ損失につながることはない。また、メディアのコスト面についても、DLTのテープカートリッジが1本あたり1万円前後するので、実は売れ筋(執筆時点では120GB)のATA HDD 1台分と変わらなかったりする。従って、筆者の使用条件下においては、DLTよりも高速で大容量のテープカートリッジとして振る舞ってくれることになる。
最後に、Disk to Disk Backupを実際に試してみた。バックアップ元をヤノ電器のFR1-120A、バックアップ先をラトックシステムのFR-DK1ALB(IBM DTLA-307060を内蔵)としたとき、約20GBのバックアップに要する時間は、ベリファイなしで29分、ベリファイありで41分だった。
さらに、なるべくバックヒッチング(backhitching)が生じないように配慮しながら、DLT 7000で同じデータのバックアップを行なったところ、所要時間はベリファイなしで79分、ベリファイありで155分だった(いずれもハードウェア圧縮 有効時)。つまり、Disk to Disk Backupのバックアップ所要時間は、DLT 7000と比較してベリファイなしで3分の1、ベリファイを含めれば4分の1にまで短縮されたことになる。これくらい迅速にバックアップを行なえれば、バックアップ頻度を高めてデータ保護をさらに強化することも容易になる。
こうした考察と実験の結果、Disk to Disk Backupが筆者のPC環境で十分に実用になることが分かった。まだ名残惜しいので当分部屋にはDLTを飾っておくつもりだが、筆者のテープ生活は事実上これにて幕を閉じる。
□日本クアンタムストレージ、仮想テープライブラリ
http://www.quantum.co.jp/tapelibrary/products/enhnced+backup+solutions/
□ラトックシステム、FireDockシリーズ
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/dk.html
(2003年6月5日)
[Text by 伊勢雅英]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.