



 |
|
●いよいよ1GHzがデモ段階へ
IntelとAMDは、いよいよ1GHzプロセッサの実物を見せ始めた。AMDは、特殊な冷却装置を使わないAthlonプロセッサで1.1GHz動作をデモ。一方、Intelも0.18μm版Pentium III(Coppermine:カッパーマイン)コアでの1GHzを技術発表した。Intelは、来週米国パームスプリングスで開催される同社のカンファレンス「Intel DeveloperForum(IDF)」で、1GHzのデモを行なうと見られている。両社とも、早ければ夏、遅くても初秋に発売する1GHzプロセッサへ向けて、いよいよスパートに入った。
IntelもAMDも、1GHzが目の前にあることは示すことができるようになった。しかし、デモや技術発表と、製品出荷は別な話。ユーザーの手元に届く製品に、1GHzプロセッサが載って来ないと、1GHzを実現したとはいえない。そして、両社とも、1GHzの製品出荷前には、越えなければならないハードルをいくつか抱えている。
今回の1GHz前哨戦で面白いのは、AMDが銅(Cu)配線技術を使った0.18μmプロセスでデモを行なっているのに対して、Intelがアルミニウム(Al)配線の0.18μmプロセスでの技術発表を行なっている点だ。ここで、両社の製造技術の面から見た、1GHzの現実性を比較してみよう。
●銅配線のAMDとアルミ配線のIntel
Intelは、0.18μmプロセス「P858」では、アルミ配線を使う。Intelは、0.18μmでは銅配線を使う計画がなく、1GHzは、このP858をチューンして実現する見込みだ。
対するAMDの0.18μmプロセスは、すでに量産を始めているアルミ配線の「CS50」と、銅配線の「HiP6L」の2本立てだ。CS50は米テキサス州オースティンのFab25で、HiP6LはドイツドレスデンのFab30で生産を行なう。AMDの当初のアナウンスでは、GHzはHiP6Lで実現することになっていたが、場合によってはCS50でも1GHzプロセッサが採れるようになるかもしれない。
Intelはアルミ配線、AMDは銅配線と聞くと、銅配線の方がずっと有利なように聞こえる。しかし、問題はそれほど単純ではない。それは、(1)新しい素材である銅配線が製造面でハードルを抱えていることと、(2)IntelのP858がアルミ配線でありながら銅配線並に配線抵抗を減らす技術を織り込んでいるためだ。つまり、IntelのP858のパフォーマンスが高く、銅配線には歩留まりの不安があるため、一概に銅配線のAMD有利とはいえないということだ。
●配線遅延を減らす切り札が銅配線
では、両社は同じ1GHzを目指す過程で、どうしてアルミと銅に道が分かれたのだろう。よく誤解されているが、問題になっているのは銅配線を「導入するかどうか」ではなく、銅配線を「いつ導入するか」だということだ。CPU業界では銅配線技術は0.13μm世代では必須になると見ているが、0.18μm世代については意見が分かれている。Intelは、“0.18μmではまだ必要ない派”で、IBMやMotorola、AMDは“0.18μmから必要派”という立場だ。
では、0.18μmプロセスで、銅配線が突然注目されたのはなぜか。それは、プロセスの微細化が進むにつれて、配線遅延により動作クロックを上げられなくなるという問題が指摘され始めたからだ。これは、微細化が進むと配線ピッチを小さくしなければならなくなるためで、ピッチが狭くなると配線の抵抗と配線間の容量が増加するからだ。すると、長い配線では配線遅延がネックとなって動作周波数を上げられなくなってしまう。
この問題を解決するには、配線抵抗を減らすか、配線間容量を減らせばいいことになる。そこで登場したのが、従来のLSIの配線に使われているアルミニウム(Al)系素材と比べると、抵抗率が約半分の銅(Cu)を配線に使うアプローチだった。銅配線では、同じ抵抗値の配線を、アルミよりもずっと微細に実現できる。そのため、銅配線に最適化して物理設計を行なうと、高クロックのプロセッサを実現しやすいという。
●銅配線の不安材料は歩留まり
このように、銅配線はハイエンドプロセッサ用としては理想的な技術だが、問題もある。それは歩留まりやコストの不安だ。というのも、銅がチップ素材のシリコンに溶け込むコンタミネーション(汚染)を起こしやすい典型的な不純物だからだ。銅配線を採用するメーカーは、そのコンタミネーションを防ぐ技術を開発したのだが、その有効性がまだIBM以外はあまり実証されていない。
Intelが懸念したのも歩留まりの点だった。例えば、Intelのロナルド・E・カリー氏(ディレクタオブマーケティング、IA-64 Processor Division)は、昨年9月のIDFで次のように語っている。「銅配線技術の評価は行なっているが、問題は歩留まりが悪いことだ。それも、非常に悪いという調査結果を得ている。Intelは、90%以上の高い歩留まりを求めているため、銅配線をすぐに採用することはできなかった。だが、0.13μmのタイムフレームになれば、そうした問題も解決しているだろう」
つまり、Intelは確実な歩留まりを求めているため、銅配線という冒険ができなかったというわけだ。各社の歩留まりは公表されていないためわからない。しかし、AMDが銅配線技術で技術提携したMotorola自体が、PowerPC G4の銅配線版で苦戦している(銅配線SRAMはうまくいっている)という報道はよくなされている。こうした懸念がPC業界にあるため、AMDは銅配線で1GHz製品を出す場合には、歩留まりで問題がないことを実証し、実際に潤沢に出荷しなければならないだろう。
AMDは、HiP6L版Athlon(おそらくMustang)について「第2四半期末から売上げに貢献する」、つまり、6月までには出荷が始まるとしている。この時点で、AMDがどれだけの数量を出荷できるかが、注目されるだろう。もし、AMDが夏までに十分な数のHiP6L版Athlonを出荷することができ、しかも最初のクロックが1GHzに達していたとすれば、1GHzの戦いでAMDがリードすることができる。
●Intelはトリッキーな技で配線遅延を解決
一方、Intelは銅配線を使わない代わりに、アルミ配線と低誘電率膜の組み合わせで、高クロックを実現できるプロセス技術を探った。その結果が、P858だ。このP858の特長に関しては、'98年秋のIDFで、Intelのアルバート・ユー上級副社長が説明している。それによると、Intelは長い配線に使われる上層を厚くし、配線の断面が長方形になるように形成することで、抵抗の増加を抑えたという。これを単純な概念図にすると次のようになる。
プロセスの相違による断面の差
|
| 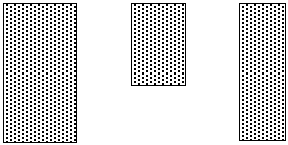
左から0.25μmプロセスの配線の断面、0.18μmプロセスの銅配線の断面、Intelの0.18μmプロセスのアルミ配線の断面
| |
つまり、銅配線では、0.18μmに微細化する際に、そのまま配線も微細にしてしまっても抵抗率が低いので問題がない。ところが、アルミでは微細にすると抵抗が増大してしまい配線遅延が生じてしまう。そこで、Intelは縦に長くすることで、ピッチを狭く保ちながら抵抗の増加を抑えたというわけだ。
なんだかコロンブスの卵みたいな話で、これで問題が解決できるなら、どのメーカーもIntelと同じことをやればいいと思うかもしれないが、そうもいかない。昨年10月のMicroprocessor ForumのセミナーでKeith Diefendorff氏(Microprocessor Reportのシニアアナリスト)が行なった説明によると、P858のように、厚みと高さの比率を大きくして配線を形成することは、製造する際に難しいのだという。Intelは、この高い比率を安定に形成する独自技術を開発しており、他社がすぐにマネすることはできないようだ。
●IntelはCPUアーキテクチャで不利
IntelのP858は、このようにアルミ配線でありながら高クロック化しやすく開発されている。これが、1GHzを目指す上でのIntelのアドバンテージだ。Intelは、AMDのように、銅配線への移行というリスクを負っていない。Intelは、P858プロセスに改良を加えて、さらに高クロック化を実現できるように持ってゆくと思われる。
例えば、Intelは0.25μmでも、プロセスに改良を加えてパフォーマンスの向上を図った。「Intel Technology Journal」のQ3'98号によると、同社の0.25μmプロセス「P856」を改良した「P856.5」プロセスでは、光学的に5%縮小して、18%ゲイト遅延を向上させたという。つまり、実質的に0.22μm程度になっていたわけだ。0.18μm(P858)でも当然、こうした改良が図られると思われる。Intelの抱えるひとつの問題は、そうしたプロセスの改良が間に合うかどうかだ。うまく行かなかった場合は、Pentium IIIの1GHzは、秋までにあまり量が採れるようにならないという可能性もある。
そのほかにも、Intelには不利な点がある。それは、Pentium III(P6)コアとAthlonコアでは、Athlonコアの方が高クロック化しやすいと見られることだ。Athlonの方がよりパイプラインが深く、内部アーキテクチャもより洗練されている。実際に、0.25μm世代のプロセスで製造したPentium IIIの最高クロックが600MHzだったのに対して、Athlonの0.25μmの最高クロックは700MHzだった。
このことは、プロセス技術のパフォーマンスが同程度だったら、Athlonの方がPentium IIIよりクロックが高くなる可能性が高いことを意味している。現状で、Pentium IIIがAthlonとクロック競争でなんとか競り合っていられるのは、AMDのアルミ配線0.18μmプロセス(CS50)より、IntelのP858の方が優秀だからろう。
●銅配線版AthlonにはWillametteで対抗か
こうした基本アーキテクチャの優秀性のために、Athlonは、CS50で1GHzを達成できる可能性もある。AMDは、CS50ベースの次世代Athlonとして512KB程度の2次キャッシュSRAMを統合した「Thunderbird(サンダーバード)」を計画しているが、このThunderbirdである程度限られた量なら1GHz品を採れるようになるかもしれない。
しかし、CS50のThunderbirdでは、1GHzを採れても、製品ミックスのかなりの割合を1GHz以上に引き上げることは難しいと思われる。同じく、限られた量の1GHz品が採れるようになると見られるPentium IIIと、互角以上には戦えないだろう。だが、HiP6Lが順調に立ち上がれば状況は変わる。1GHz品を大量に生産して2001年にメインストリームに持ってきて、さらにオーバー1GHzへと移行してゆくことができるかもしれない。そうなれば、プロセス技術の優位性が失われるため、Pentium IIIが圧倒的に不利になってしまう可能性が高い。
だが、Intelはここへ来て、OEMメーカーに今秋デビューする次世代CPU「Willamette(ウイラメット)」を強く打ち出したと言われる。WillametteはPentium IIIより高クロック化が容易な設計になっており、同じプロセス技術でもPentium IIIより数割高いクロックを実現できると見られている。デビュー時のクロックは1.4GHzだと言われている。つまり、Intelは、HiP6L版Athlonには、Willametteで対抗しようとしているのだ。AMDは、1GHzを越えてもまだ安心できない状況が続きそうだ。
(2000年2月10日)
[Reported by 後藤 弘茂]