 |


■森山和道の「ヒトと機械の境界面」■
|
BMI(Brain Machine Interface)、あるいはBCI(Brain Computer Interface)と呼ばれるインターフェイス技術がある。脳と機械、コンピュータを直結させるインターフェイス技術だ。人間は脳で考え、脳で身体を制御している。インターフェイス技術がターゲットとして脳を選ぶことは必然だと言えよう。
国内外で研究が進んでいる技術だが、4月4日、5日にはBMI技術を中心としたシンポジウムが開催された。少なくとも今のところはPCとは全く関係ないのだが、「脳を活かす」と題されたこのシンポジウムの内容を簡単にレポートしておきたい。
ATR(国際電気通信基礎技術研究所)大会議室にて開催されたこのシンポジウムは、「脳を活かす」研究会の発足記念シンポジウムだ。登録者は400名以上にのぼり、会場の外にモニターが設置されるほどのにぎわいとなった。
●記者会見 根本問題に迫ろうとする脳科学
シンポジウム開会前には研究会に関する記者会見が行なわれた。出席者は、理化学研究所脳科学総合研究センターの甘利俊一氏、ATR脳情報研究所所長の川人光男氏、大学共同利用機関法人自然科学研究機構 生理学研究所 発達生理学研究系 認知行動発達機構研究部門教授の伊佐正氏の3氏。
 |
 |
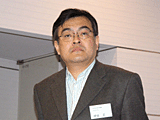 |
| 理化学研究所脳科学総合研究センター 甘利俊一氏 | ATR脳情報研究所所長 川人光男氏 | 自然科学研究機構 生理学研究所 教授 伊佐正氏 |
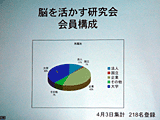 |
| 「脳を活かす」研究会・会員構成。企業からの参加者も多い |
甘利氏は現代の脳科学は「人間とは何なのかという根本問題に迫る時代が来た」と語った。さまざまな測定技術の発達により現在の脳研究分野は画期的な時代を迎えている一方で、社会のさまざまなステージに関わるようになりつつある。また一般の関心も高い。そこでこの研究会は、脳科学者と同時に一般の関連分野の人たちとの交流の広場となり「大きな方向付け」をしていくことを狙ったものだという。
背景には、「ある種の脳ブーム」に見られるように、必ずしも正しい情報が一般に行き渡っていない現状がある。研究者自身も情報発信に対する姿勢を反省しつつ、信用されるような研究者集団であることを目指し、閉じた研究会ではなく、大きく踏み出して広い分野との共同研究を進めていきたいという。
具体的には一般社会とのコミュニケーションのほか、情報交換、情報発信、予算獲得の環境作り、サポートなどを行なっていき「これでかたまって研究費をとろうということではなく、多くのコミュニティを巻き込んだ応援団としての役割」を果たしたいと語った。クオリティをコントロールしながら、一般社会にも開かれた形で脳科学を発展させていくことが、この研究会の趣旨であるようだ。
なお、より詳細な研究会立ち上げの背景については こちらを参照していただきたい。
●講演
講演は、甘利俊一氏による「脳を活かす研究会の発足にあたって」という挨拶と、川人光男氏による「脳を活かす研究会の準備状況」から始まった。川人氏は脳科学の広がりを紹介すると同時に「自分たちの意識や心の問題に直接言及できるのは脳科学をおいて他にはない」と述べた。
また、「脳文化人」の登場に見られるように何となく脳科学を背景にさまざまな問題について発言する研究者がいることに懸念を示しつつも、よりよく生きる倫理を考える上でも脳科学の重要性は増しており、脳科学への支持を広く受けられるようになることを望む、とまとめた。
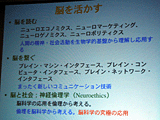 |
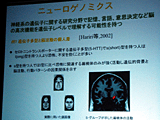 |
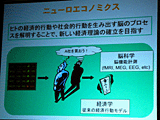 |
| 脳を読む、繋ぐ、脳と社会などの分科会から構成される | 脳科学の広がりの例:ニューロゲノミクス | ニューロエコノミクス |
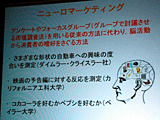 |
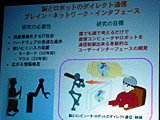 |
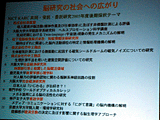 |
| ニューロマーケティング | ブレイン・マシーン・インターフェイス | さらに色々ある |
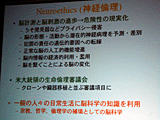 |
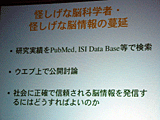 |
| ニューロエシックス(神経倫理学)という学問も立ち上がっている | その一方で、怪しげな脳科学情報が出回ってもいる |
 |
| 評論家 立花隆氏 |
続けて登壇したのは評論家の立花隆氏。「サイボーグ技術と脳を活かす」と題して、主にNHKで放映されている最近のサイボーグ技術取材の概要について述べた。
立花氏は「サイボーグ技術の現実化とその可能性については取材をしながら大きなショックを受けた。SFの世界のことだと思っていたが現実になりつつある。ニューロサイエンスはニューロエンジニアリングへと変わって行きつつある。脳科学というと、日本では基礎科学がイメージされるが、世界の趨勢は応用技術だ」と述べた。
ピッツバーグ大学のシュワルツのサルとロボットアーム操作や、南カリフォルニア大学のバーガーによる人工海馬チップなどの話題を、『マトリックス』や『攻殻機動隊』などフィクションも引きながら、全般的にかなり無邪気に紹介した。
作家の瀬名秀明氏は「脳と社会:サイエンスリタラシー」と題して講演した。瀬名氏は現在東北大学機械系特任教授として「SF機械工学企画担当」を務めている。日本では珍しい大学内滞在作家として、大学内を取材しSF作品を書くのが仕事だ。
瀬名氏はこれまで作家として「難しいけれど面白い」ことに対して取り組んできた。科学を知れば知るほど、科学は白黒はっきりしたものではなく、むしろグレーゾーンに本質があるとわかってくる。だが、それはなかなか理解されづらいジレンマがある。
そのような話の中から「脳文化人」が日銭を稼いだりすること以外に社会のなかで脳科学を活かすということは意外と難しいと述べつつも、小林秀雄氏の講演を引きながら、脳倫理的に社会のリテラシーのなかで脳科学の成果を生かすとなると、「主観と客観」や「信じるということと知ることは違う」といったことを伝えることが近いのではないかと語った。
脳は客観的な科学の対象にできる臓器である。いっぽう、脳が紡ぐ思考は主観的なものだ。また人間は、一回しか起きなかった出来事に強烈な印象を受けることがある。脳は一回切りの出来事でも根本的に状態が変わってしまうことがあるのだ。このあたりのこと、一回性をどれだけ大事にできるかに対して脳科学はどのようにアプローチしていくのか。それが今後の課題だと述べた。
 |
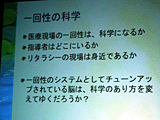 |
| 作家 瀬名秀明氏 | 瀬名氏は「科学の方法論」や、医療現場での課題としての「一回性」を取り上げた |
 |
| 日本大学大学院医学研究科脳神経外科 片山容一教授 |
日本大学大学院医学研究科脳神経外科教授の片山容一氏は「脳深部刺激とブレインマシンインターフェイス」について講演した。脳深部刺激(DBS)とは、脳機能異常の治療手段の1つである。脳の深部に電極を埋め、鎖骨の下に埋められたバッテリを繋ぎ、電気信号を出すことでパーキンソン病患者などの状態を改善させる。脳の働きを人工的に調整する技術である。つまりもともとはブレイン・マシーン・インターフェイス技術ではない。だが徐々にインターフェイスにも近づきつつある技術としても見ることができるという。
これまでは「脳損傷の後遺症状は神経回路の機能欠損である」と捉えられてきた。欠損ということは、暗黙のうちに再建は不可能だ、つまり治らないと見なしていることを示す。だがこれが機能神経外科、再建神経外科の世界では見直されつつあるという。後遺症は「神経回路網の機能失調だ」と見なすのだ。そうすると機能にバランスを取り戻すことが可能ではないかとなる。
講演では実際に頭のなかで作られる幻の痛み、難治性疼痛に対する治療の様子や、ジストニアやパーキンソン病の不随意運動や震えなどに対する治療効果の様子が披露された。片山教授は'79年からDBS手術を開始し、これまでに500以上の症例に対して手術を行なってきたという。DBSは'92年からは保険適用の対象にもなっており、日本は決してこの分野では遅れを取っておらず、独自の経験を蓄積していると語った。
このような手術の正確さが確立したのは'90年代である。手術ができるようになったのはMRIを使った誘導定位脳手術と呼ばれる技術の発展が大きいという。MRIには1mm以下の精度はないため、細い電極を使った神経細胞の活動計測を併用しながら手術を行なう。
脳の一部の部位を破壊する手術に比べてDBSは空間的調節性と時間的調節性が高い点が有利だという。つまり、かなりいろいろな範囲に電極を置くことができ、また破壊と違って不可逆ではないということだ。スイッチのオンオフができるからである。
振戦(ふるえ)の患者さんの中には、例えば腕を持ち上げたときだけ振戦が出るという人もいる。そこで現在「オンデマンドDBS」と呼ぶ技術を研究中だという。例えば腕を動かしたときだけDBSのスイッチを入れるのである。問題は、そのスイッチをいつ入れるかだ。ふるえが起こったあとにDBSのスイッチを入れると逆に元の震えよりも複雑なふるえが起きてしまう。できれば、脳内シグナルからDBSを駆動することが望ましい。
つまり、腕を動かそうと患者さんが思う(意識上にその考えが上る必要はない)とDBSのスイッチが入ればいいのだ。つまり今後は「入力と出力を持つDBSができる」という。脳の中から入力を受け、「脳を道具として活かす」ために出力を出す、そのために「脳に付け加えた回路」として捉えられるようになるのではないかと語った。
なお刺激の周波数だが、振戦そのものの周波数は6Hzくらいなのだが、DBSの出力は電圧2V、130Hzだとうまく収まることが多いだそうだ。その意味はまだ分かっていないという。
また、手術にあたっては本来の目的の機能調整だけで収まればいいのだが、てんかん発作や精神的な影響の危険性も考慮に入れなければならない。現在まではそのような事故は500例中1例もないそうだ。
講演の内容も患者さんのビデオも非常にエキサイティングだったが、症状が改善した患者さんの話をするときに浮かべる片山教授の笑顔もまた非常に印象的だった。
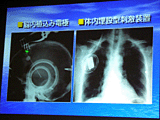 |
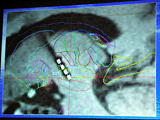 |
| 脳のなかに電極を埋め込む | 実際に電極を埋め込む様子も紹介された |
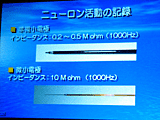 |
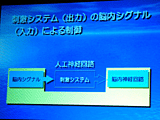 |
| 脳に埋め込まれる電極 | 脳内シグナルを入力として制御する人工神経回路の概念図 |
翌5日には、プリンストン大学のサミュエル・マクルーア(Samuel McClure)氏が「Multiple Minds : Neuroscience of economic decisions」と題して講演を行なった。
なお、予定されていた仮演題は「Neuromarketing and Neuroeconomics」だった。ニューロマーケティング(神経マーケティング)、ニューロエコノミクス(神経経済学)という言葉は聞き慣れないかもしれないので少し解説する。マーケティング分野では以前から心理学のテクニックを使って、市場の一般人が何を欲しているのか調査が行なわれていた。だがアンケートやヒアリングでは、結局、人間は自分が知っていることしか語れない。
だが、自分がある商品を気に入っている理由を言語化して語れる人は残念ながら滅多にいない。そもそも、まったく新しい製品の場合は、本当にそれが気に入っているのかどうかといったことは、本人にもよく分かってないことが多い。そこでここに来てfMRIを初めとした脳の非侵襲活動計測技術が注目され始めているのである。
さて、マクルーア氏らは、被験者にペプシコーラとコカコーラの飲み比べをさせたときに、ブランドイメージが行動や神経活動にどんな影響を与えるかという実験を行ない、2004年に発表した。コーラはどちらも化学成分を見れば似たようなものである。だが人はどちらかのブランドを好む傾向がある。そこで67人のボランティアを対象に、ブランドを隠して飲ませた場合と、ブランドを示して飲ませた場合を比較し、脳活動に違いが出るか否か調べた。
すると、ブランド情報を示したときは、特にコカコーラの場合は前頭前野背外側、海馬、中脳などに働きが見られた。いっぽう、ペプシの場合はブランド情報を示しても特に活動部位には差が見られなかったという。このことは、コカコーラ・ブランドのほうが脳や味覚の嗜好に対して何らかの影響を与えていると考えられ、コカコーラのほうがブランド戦略においては成功していることを示しているという。
 |
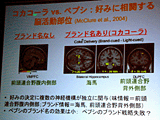 |
| サミュエル・マクルーア氏 | ブランド名のあるなしによる脳活動の違い |
一方、ニューロエコノミクスはまた少し毛色の違った研究分野だ。一言でいえば「行動と決定」に関する研究分野である。経済学のなかに「行動経済学」と呼ばれる一分野があるが、その延長線上と、脳科学でこれまで研究されていた、報酬に関する神経生物学が組み合わさったサイエンス分野だ。「報酬」というのはお金とか食物のことではない。人間がある行動を行なうときに、どのように自分自身の予測行動に価値判断を行なっているのかといったことだ。そもそも経済活動は人間しか行なわない活動だ。突き詰めて研究していくと面白いことになりそうだ。
これまでの研究で、脳は、例えば短期的なことに関わる予測と、長期的なことに関わる予測とで違うシステムを使うように、複数のシステムを状況に応じて切り替えて使っていることが分かっている。マクルーア氏は脳がどのようにコンテキストに応じてシステムを切り替えていくかが問題だと語った。
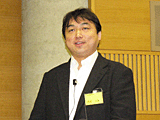 |
| ATRの神谷之康氏 |
ATRの神谷之康氏は「脳を読み、つなぐための神経デコーディング」という演題でエキサイティングな講演を行なった。
神谷氏は人間の脳のなかには心を読むシステムが存在し、マンガ「ドラえもん」に心を読む機械が多数登場するように、心を読む人工的な機械への願望があると述べた。現在の脳科学は、脳活動をある種の符号と見なしている。この文脈を延長すると、神経系のコードをデコードすることでマインドリーディングが出来るのではないかと考えられる。
神谷氏らは、fMRIとニューラルネットワークを使った視知覚のデコーディングに取り組み、既に人間が見ているのが右に傾いたシマか左に傾いたシマかを神経系の活動を読むことに成功している。またその他多くのマインドリーディング系の実験に成功しており、それらの成果は間もなく論文として公開されるという。
これだけでもかなり面白い話だが、自分が考えていることを機械に読んでもらっても何も嬉しくない。BMIの話を聞いたときに、頭で考えるより手を動かしたほうが早いと思った人も多いはずだ。だが我々はもともと「手を動かそう」と考えて手を動かしているわけではない。意識したときにはもう手は動き出している。
神谷氏は「究極のマインドリーディングは自分にも分からない自分の心の状態を知ること」であり、BMIは「意志決定支援」装置としても使えるのではないかと将来の可能性を述べた。脳のなかには複数の意志決定回路がある。その間でなんらかの折り合いをつけて我々は時々刻々の決断を行なっているものと思われる。それぞれの意志決定回路が何をしているのか、当人である我々も知らない。我々が知っているのは、単に我々自身が「決断した」と考えている結果のみである。だがそれは、意識に上らないところで活動している多くの意志決定モジュールの働きによるのかもしれない。
しかし、デコーディング・システムがあれば、その意志決定モジュールが何を考えているのか、直接読み出すことができる。意識上に登らせることができなかったものを明示できるかもしれないのである。
さらに、デコーディング・システムがあれば複数人の意志決定システムへアクセスできるかもしれない。我々は統一された自我という感覚を持っているが、それはイリュージョンに過ぎないかもしれないと神谷氏は語る。意志というのは後付の感覚に過ぎないかもしれないのだ。
このように神谷氏は、BMI技術は、オンライン的応用よりもむしろオフライン的応用に未来があるのであはないかと語った。もちろん、倫理的社会的問題もあるので、その点は今後議論していかなければならないとも付け加えた。映画「マトリックス」の話など硬軟織り交ぜたトークだった。
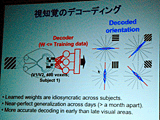 |
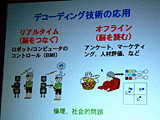 |
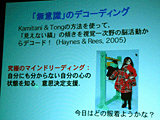 |
| デコーダーの概念図 | デコーディング技術の応用 | 究極は無意識のデコーディングだという |
最後に「BMIの脳科学と社会へのインパクト」と題されたパネル討論が行なわれたが、これはパネルというよりもむしろ各関係者の意志表明の場だった。念のため、パネリストは以下の通りである。
司会:外山敬介
パネリスト:
文部科学省 研究振興局ライフサイエンス課 先端医科学研究企画官 池田千絵子
総務省 情報通信政策局 技術政策課企画官 山内智生
経済産業省 製造産業局産業機械課 課長補佐 土屋博史
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 企画課 課長補佐 武井貞治
甘利俊一(理化学研究所)
丹治 順(玉川大学)
不二門尚(大阪大学医学部)
小泉英明(日立製作所)
天外伺朗(土井利忠)(ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス研究所(株))
川人光男(ATR脳情報研究所)
このように、「脳を活かす」研究会にはさまざまな人が、さまざまな立場から参加している。
 |
| パネリストたち |
ただ、出席者の一人としての感想を述べると、少々話題が偏り過ぎている感は否めなかった。脳科学の応用分野にしても、同研究会が考えている範囲は少々狭いように思われた。
また「脳を活かす」という言葉の意味が最後まで今ひとつ明確ではなく、どういったことを考えているのか、社会と接点を持つことを掲げる会であるならば、もう少し議論を突き詰めるべきではないかとも感じた。
いずれにせよ、今後の脳科学が、情報技術とさらに深く融合しつつ、我々の生活に徐々に入り込んでくることは間違いない。同研究会ではそれぞれの分科会などによる集まりなども企画しているようだ。今後もウォッチを続けていきたいと思う。
□「脳を活かす」研究会
http://www.cns.atr.jp/nou-ikasu/
(2006年5月11日)
[Reported by 森山和道]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2006 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.