 |


■山田祥平のRe:config.sys■サランラップごしのコピー |
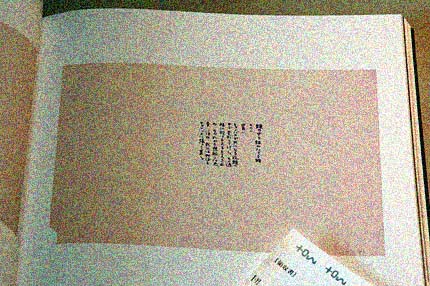 |
コンピュータのことを考えるときには常に、コンピュータには「オリジナル」を扱うことができないという、どうしようもない事実に突き当たる。コンピュータが扱う対象は、常に、「コピー」であり、「オリジナル」ではないということだ。
たとえば、この文章は、キーボードを打鍵していくことによって作成している。ハードウェアとしてのキーボードは、キーの打鍵を監視し、あるキーが押されたことを検知すると、まず、Makeというスキャンコードに続き、押されたキーそのもののスキャンコード、そして、離されたときにBreakというスキャンコードを発行する。この情報は、シリアル信号として送られ、パソコン側ではキーボードコントローラが受け取り、スキャンコードをキーコードに変換する仕組みになっている。
Uキーを押したときに、それがUである(あった)と運命づけられるためには、OSとしてのWindowsが、キーボードドライバによって、そのとき接続されているキーボードのタイプや、その既定の言語によって決めるのを待たなければならない。
さらに、日本語環境では、IMEなどのソフトウェアを通り抜け、ローマ字変換なども行なわれるので、Uを押したときに、エディタなどの画面に表示されるのは「U」ではなく「う」という文字かもしれない。そして、瞬く間ではあっても、そこまでの間には、限りない回数のコピーが繰り返されている。
ぼくら人間は、キーボードやマウス、ディスプレイやプリンタなどのデバイスを通してしかコンピュータと対話することができない。対面するのは、常に、なんらかのデバイスを通じてであり、そこに、何か、サランラップごしにモノに触れるようなもどかしさを感じることがある。しかも、その対象は、常に「コピー」なのだ。
●コピーとオリジナル
ぼくは、この2年間ほど、パソコンのことをずっと考えながら、何か、自分ではわからないもやもやしたものを感じていた。2年間考えてもわからなかったので、とにかく書き始めてみようというので、このシリーズをスタートすることにしたわけだ。とにかく書き始めれば、いろいろなことが見えてくるに違いないと思った。
もやもや感の原因のひとつは、おそらく、パソコンが扱う対象が常に「コピー」であるということを、自分では意識していなかったことにあるのだろう。だからこそ、「コピー」を扱うことによるリアリティの不在のような不安にかられていたのかもしれない。
パソコンで日本語を処理することが、今日のように実用的ではなかったころ、すでに物書きを生業としていたぼくは、当然、毎日、手書きで原稿を書いていた。出版社や放送局で用意されるペラと呼ばれる200字詰めの原稿用紙に、4Bの鉛筆で文字を書きつける。シャープペンシルはほとんど使わなかった。仕事中、机に向かう手元には、いつも10本程度の鉛筆を用意しておき、書き進むにつれて、先が丸まってくると別の鉛筆に取り替える。そして、用意した鉛筆の先が、全部丸くなると、電動鉛筆削り機でとんがらせた。
シャープペンシルを使わずに、鉛筆を使っていたのは、木の特性として、書くときの適度なしなりが、握る掌や腕、肩の疲労を抑制すると聞いたことがあったからだ。また、鉛筆には黒鉛と粘土を焼き固めた芯が使われているが、シャープペンシルの芯は強度を高めるために、プラスティックが使われているらしい。
確かに、夜を徹しての原稿書きでの疲労は減ったように思う。それでも、今でいうなら、50KBほどの原稿を書き上げ、白々と夜の明けかかった窓の外に目をやるころには、机の上は消しゴムのカスだらけだったし、縦書き原稿用紙のおかげで、手のひらから肘までは、鉛筆のこすれ跡で真っ黒になってしまっていた。キーボードを叩く50KBは、それほど疲れないけれど、手書きによる50KBは、まさに肉体労働だった。
でも、確かに、仕事をした痕跡としての原稿用紙の束は目の前にあり、そこには、物理的に、鉛筆の黒鉛が紙の繊維にくっついている。ちなみに、黒鉛についてちょっと調べてみたら、日本黒鉛のサイトに黒鉛は鉛(Pb)ではなく、石墨(グラファイト)であるという説明を見つけた。三菱鉛筆のお客様相談室でも、鉛と違って人害はないという回答をいただいた。
いずれにしても、これがオリジナルだ。名作家の直筆生原稿のようなありがたい存在ではないにせよ、少なくとも、ぼくが、一晩がかりで仕上げたオリジナル原稿である。ひらめきという得体の知れないものが、そこに姿カタチを現出したのだ。そして、それは、そこにしかない。
●インストラクションを考える
対象が文章である場合、オリジナルかコピーかは、さほど重要な問題ではないように思える。だが、それがもっとビジュアルなものである場合はどうなのだろう。
東京都現代美術館(MOT)で、オノ・ヨーコの回顧展「YES オノ・ヨーコ」(2004年4月17日~6月27日)を見てきた。ぼくらの世代なら、故ジョン・レノンの妻として知られる彼女だが、今の若い世代にとってはどうなのだろう。いずれにしても、日本人であるオノの40年にわたる活動を、母国で初めて包括的に紹介するものだ。よくわからない前衛芸術というイメージがあって、あまり期待もせずに立ち寄ったのだが、結果的にはとてもおもしろく、そして楽しめた。
ぼくが興味を持ったのはオノが'61年に始めた「インストラクション・ペインティング(指示の絵)」という試みだ。あるテーマに対して絵を仕上げるまでの手順が具体的に示され、鑑賞者は、その手順にしたがって、作品を完成させる。作品は短い文章で、ここでは引用の範囲を超えそうなので、紹介はできないが、つまるところは、言葉による絵の楽譜だ。展覧会の図録も出版されているので、ぜひご覧になっていただきたい。
オノは、'66年に米ウェズリアン大学で、個人イベントを開催しているが、後日、その注釈として、ミーティング出席者へのメッセージを書いている。その中で、自分の絵が、他の人に制作してもらうものであり、それらは、コラージュとアッサンブラージュ、さらにハプニングが芸術の世界に登場した後に生まれたとし、自分の絵を説明するためには、その3つのいずれかの用語か、新しい用語を当てはめることができるだろうとしている。
インストラクション、アッサンブラージュ。聞き慣れた言葉だ。マイクロプロセッサのインストラクションをアセンブルすればソフトウェアができあがる。一瞬、ハプニングはクラッシュかと思ったが、そうではなさそうだ。インストラクションミスによるクラッシュは、偶然によるものではなく、必然であり、確実に再現するからだ。
ぼくは、このインストラクションペイントに、パソコンとそれを操作する人間との類似性を垣間見たような気がしたのだ。
●オリジナルの放棄
出版社放送局から支給される原稿用紙に使いにくさを感じるようになったぼくは、 自分専用の原稿用紙を特注するという行動をとった。'85年頃のことだった。
文具店の伊東屋などの店頭に並んでいる市販の原稿用紙から、自分的にもっとも使 いやすい罫のものを選び、それと同じものを、放送局に出入りしていた台本印刷業者 に頼み込んで作ってもらったのだ。用紙も見本を探してきて指定した。そして、紙の 表ではなく裏に罫を印刷するように頼んだ。これは、梅棹忠夫『知的生産の技術』 (岩波書店、'69年)で紹介された京大型カードの方法を真似た。書く面に、紙の裏を 使うことで、滑りが適度になる。しかも、インクで書いた場合も乾きが速く、手を汚 しにくい。さすがに銘入りにする勇気はなかった…。
だが、手元に届いた1,000枚のB4サイズ400字詰原稿用紙は、ついに使い切られるこ
とはなかった。なぜなら、そのあとしばらくして、ぼくは、書く行為のために、鉛筆
を握ることをやめ、キーボードを使って文章を書くようになったからだ。
バックナンバー
(2004年5月28日)
[Reported by 山田祥平]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2004 Impress Corporation All rights reserved.